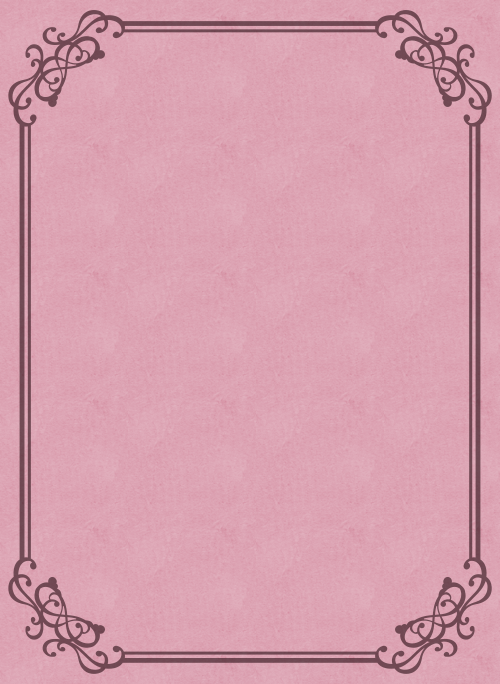「ありがと」
こちらも見ずに俊彦は私の手からコーヒーを受け取った。一瞬だけ触れ合った指先は、人肌にしては冷たい温度で、その指先が私に触れていたかつてを否応無く思い出させる。
だから、時効だってば。
一際強くなる雨の音に混ぜるように、自分にも聞こえない声で唇だけを動かしてそう言い聞かせる。
深くソファに腰掛けて、ひとくちコーヒーをすすった。ほろ苦い豆の香りが口いっぱいを満たしていく。
俊彦と同じで、わたしだってこの味は好きになれない。それでも無理して飲んだのは、あの頃より大人になったのだと信じたいからだ。
「私も、結婚することになったの」
まるで明日の献立を思いついたような、この静かな室内には不釣り合いなしゃきしゃきした声音でそう口にした。
まどろむように落としていた視線を上げて、俊彦はようやっとこちらを見た。
片眉をぴくりと顰めるのは、驚いたときの癖だった。
「そうか」
けれど彼はそう言ってまた本に視線を戻した。
「珍しく俺の家にまで来たのは、その報告?」