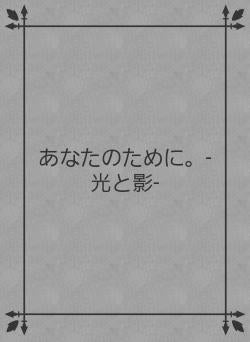「…どうして北村さんは夕里に好きだって伝えないで傍にいたの?
夕里に好きって言って、自分のものにしようとは考えなかったの?」
そうだ。
夕里に頑張って告白して、夕里を振り向かせれば、こんな風にりか達や綾女を巻き込まなくてよかった。
傷つく人なんていなかったんだ。
「もちろんそうしようと思ったわ。
例え振られても、好きって言われた相手のことはちょっとは気にするでしょ?
それを使ってもっとあたしのこと見てもらおうと考えた」
でも……
北村さんは自分の手を見つめて、若干震える手を握り締めた。
「…でも怖かった。
そういう目で俺のこと見てたんだって、俺は紗奈にそういう風にさせるために助けたんじゃないって言われるのが怖かった。
夕里がそういうことを言う人じゃないって分かってても、いつかあたしから離れていくんじゃないかって思うと怖くて言えなかった……
あたしには夕里しかいなかったから…」
強く目を瞑って痛みに耐えるようにして自分自身を抱き締める、北村さん。
……そうか。
北村さんは夕里のために、夕里を道標にして生きてきたんだ。
北村さんにとって夕里は、生きる意味だったんだ。
その生きる意味を誰にも奪われたくなかったから他人を利用して、夕里にまとわりつく女子を遠ざけてたんだ。