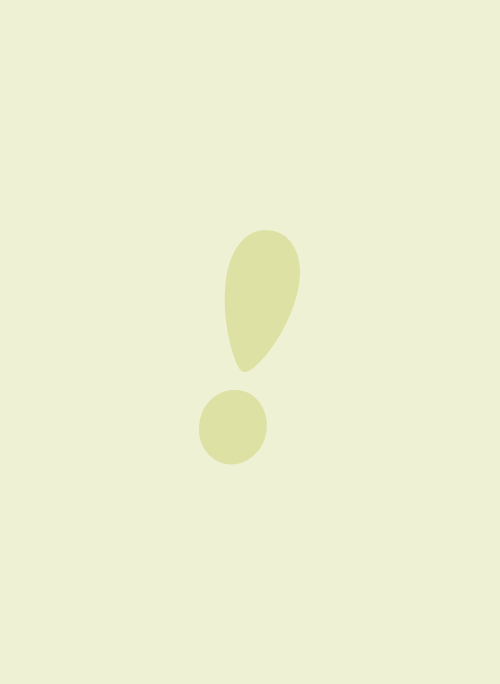「…いや?あんまりそうは思わないけどな。ただもしかすると筋を傷めたかもしれないな。あとで痛み止めの注射でもやっておこうかな。…じゃあ起きていいよ。手を貸そうか?」
いつも渚なら断っていただろう。
だが渚は素直に隼人に助けてもらっていた。
これ以上怪我が悪化するのが嫌、というのもあったのは事実だが、隼人に心配かけたくないという意識が強かった。
隼人は渚を起こしたあとに、いつもと違うことに気付き、思わず口にしたのだった。
「…珍しいな。お前が人の手を借りるなんて…。別に悪いってわけじゃないけど…ていうかお前はそうすべきなんだけど…」
「だって…もう先生に心配かけたくなかったから。先生にはもう存分に甘えることにしたの。もちろん入院中だけだけどね。それでも他の人には甘えたくない!それはある意味、私のポリシーだから。人に弱いって思われたくないの!…なんか力説しちゃったけど、変だったかな?」
渚は顔を赤くしながらそう言った。
いつも渚なら断っていただろう。
だが渚は素直に隼人に助けてもらっていた。
これ以上怪我が悪化するのが嫌、というのもあったのは事実だが、隼人に心配かけたくないという意識が強かった。
隼人は渚を起こしたあとに、いつもと違うことに気付き、思わず口にしたのだった。
「…珍しいな。お前が人の手を借りるなんて…。別に悪いってわけじゃないけど…ていうかお前はそうすべきなんだけど…」
「だって…もう先生に心配かけたくなかったから。先生にはもう存分に甘えることにしたの。もちろん入院中だけだけどね。それでも他の人には甘えたくない!それはある意味、私のポリシーだから。人に弱いって思われたくないの!…なんか力説しちゃったけど、変だったかな?」
渚は顔を赤くしながらそう言った。