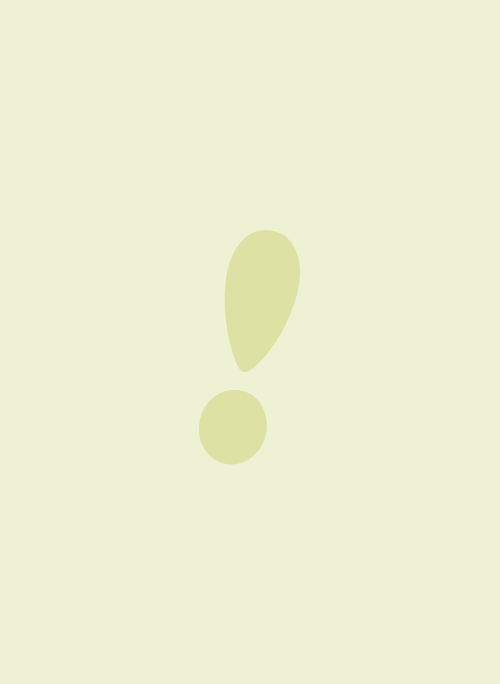しかも人間とは厄介なもので、やるなと言われるとやりたくなるものである。
渚にはその傾向が強いことぐらいは読者の皆様にはお分かりだろう。
渚の手足はやっと曲げることができるぐらいの状態であった。
しかもゆっくりゆっくりやって半分ぐらいまで曲がるかな、という程度だった。
渚は読者の方を含む、みんなの予想通りの行動を始めてしまった。
まだ痛む手で、ベットに力を加え、そこからおりた。
足に負担もかかり、転んでしまった渚だったが、ゆっくりゆっくり立ち上がって、病室のドアの方まで歩いていった。
その歩き方は危なっかしいものだった。
1歩を踏み出す度によろけるような状態だった。
ドアのとこまで行っただけでも疲れて、息をつく有り様だった。
しかし自分の足で歩けてるという感覚がうれしくて、ドアに手をかけて部屋の外に歩き出したのだった。
もちろんドアをあけるのも一苦労だったことは言うまでもなかった。
渚にはその傾向が強いことぐらいは読者の皆様にはお分かりだろう。
渚の手足はやっと曲げることができるぐらいの状態であった。
しかもゆっくりゆっくりやって半分ぐらいまで曲がるかな、という程度だった。
渚は読者の方を含む、みんなの予想通りの行動を始めてしまった。
まだ痛む手で、ベットに力を加え、そこからおりた。
足に負担もかかり、転んでしまった渚だったが、ゆっくりゆっくり立ち上がって、病室のドアの方まで歩いていった。
その歩き方は危なっかしいものだった。
1歩を踏み出す度によろけるような状態だった。
ドアのとこまで行っただけでも疲れて、息をつく有り様だった。
しかし自分の足で歩けてるという感覚がうれしくて、ドアに手をかけて部屋の外に歩き出したのだった。
もちろんドアをあけるのも一苦労だったことは言うまでもなかった。