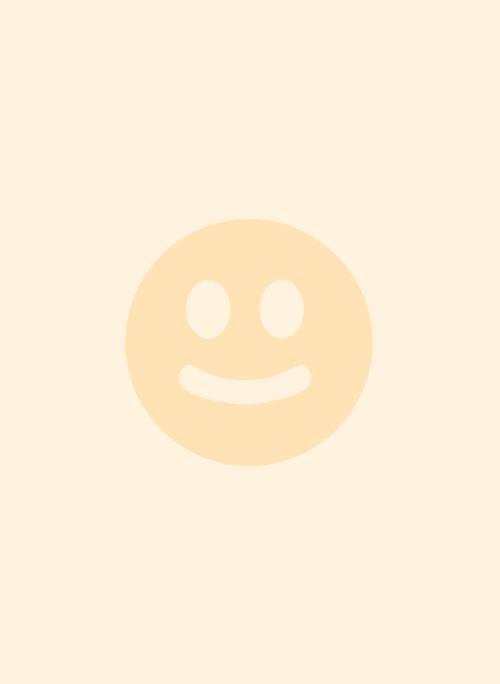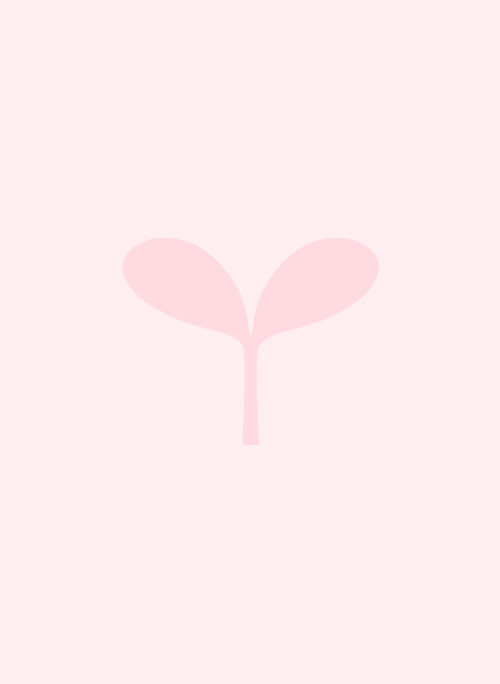美しいが、生気のない彫像の唇が微かに開いたのを、日向は見た。
聞こえないはずの低い声を、確かに聞いた。
『誰かが誰かを憎んで
いったい誰が幸せになれんの?』
だから、日向は動いた。
眉を顰めた杏子が、ナニか言い出すより早く。
ついさっきの由仁のように、スタスタ歩いて。
背筋を伸ばして、瑠璃子の前に立って。
「なに」
ガっ!!!
「ぶっ?!」
『なによ』と、瑠璃子は言いたかった。
だが、最後まで言えずに変な声を上げて顔を仰け反らせた。
日向の強烈な頭突きを食らったから。
着物の襟を片手で掴み、よろめく瑠璃子を引き寄せた日向が、鼻と鼻が接触しそうなほどの至近距離で彼女を睨む。
「ザケんな、コラ。
ナメた口利いてンじゃねーゾ。」
「は… は?」
「そーだよ、先輩はケダモノだよ。
『男の中の漢』的な、立派なケダモノだよ。
そこのクズやヘタレと一緒にしてンじゃねーよ。」
「ちょ… あの… あの?」