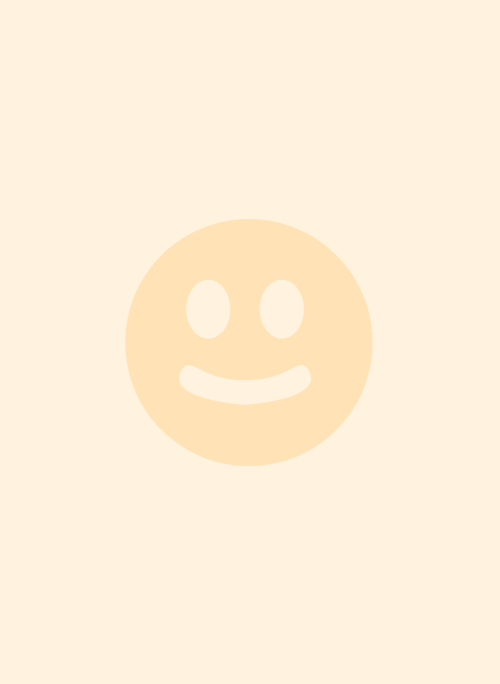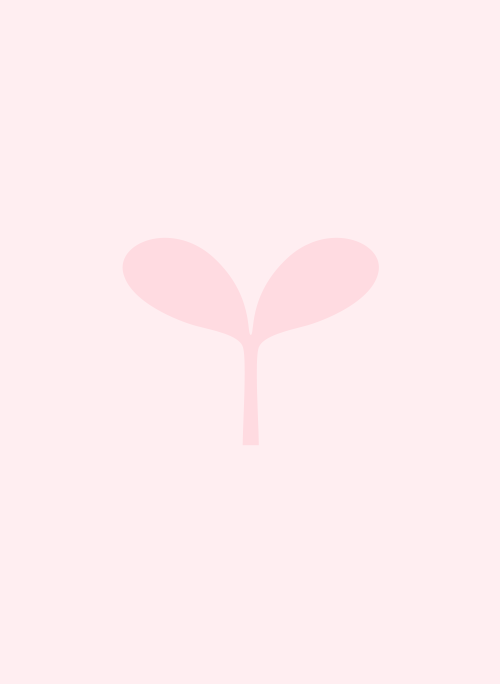「ところで一年女子。
こんな居心地が悪そうな場所で よくノンキに食事できるな。」
やっと百合に解放されてズルズルとラーメンを啜りだした日向に、割り箸をパチンと割った樹が言った。
彼も、この異様な雰囲気に気づいているのだ。
いや、気づかないはずがない。
だって今も日向は、恨みがましい多くの目で一挙一動をガン見されているのだから。
ひょっとしてこの二人…
心配して、声を掛けてくれたのカナ?
「気にしてませんから。
てかココが戦場でも、きっとなんでも食べますよ、私。」
箸でメンマをつまみながら、あっけらかんと日向が笑った。
けれど、隣の百合は眉をひそめる。
「でも、コレはサスガにあんまりよ。
ジンはなんて言ってンの?」
え…
なんて言ってるもナニも…
「久我先輩は知りませんよ、このコト。」
「「はぁ?」」
「え… ハイ?」
声を揃えた樹と百合に真顔で迫られ、日向は若干身を引いた。
なんか…
悪いコト言いマシタカ?