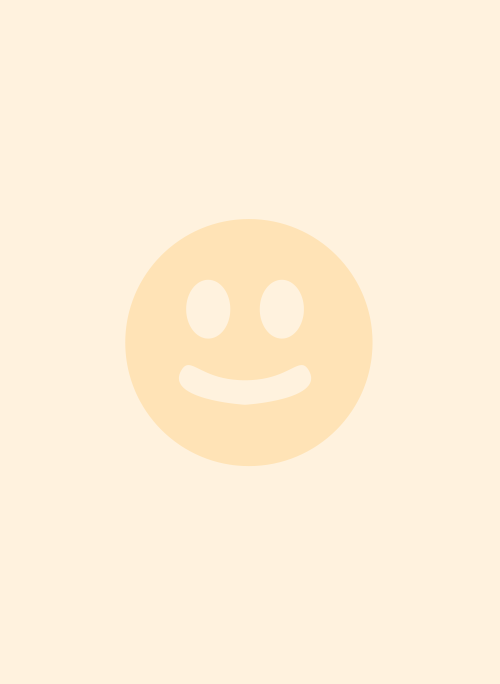一日に三本しか走っていないバスを降り、その村に一軒しかない宿に鼻唄を歌いながら向かっている最中、私は今まで感じたことのない感覚に襲われて立ち竦んだ。
注意深く、辺りを見回す。
舗装されていない、土埃が舞い上がる一本道。
右側には鬱蒼と生い茂る木々。
左側にはちょっとした崖と、その下に流れる小川…
私はナニカに導かれるように、崖の下を覗き込んだ。
人が倒れている。
女が、倒れている。
…
死んでンの?
あの女の霊が呼んだの?
いや、違う。
あの感覚はそんなモンじゃなかった。
もっと強大な。
言うなれば、神に近いような…
だが今は、考え込んでいる場合ではない。
助けを呼ばなければ。
私は携帯電話を取り出した。
が!
まさかの圏外─────?!
まぁ、当時は珍しいコトでもなかった。
携帯するコトが前提のわりに、結構デカかった時代だしネ。
しょーがない。
そんなに高くもないし、傾斜も緩い。
私は躊躇うことなく崖を下りた。
手を伸ばし、確認する。
女は死んでいた。
頭から血を流し。
腹を裂かれ。