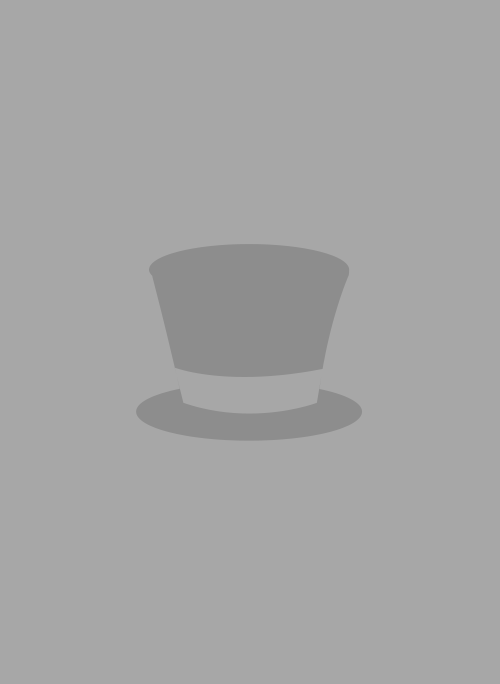――リーン、リーン。
エプロンに入れていた携帯が鳴る。
美紀は手を拭くためのタオルを取ろうと調理台の下の取っ手に手を延ばした。
流しの調理台の上には、ラップの掛かった野菜サラダと一緒にシェーカーが置いてあった。
この中にドレッシングの材料を入れて振るだけになっていた。
家庭菜園で採れるレタス・トマト・胡瓜。
手作りドレッシング。
どれ一つとってもそこには珠希の影があった。
手を拭きながら携帯電話を開ける。
表示にはパパとあった。
美紀は少し困ったような顔をした。
プロレスの試合のない日の夕食前の正樹の電話。
それは何時も決まっていた。
『遅くなる』
だった。
「困ったパパだね、ママ」
美紀はラップを手に持ち、リビングにあるローテーブルに向かった。
「ママ、パパって何時もこうだった?」
美紀は仏間の方に目をやった。
食事中は何時も仏間の襖は開けられていた。
一緒に居てほしいと願ってのことだった。
陰膳は同じ種類用意した。
美紀は珠希を引きずっていた。
美紀だけではない。
家族全員が、珠希との思い出の中に生きていたのだった。
「あっパパ。え、少し遅くなるの? うん分かった」
(やっぱりだ。何時もそう思う。でも今日は、ママの誕生日だよ)
そう言ってやりたかった。
美紀はガッカリしながら、ローテーブルの上の母直伝の料理をラップで覆った。
それらは全部美紀の手作りだった。
(冷めたら美味しくないのに)
美紀は溜め息を吐いた。
美紀も珠希同様、家族の元気のために頑張っていたのだった。
秀樹はご馳走が気になり、さっきから台所をウロウロしていた。
「え、パパ遅くなるの?」
美紀の受け答えを聞いてガッカリしながらラップを開けて見る。
「秀ニイ! 全く油断も隙もない」
秀樹はとうとう、美紀の怒りをかって其処から追い出されてしまったのだった。
秀樹のつまみ食いを見逃す余裕さえもない。
何時もの寛大は母心に似たゆとりさえ無くしていたのだ。
美紀はそれほどガッカリしていた。
美紀はその後へなへなと座り込んでいた。
秀樹と同じようにローテーブルのご馳走を覗く。
(どうしてなんだろう? 何でママから教えられた料理だけなんだろう?)
美紀は自分の行動が不思議でならなかった。
エプロンに入れていた携帯が鳴る。
美紀は手を拭くためのタオルを取ろうと調理台の下の取っ手に手を延ばした。
流しの調理台の上には、ラップの掛かった野菜サラダと一緒にシェーカーが置いてあった。
この中にドレッシングの材料を入れて振るだけになっていた。
家庭菜園で採れるレタス・トマト・胡瓜。
手作りドレッシング。
どれ一つとってもそこには珠希の影があった。
手を拭きながら携帯電話を開ける。
表示にはパパとあった。
美紀は少し困ったような顔をした。
プロレスの試合のない日の夕食前の正樹の電話。
それは何時も決まっていた。
『遅くなる』
だった。
「困ったパパだね、ママ」
美紀はラップを手に持ち、リビングにあるローテーブルに向かった。
「ママ、パパって何時もこうだった?」
美紀は仏間の方に目をやった。
食事中は何時も仏間の襖は開けられていた。
一緒に居てほしいと願ってのことだった。
陰膳は同じ種類用意した。
美紀は珠希を引きずっていた。
美紀だけではない。
家族全員が、珠希との思い出の中に生きていたのだった。
「あっパパ。え、少し遅くなるの? うん分かった」
(やっぱりだ。何時もそう思う。でも今日は、ママの誕生日だよ)
そう言ってやりたかった。
美紀はガッカリしながら、ローテーブルの上の母直伝の料理をラップで覆った。
それらは全部美紀の手作りだった。
(冷めたら美味しくないのに)
美紀は溜め息を吐いた。
美紀も珠希同様、家族の元気のために頑張っていたのだった。
秀樹はご馳走が気になり、さっきから台所をウロウロしていた。
「え、パパ遅くなるの?」
美紀の受け答えを聞いてガッカリしながらラップを開けて見る。
「秀ニイ! 全く油断も隙もない」
秀樹はとうとう、美紀の怒りをかって其処から追い出されてしまったのだった。
秀樹のつまみ食いを見逃す余裕さえもない。
何時もの寛大は母心に似たゆとりさえ無くしていたのだ。
美紀はそれほどガッカリしていた。
美紀はその後へなへなと座り込んでいた。
秀樹と同じようにローテーブルのご馳走を覗く。
(どうしてなんだろう? 何でママから教えられた料理だけなんだろう?)
美紀は自分の行動が不思議でならなかった。