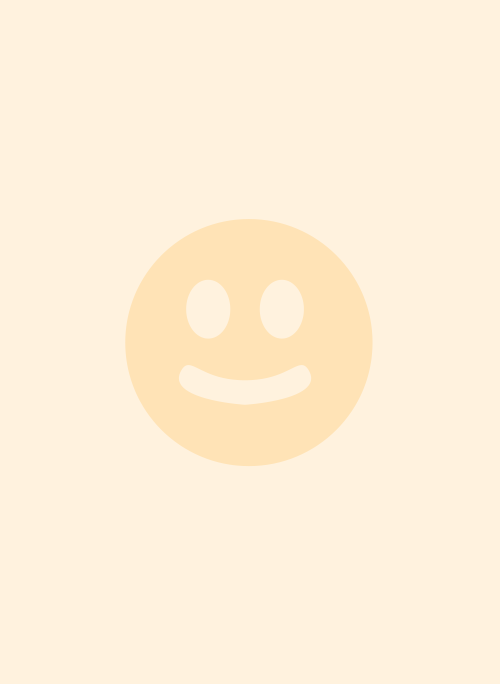「こーうーちゃん!あーそーぼ♪」
調子外れな声が玄関先で響く。
宿題もそこそこに、俺は走って玄関へと向かった。
「耕介!走らないの!」
母さんの声なんて無視して、俺は慌てて靴を履いた。
「千秋!早く行こう!母さんに捕まっちゃうよ!」
「うん!ごめんねおばちゃん!こうちゃん連れてくねー!」
俺は頭一つ背の低い女の子と共に、元気よく夏空に走り出していった。
はっきりした記憶に残っているのは、小学校低学年の頃だ。
気がつけば、彼女は常に側にいたように思う。
矢崎千秋。
俺より三つ年下の女の子。
家が近所って事もあり、しょっちゅう顔を合わせていた。
といっても、近所には年上の男友達や同級生も大勢いた。
そんな中で、確実に毎日俺のそばにいるのは千秋だけだった。
「こうちゃん、昨日の子また来てるかな?」
よく日焼けした、活発そうな表情。
くるくると元気よく動く瞳で、千秋は俺を見た。
俺の名前は「織田耕介」なので、近所のおばちゃんや千秋のお母さんは「こうちゃん」なんて呼んでいる。
千秋もそれに習って、俺の事は「こうちゃん」と呼ぶ。
「来てるかもな。今度こそやっつけないと」
千秋の手前、俺はよく偉そうぶって言っていたのを覚えてる。
調子外れな声が玄関先で響く。
宿題もそこそこに、俺は走って玄関へと向かった。
「耕介!走らないの!」
母さんの声なんて無視して、俺は慌てて靴を履いた。
「千秋!早く行こう!母さんに捕まっちゃうよ!」
「うん!ごめんねおばちゃん!こうちゃん連れてくねー!」
俺は頭一つ背の低い女の子と共に、元気よく夏空に走り出していった。
はっきりした記憶に残っているのは、小学校低学年の頃だ。
気がつけば、彼女は常に側にいたように思う。
矢崎千秋。
俺より三つ年下の女の子。
家が近所って事もあり、しょっちゅう顔を合わせていた。
といっても、近所には年上の男友達や同級生も大勢いた。
そんな中で、確実に毎日俺のそばにいるのは千秋だけだった。
「こうちゃん、昨日の子また来てるかな?」
よく日焼けした、活発そうな表情。
くるくると元気よく動く瞳で、千秋は俺を見た。
俺の名前は「織田耕介」なので、近所のおばちゃんや千秋のお母さんは「こうちゃん」なんて呼んでいる。
千秋もそれに習って、俺の事は「こうちゃん」と呼ぶ。
「来てるかもな。今度こそやっつけないと」
千秋の手前、俺はよく偉そうぶって言っていたのを覚えてる。