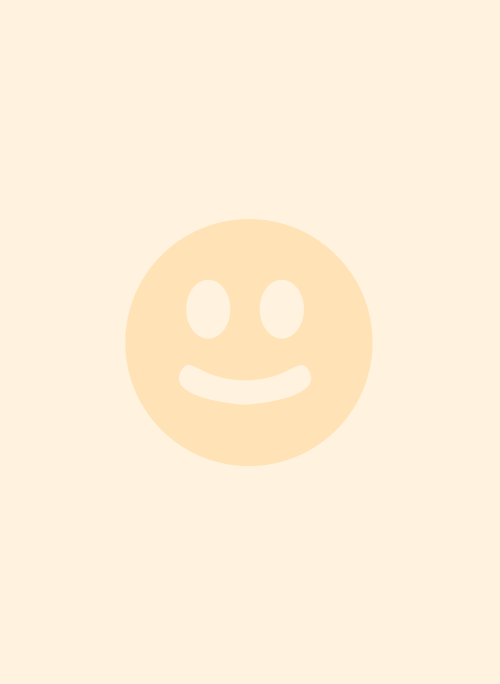その後、何度もマリーに事情を話そうとしても取り合ってもらえず、洗った洗濯物を各部屋に届ける役目を押し付けられた。
ティアラはそこで誰かに会えばきっとわかってもらえると思い各部屋を回った。
一室目は誰もいなかった。
二室目も誰もいない。
三室目は朝に案内された部屋だ。
微かに声が聞こえた。
パッと明るく希望が差し込んだかのようだった。
扉を開けるとドレスを着た赤毛の少女がまたもドレスを着た年配の女性と話をしていた。
二人はティアラの存在に気付き不思議そうにした。
『あら。ノックもせずにはしたなくてよ。』
貴婦人はティアラを咎めた。
『もしや夫人はマーキング夫人ではありませんこと?』
ティアラは洗濯物を床に置き、話をしようと佇まいを直した。
その時だった。
『何をしているの!』
背後から大きな声がした。
そこには息巻いたマリーが洗濯物の山を抱えて立っていた。
『わたくし、、、』
とティアラが言いかけてマリーが遮った。
『奥様。失礼致しました。今、すぐに仕事に戻ります。』
さぁ!とマリーはティアラを引っ張る。
そんな状況の中でティアラは赤毛の少女に驚くべき発見をした。
赤毛の少女はブルーのドレスに白い手袋をはめていた。
よく見覚えがある。
私のドレスだわ!
と悲鳴を上げそうになるのをぐっと堪えた。
『あ、、、あの!』
なんと申し開きをしようかと口をパクパクしていると赤毛の少女が言った。
『早くお仕事に戻った方がいいわ?』
その声は服を運んできたメイドのものだった。
ティアラは信じられない思いでいっぱいになった。
夫人はにこやかに微笑むと『新人さんなのね?珍しい物でもあったかしら。』などと言っている。
『きっとこんなに素敵なお屋敷には勤めたことがなかったんですわ。』
赤毛の少女はそう言ってそばかすだらけの顔を歪ませた。
私はマリーの手が頭にのってお辞儀させられたことで何も話せず、二人は私には目もくれずに室外へと行ってしまった。
マリーに部屋に人がいる時は入ってはいけないだの、お辞儀も知らないのかだの言われてもちっとも頭に入らなかった。
ただティアラは理解していた。
あのメイドに自分は陥れられたのだと。
ティアラはそこで誰かに会えばきっとわかってもらえると思い各部屋を回った。
一室目は誰もいなかった。
二室目も誰もいない。
三室目は朝に案内された部屋だ。
微かに声が聞こえた。
パッと明るく希望が差し込んだかのようだった。
扉を開けるとドレスを着た赤毛の少女がまたもドレスを着た年配の女性と話をしていた。
二人はティアラの存在に気付き不思議そうにした。
『あら。ノックもせずにはしたなくてよ。』
貴婦人はティアラを咎めた。
『もしや夫人はマーキング夫人ではありませんこと?』
ティアラは洗濯物を床に置き、話をしようと佇まいを直した。
その時だった。
『何をしているの!』
背後から大きな声がした。
そこには息巻いたマリーが洗濯物の山を抱えて立っていた。
『わたくし、、、』
とティアラが言いかけてマリーが遮った。
『奥様。失礼致しました。今、すぐに仕事に戻ります。』
さぁ!とマリーはティアラを引っ張る。
そんな状況の中でティアラは赤毛の少女に驚くべき発見をした。
赤毛の少女はブルーのドレスに白い手袋をはめていた。
よく見覚えがある。
私のドレスだわ!
と悲鳴を上げそうになるのをぐっと堪えた。
『あ、、、あの!』
なんと申し開きをしようかと口をパクパクしていると赤毛の少女が言った。
『早くお仕事に戻った方がいいわ?』
その声は服を運んできたメイドのものだった。
ティアラは信じられない思いでいっぱいになった。
夫人はにこやかに微笑むと『新人さんなのね?珍しい物でもあったかしら。』などと言っている。
『きっとこんなに素敵なお屋敷には勤めたことがなかったんですわ。』
赤毛の少女はそう言ってそばかすだらけの顔を歪ませた。
私はマリーの手が頭にのってお辞儀させられたことで何も話せず、二人は私には目もくれずに室外へと行ってしまった。
マリーに部屋に人がいる時は入ってはいけないだの、お辞儀も知らないのかだの言われてもちっとも頭に入らなかった。
ただティアラは理解していた。
あのメイドに自分は陥れられたのだと。