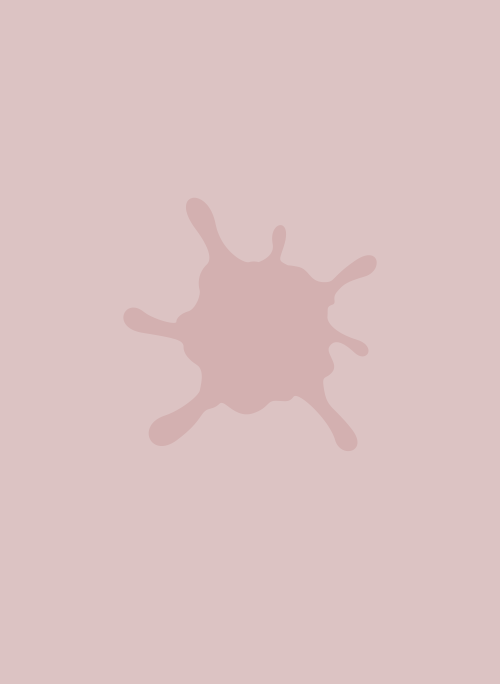無意識に夜景に向かって手を伸ばしたとき、チラリと指先が光って見えた。
その光の正体を知るのに幾許もかかることはなかった。
光は、消えていくリオンの指先。
痛みは無い。
ただ、光の粒に変わっていく手を眺めながら、自分が青の庭のものと同じ、幻だったのだと知ってしまったことが辛かった。
落ちる速度は徐々に上がっていく。
下の海から吹きつける風に光の粒は舞い上がり、リオンの視界を遮っていく。
その中に見慣れたものがよぎる。
いびつな形の、薄青色のガラス瓶。
下の世界のものは光にならずにただ、宙に投げ出された。
リオンは掴もうとまだ形のある反対側の腕を伸ばす。
けれどあと少しで届く距離で、指先から光へと変わり、再び距離は開いていく。
どうにかして触れようと、必死に腕を動かす度に光は揺れて、消える。
瓶はリオンの追いつけない速さで海へと落ちていった。
そしてまた視界には小さな宝石を撒いたように煌く夜景が映る。
――あの光のどこかに、マナはいるのかな。
「……マナ」
呼び声は、吹き付ける風よりもずっと小さい。
全身が、光を帯びていく。
――待っていて。会いに行くから。
声にならない言葉が光と共に夜に溶けていった。
その光の正体を知るのに幾許もかかることはなかった。
光は、消えていくリオンの指先。
痛みは無い。
ただ、光の粒に変わっていく手を眺めながら、自分が青の庭のものと同じ、幻だったのだと知ってしまったことが辛かった。
落ちる速度は徐々に上がっていく。
下の海から吹きつける風に光の粒は舞い上がり、リオンの視界を遮っていく。
その中に見慣れたものがよぎる。
いびつな形の、薄青色のガラス瓶。
下の世界のものは光にならずにただ、宙に投げ出された。
リオンは掴もうとまだ形のある反対側の腕を伸ばす。
けれどあと少しで届く距離で、指先から光へと変わり、再び距離は開いていく。
どうにかして触れようと、必死に腕を動かす度に光は揺れて、消える。
瓶はリオンの追いつけない速さで海へと落ちていった。
そしてまた視界には小さな宝石を撒いたように煌く夜景が映る。
――あの光のどこかに、マナはいるのかな。
「……マナ」
呼び声は、吹き付ける風よりもずっと小さい。
全身が、光を帯びていく。
――待っていて。会いに行くから。
声にならない言葉が光と共に夜に溶けていった。