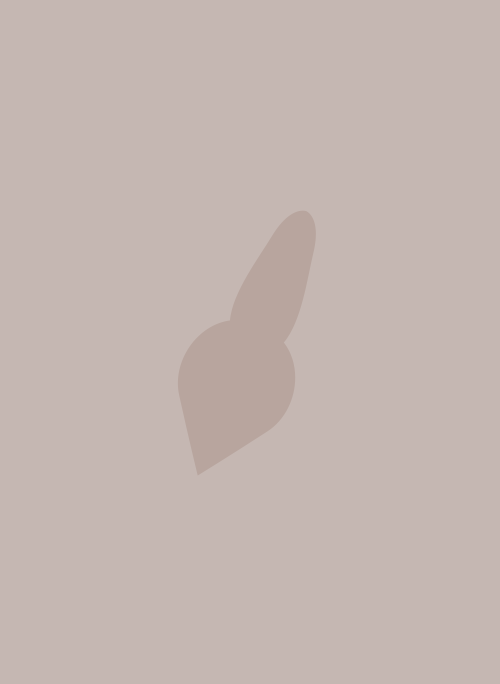「おい。」
「……」
「おい。こら。」
「…なんですか?」
朝日が昇り始めた頃、小さな花園ではまたもめごとが始まりそうになっていた。
「お前まさかその木切るんじゃねぇだろうなぁ?俺焦げて死んじまうぞ?」
噴水の近くで、力強く咲き乱れている桜の木が揺れる。
「はい。少し邪魔になってきたんで。」
その桜の木の下で爽やかに微笑む青年。
細く、長い手脚に小さく、整った顔。
切れ長の茶色の瞳は澄んでいる。
「お前は大丈夫かもしれねぇが俺は焦げる。考えろ。」
桜の木の上の方に目をやると、小柄な青年が、木の枝に座っていた。
華奢な身体つきに、白銀の髪から覗く、ギラリと光る真っ赤な瞳は吸い込まれそうなほど大きい。
「でも、花園の美しさの方が大事ですし…」
「お前は俺より花の方が大事なのか!」
「はい。」
満面の笑みで、即答した青年が枝の上の青年に木から降りるように呼びかける。
「そんなとこにいたら見張りの意味ないですよ。ナイトはこの花園の管理人なんですから。」
「それを言うならお前もだろうが。」
“ナイト”と呼ばれた白銀の髪の青年が桜の木から飛び降りる。
着地と同時に青色の花びらが舞う。
「ったく。コートが汚れちまった。」
ナイトが真っ黒なコートを両手で払う。
「ちょっと!花踏まないで下さいよ!!」
それを見て青年が怒鳴る。
「あぁ?んなこたぁいいんだよ。」
ナイトが舌打ちをし、ズカズカと花畑の真ん中を突っ切る。
「あー!ナイトったら!!」
青年がナイトにまた怒鳴る。
だが、そんな青年の声を無視してナイトはまた別の木陰を探し出す。
「……」
青年が、持っていた小さくて可愛らしい如雨露をその場に放り投げる。
そしてスタスタとナイトに近付き、乱暴に腕を掴んだ。
ナイトが動きを止める。
「なんだぁ?」
ナイトが顔を顰めながら振り返る。
「…嫌な予感がするんです。」
「珍しいこと言うじゃねぇか。どうした?」
ナイトも急に真剣な顔つきになり、青年の瞳をまっすぐ見つめている。
「ここ数百年で味わなかった予感です。」
「…なるほど。お前の勘はよく当たるからなぁ。」
そんな会話をしている内にナイトの肌はジリジリと音をたてて焦げ始めた。
本人は慣れているのか、全く気にしていない。
青年は不安そうに、力強くナイトの腕を握り締めると、俯いた。
「また…また“奴ら”が襲って来るんですか……?」
ポツリとナイトの腕に冷たい液体が零れる。
その液体は青年の涙で、絶えることなく流れ続けている。
「まだ決まった訳じゃねぇだろ?」
それを励ますようにナイトが青年の頭をポンポンと撫でる。
「…もし“奴ら”が、この箱庭を汚すようなことしたら俺が黙っちゃいねぇよ。」
ナイトは吐き捨てるように呟いた。