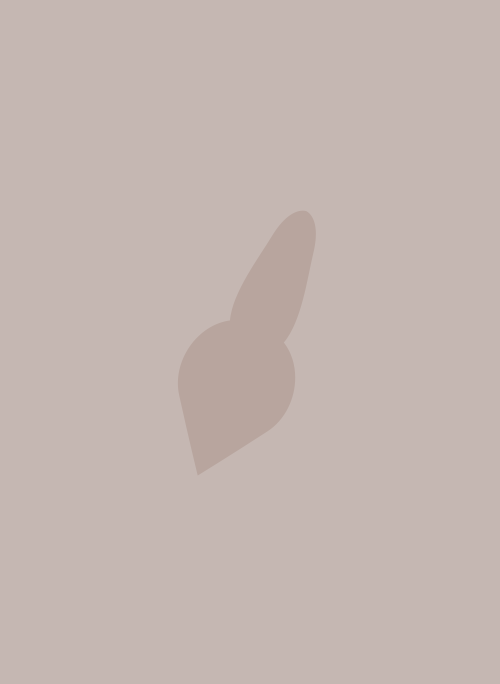「…それから俺とあいつは城の庭へ抜けた。」
今でも、鮮明に覚えているのだろうか、どこか一点を虚ろな目で見つめ、ゆっくりと語る。
隣りでは、辛そうに顔を顰める花村が、その場にしゃがみこんでいた。
「やっと助かる。逃げられるって思ったその時だ……
あいつが俺に向かってナイフを向けて来たんだ。」
信頼していた最後の味方にさえも裏切られた、その時のナイトの気持ちはどんなものだったのだろうか。
絶望?
落胆?
後悔?
きっと、言葉では表せないほどだっただろう。
「“お前は母さんを殺した醜い化け物だ。母さんの仇は俺がとる。”
そう怒鳴り散らして俺の懐を狙ってきやがった…」
「その時に…僕の兄がナイトを助けたんです……」
花村が呟く。
「んで、そこからこれは吸血鬼の城にいって、無事保護されたって訳よ。
はい、おしまい。」
きっと、この事件は誰も悪くない。
運命の悲劇なのだ。
ナイトは、はぁ、と息を吐くと、俺の前でしゃがみこんだ。
「その事件をきっかけに、両一族の仲は急激に悪くなり、互いの一族を傷つけ合うようになった。」
「ある日、ナイトの命が狙われたのです。
“神の子”は両一族の“心臓”とも言える重要な人物。
殺して一族を滅ぼすことが目的だったのでしょう。」
「で?どうなったん?」
目の前にナイトガいる時点で無事だったことは分かるのだが、取り敢えず聞いておく。
「私の兄が死にました。
他にもナイトに仕える者のほとんどが命を落としました。
…そこで、王はナイトを幽閉することを思いついたのです。」
花村が立ち上がり、外の花園を眺め始めた。
「幽閉って…」
「だが、幽閉してしまったら俺に一族を継げる力が身につかねぇだろ?だから、“あっち側”の神の子も探しながらここの箱庭に身を隠してるんだ。」
中々話の内容がややこしくなってきた。
「要は、ナイトさんと花村さんはここに隠れながら、その、敵の“メア”って奴を探してるってこと?」
「そうだ。」
ナイトは俺の頬をつねると、ニコッと微笑んだ。
「それであっち側が強力な野郎を味方につけたそうなんだ。
だから、俺らも強力“そうな”助っ人をここに連れてきた訳よ。」
「もしかして…その助っ人って…」
二人がニヤリと笑う。
「柴田凛。あんただ。」