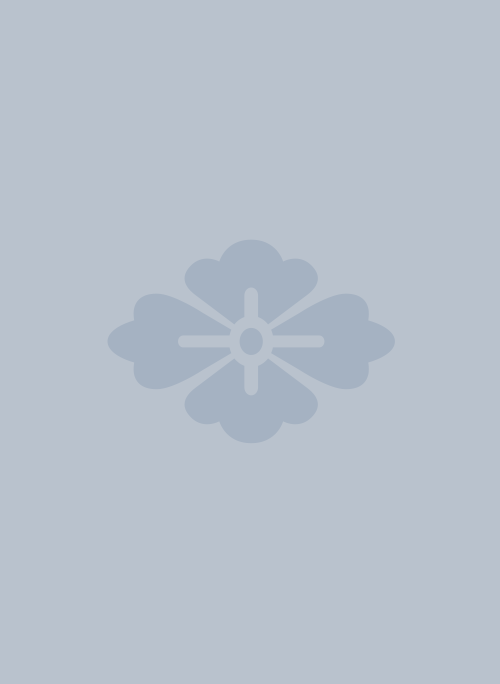けったいな話が来た。
梅雨ぐもりの蒸し暑い日、翔一郎はとうとう引っ張り出される感じで、東京までテレビの番組へ出さされる羽目になったのである。
エマは心配そうな顔をしたが、
「やっつけ仕事やし、あんじょうチャッチャとやって早よ済ますわ」
そういうと、車中の人となっている。
当日。
東京のテレビ局には入館証というものが要るらしく、煩わしく思ったのか少し面倒がりな翔一郎は、
「いちいちそんなんややこしいことしやなあかんのやったら、出んかて食うのは困らんし、別に出んでもよろしがな」
といって踵を返し、京都へ帰ろうとしたので、ついてきていたプロデューサーを大慌てさせた。
こういうところが、
──京都の饗庭は、相手が誰であろうが媚びない。
と見られており、支持が高い反面ややもすると鼻持ちならないようにも見られるらしい。
が。
「昔から人間の評価は、本人が棺桶におさまらんと定まらんもんや」
いちいち生身の人間のえこひいきなんぞ聞いてられるか、ととどめを刺すこともあった。
テレビの業界の人間にすれば、歯に衣を着せぬ物言いは諸刃の剣で、
(京都からえらい面倒なの連れてきたな)
というのが本音であったらしい。
生放送が始まった。
翔一郎は連れてこられた、というのがあって、そのくせ話もろくに振られないので、不機嫌そうに雛壇に座っている。
しかも。
さすがに退屈なのか、一つ大あくびをした。
すると。
司会者に咎められた。
「饗庭さん…あくびって」
「なーに、下らんからあくびが出たまで、気に入らんなら帰るだけや」
というが早いか、さっと雛壇を立って、翔一郎は消えてしまった。
たちまちスタジオは騒然となる。
ディレクターが飛んできて、
「ちょっ…ちょっと、饗庭さん!」
取りすがった。
「なんでもかんでも東京が偉い思ったら、あんさん大間違いやで」
それだけいい残すと、その足で京都まで帰ってきてしまったのである。
当然、問題になった。
──なんと傲慢な奴だ。
という抗議ももちろん半数近くあったが、
「あれだけ自己の意見があるのだから、何があってもブレないだろう」
という賛意も寄せられ、例のガバチョの旅シリーズのヒットもあって、いつのまにやら知る人ぞ知る人物になっていたのであった。
西陣に帰ってきた。
「おかえりー」
エマはいつも通りに迎えた。
翔一郎が東京で何をしてきたかは、萌々子やあさ美からメールやら電話やらが来て、すでに知っている。
が。
「…なんかさ、翔くんって価値観がハッキリしてるよね」
そういうトコ嫌いじゃないよ、とエマはいった。
「…おぉきに」
翔一郎は初めて顔がほころんだ。
「昔さ、食べ物でも何でも好き嫌いはダメって言われたりしたけどさ、翔くんは好き嫌いってダメとか言われた?」
「なんや藪から棒に」
といいながらも、
「うちのオカンが好き嫌いやたらあったから、お前は好き嫌いは遺伝やし諦めぇっていわれた」
エマは吹き出した。
「…それじゃ、好きなものしか食べなかったってこと?」
「ま、そういうことやな…けど別に死なんかったし、大病もせなんだし、これがキャラやと思えば何の世話も苦労もあれへん」
ストレス抱えて生きる方がよっぽどアホ臭くてかなんわ、と翔一郎はとりつく島もない様子でいった。
「翔くんって子供みたい」
「しゃーないやないか、えぇモンはえぇけどアカンもんはアカン、それだけのこっちゃ」
「それはそうだけど…」
「そういうエマかて、まだ成人式やってへんやないか」
すかさずやり返した。
「…って、まるで花月の夫婦漫才やな」
オチがつくとエマは、笑うしかない。
半月ほど過ぎた。
出席の日数の関係で遅れていたエマの卒業式が無事に片付いて、エマは本格的に翔一郎の事務所で帳簿付けやら電話番やらサポートに回り始めた。
といって、作業の中身は大した変わらない。
何かしら撮影に行く翔一郎の毎日も、変わりようがないぐらい変わらない。
ところが。
翔一郎が写真の整理をしていると、キッチンから何か割れる音がした。
急いで行くと、茶碗が割れている。
「エマ、怪我せえへんかったか?」
「あたしは大丈夫」
でも翔くんの茶碗が…と、エマはひどく落ち込んでいた。
「あー…これ、おれが芸大の頃から使ってた、古道具屋で百円まで値切った安モンや」
こら寿命やな、と翔一郎はフラットにいった。
「でも…」
「んなエマが無事やったらええのや」
割れたら茶碗なんぞサラ品買うたらええがな、といいかけて、何か思いついたらしく、
「せや」
二人でなんぞお揃いのモン作らへんか、といった。
「えっ?」
「うちら一緒になってしばらく経つけど、好き連れで指輪も式もあれへんから、せめて何かしら夫婦らしいもん作らなあかんなって」
どやのん?──翔一郎はうつむいたエマの顔をのぞきこんだ。
「…夫婦茶碗とか?」
「茶碗なんぞ、また安モン探せばえぇ」
うちらだけのモン作ればええがな、と翔一郎はエマの手をとった。
エマと翔一郎が出掛けたのは、清水寺の近くの京焼の安幕部窯という窯である。
「あんまくぶ…?」
「これな、あまかべって読むのや」
芸大の頃の後輩や、というと暖簾をくぐった。
「おじゃましますで」
「あ、饗庭さんご無沙汰です」
奥から出てきたのは女将である。
「先日はお電話でわざわざご連絡までいただいて」
「いやいや。ほんで窯元いてます?」
「いますよ」
呼びに奥へ再び消えた。
しばらくすると、
「饗庭先輩、久しぶりです」
「安幕部お前、元気そうやないか」
出てくると、どうも安幕部薫です、とみずから自己紹介した。
「仲間内では安幕部薫と青島薫とでダブル薫って呼んでたんやけどな」
「まぁ立ち話もなんですし、奥にどうです?」
奥の間へ招き入れた。
茶が出てくる。
「まさか夫婦で来やはるとは」
「まあな。で、例の電話で話したアレやけど…」
「それやったら、茶碗よりこういうのがえぇかなって思いまして」
安幕部が出してきたのは、皿に文字と針がついた時計である。
「よう思いついたなあ」
「清水焼って、海外の人がよう買わはるんです」
ほんで万国共通やったら時計やろ、というので作ってみたらしい。
「でも店には並んでなかったですよ」
エマが訊いた。
「まだ実用ではあれへんのですけど、先輩やったら何かアドバイスもらえるかなと」
「うちはモルモットか」
抜け目ないなぁ、と翔一郎は笑った。
「まぁえぇ、今回は実験に協力したるわ」
「ほんまおぉきに」
安幕部は深々頭を下げた。
例の作品が出来た、というのでエマと翔一郎は安幕部窯まで再び出かけた。
「無事に窯出しが済みまして、出来栄えだけ見てもらおうかと思いまして」
奥から桐箱に入って出てきた。
「字が下手やから箱書きに手間かかりましたがな」
そういいながら、落款まで丁寧に捺されてある。
箱を開けた。
「お二人に書いてもらった絵付けは、えぇ色が出ました」
いわゆるペルシャブルーの地に、紫の数字と銀色の針がよく映える正方形の時計皿である。
そこには二人で安幕部薫の指導を受けながら描いた蝶の絵があった。
よく見るとうっすら竹の図柄が彫られてあり、裏側は安幕部窯の朱印もある。
「これ…うちらの頭文字じゃない?」
よく見ると文字盤に、
「S&E」
というロゴがある。
「こんな綺麗に字が出るとは思わんかったで」
「こういうのもよろしですな」
「で、代金の件やけど」
代わりに写真が欲しいいうてたからこれ持ってきたで──そういうと、風呂敷にくるまれた、大きな現物を拡げた。
「こら見事や…」
霧の北山の杉林が撮された枕屏風である。
「これやったら作品飾るのにも使えるやろと思って、写真を引き延ばして屏風に表装してもろた」
確かにモノトーン調なら、釉薬や絵付の華やかな清水焼の邪魔にはならない。
京焼を知らなければ選べないチョイスであろう。
「これはえらいモンもろたなあ」
「気にせぇでえぇがな」
時計をしまうと、翔一郎とエマは安幕部窯を辞去した。
雨は上がっていた。
「ね、鴨川の河原にでも行こうよ」
「何やいきなり」
「たまにはのんびりデート気分で、観光もいいかなって」
「…せやな」
茶碗坂を下り切った先に五条坂が見えてくる。
結びつけられた風鈴の短冊には「絆」という字が、ちらほら書かれてあった。
「…絆、かぁ」
「?」
「ほんまは絆って馬の脚を繋ぐ紐って意味なんやけどな」
「そうなの?」
エマは目を丸くした。
「馬の脚を繋ぐ紐はすぐ切れよる、せやからすぐまた新しい紐で繋ぐらしいのやけどな」
「ふーん」
翔くん変なこと知ってるね、とエマは呟いた。
「じゃあ、人間の絆も古いのが切れたら、新しい絆を作ればいいのかも知れないね」
「…そこは、考えつかなんだな」
いったいおもろいこというやっちゃで、と翔一郎は笑った。
五条の大通の少し先には、鴨川がある。
大和大路の赤信号が変わった。
エマと翔一郎は、青信号に変わった交差点を、川端通を目指して歩き始めた。
(完)
梅雨ぐもりの蒸し暑い日、翔一郎はとうとう引っ張り出される感じで、東京までテレビの番組へ出さされる羽目になったのである。
エマは心配そうな顔をしたが、
「やっつけ仕事やし、あんじょうチャッチャとやって早よ済ますわ」
そういうと、車中の人となっている。
当日。
東京のテレビ局には入館証というものが要るらしく、煩わしく思ったのか少し面倒がりな翔一郎は、
「いちいちそんなんややこしいことしやなあかんのやったら、出んかて食うのは困らんし、別に出んでもよろしがな」
といって踵を返し、京都へ帰ろうとしたので、ついてきていたプロデューサーを大慌てさせた。
こういうところが、
──京都の饗庭は、相手が誰であろうが媚びない。
と見られており、支持が高い反面ややもすると鼻持ちならないようにも見られるらしい。
が。
「昔から人間の評価は、本人が棺桶におさまらんと定まらんもんや」
いちいち生身の人間のえこひいきなんぞ聞いてられるか、ととどめを刺すこともあった。
テレビの業界の人間にすれば、歯に衣を着せぬ物言いは諸刃の剣で、
(京都からえらい面倒なの連れてきたな)
というのが本音であったらしい。
生放送が始まった。
翔一郎は連れてこられた、というのがあって、そのくせ話もろくに振られないので、不機嫌そうに雛壇に座っている。
しかも。
さすがに退屈なのか、一つ大あくびをした。
すると。
司会者に咎められた。
「饗庭さん…あくびって」
「なーに、下らんからあくびが出たまで、気に入らんなら帰るだけや」
というが早いか、さっと雛壇を立って、翔一郎は消えてしまった。
たちまちスタジオは騒然となる。
ディレクターが飛んできて、
「ちょっ…ちょっと、饗庭さん!」
取りすがった。
「なんでもかんでも東京が偉い思ったら、あんさん大間違いやで」
それだけいい残すと、その足で京都まで帰ってきてしまったのである。
当然、問題になった。
──なんと傲慢な奴だ。
という抗議ももちろん半数近くあったが、
「あれだけ自己の意見があるのだから、何があってもブレないだろう」
という賛意も寄せられ、例のガバチョの旅シリーズのヒットもあって、いつのまにやら知る人ぞ知る人物になっていたのであった。
西陣に帰ってきた。
「おかえりー」
エマはいつも通りに迎えた。
翔一郎が東京で何をしてきたかは、萌々子やあさ美からメールやら電話やらが来て、すでに知っている。
が。
「…なんかさ、翔くんって価値観がハッキリしてるよね」
そういうトコ嫌いじゃないよ、とエマはいった。
「…おぉきに」
翔一郎は初めて顔がほころんだ。
「昔さ、食べ物でも何でも好き嫌いはダメって言われたりしたけどさ、翔くんは好き嫌いってダメとか言われた?」
「なんや藪から棒に」
といいながらも、
「うちのオカンが好き嫌いやたらあったから、お前は好き嫌いは遺伝やし諦めぇっていわれた」
エマは吹き出した。
「…それじゃ、好きなものしか食べなかったってこと?」
「ま、そういうことやな…けど別に死なんかったし、大病もせなんだし、これがキャラやと思えば何の世話も苦労もあれへん」
ストレス抱えて生きる方がよっぽどアホ臭くてかなんわ、と翔一郎はとりつく島もない様子でいった。
「翔くんって子供みたい」
「しゃーないやないか、えぇモンはえぇけどアカンもんはアカン、それだけのこっちゃ」
「それはそうだけど…」
「そういうエマかて、まだ成人式やってへんやないか」
すかさずやり返した。
「…って、まるで花月の夫婦漫才やな」
オチがつくとエマは、笑うしかない。
半月ほど過ぎた。
出席の日数の関係で遅れていたエマの卒業式が無事に片付いて、エマは本格的に翔一郎の事務所で帳簿付けやら電話番やらサポートに回り始めた。
といって、作業の中身は大した変わらない。
何かしら撮影に行く翔一郎の毎日も、変わりようがないぐらい変わらない。
ところが。
翔一郎が写真の整理をしていると、キッチンから何か割れる音がした。
急いで行くと、茶碗が割れている。
「エマ、怪我せえへんかったか?」
「あたしは大丈夫」
でも翔くんの茶碗が…と、エマはひどく落ち込んでいた。
「あー…これ、おれが芸大の頃から使ってた、古道具屋で百円まで値切った安モンや」
こら寿命やな、と翔一郎はフラットにいった。
「でも…」
「んなエマが無事やったらええのや」
割れたら茶碗なんぞサラ品買うたらええがな、といいかけて、何か思いついたらしく、
「せや」
二人でなんぞお揃いのモン作らへんか、といった。
「えっ?」
「うちら一緒になってしばらく経つけど、好き連れで指輪も式もあれへんから、せめて何かしら夫婦らしいもん作らなあかんなって」
どやのん?──翔一郎はうつむいたエマの顔をのぞきこんだ。
「…夫婦茶碗とか?」
「茶碗なんぞ、また安モン探せばえぇ」
うちらだけのモン作ればええがな、と翔一郎はエマの手をとった。
エマと翔一郎が出掛けたのは、清水寺の近くの京焼の安幕部窯という窯である。
「あんまくぶ…?」
「これな、あまかべって読むのや」
芸大の頃の後輩や、というと暖簾をくぐった。
「おじゃましますで」
「あ、饗庭さんご無沙汰です」
奥から出てきたのは女将である。
「先日はお電話でわざわざご連絡までいただいて」
「いやいや。ほんで窯元いてます?」
「いますよ」
呼びに奥へ再び消えた。
しばらくすると、
「饗庭先輩、久しぶりです」
「安幕部お前、元気そうやないか」
出てくると、どうも安幕部薫です、とみずから自己紹介した。
「仲間内では安幕部薫と青島薫とでダブル薫って呼んでたんやけどな」
「まぁ立ち話もなんですし、奥にどうです?」
奥の間へ招き入れた。
茶が出てくる。
「まさか夫婦で来やはるとは」
「まあな。で、例の電話で話したアレやけど…」
「それやったら、茶碗よりこういうのがえぇかなって思いまして」
安幕部が出してきたのは、皿に文字と針がついた時計である。
「よう思いついたなあ」
「清水焼って、海外の人がよう買わはるんです」
ほんで万国共通やったら時計やろ、というので作ってみたらしい。
「でも店には並んでなかったですよ」
エマが訊いた。
「まだ実用ではあれへんのですけど、先輩やったら何かアドバイスもらえるかなと」
「うちはモルモットか」
抜け目ないなぁ、と翔一郎は笑った。
「まぁえぇ、今回は実験に協力したるわ」
「ほんまおぉきに」
安幕部は深々頭を下げた。
例の作品が出来た、というのでエマと翔一郎は安幕部窯まで再び出かけた。
「無事に窯出しが済みまして、出来栄えだけ見てもらおうかと思いまして」
奥から桐箱に入って出てきた。
「字が下手やから箱書きに手間かかりましたがな」
そういいながら、落款まで丁寧に捺されてある。
箱を開けた。
「お二人に書いてもらった絵付けは、えぇ色が出ました」
いわゆるペルシャブルーの地に、紫の数字と銀色の針がよく映える正方形の時計皿である。
そこには二人で安幕部薫の指導を受けながら描いた蝶の絵があった。
よく見るとうっすら竹の図柄が彫られてあり、裏側は安幕部窯の朱印もある。
「これ…うちらの頭文字じゃない?」
よく見ると文字盤に、
「S&E」
というロゴがある。
「こんな綺麗に字が出るとは思わんかったで」
「こういうのもよろしですな」
「で、代金の件やけど」
代わりに写真が欲しいいうてたからこれ持ってきたで──そういうと、風呂敷にくるまれた、大きな現物を拡げた。
「こら見事や…」
霧の北山の杉林が撮された枕屏風である。
「これやったら作品飾るのにも使えるやろと思って、写真を引き延ばして屏風に表装してもろた」
確かにモノトーン調なら、釉薬や絵付の華やかな清水焼の邪魔にはならない。
京焼を知らなければ選べないチョイスであろう。
「これはえらいモンもろたなあ」
「気にせぇでえぇがな」
時計をしまうと、翔一郎とエマは安幕部窯を辞去した。
雨は上がっていた。
「ね、鴨川の河原にでも行こうよ」
「何やいきなり」
「たまにはのんびりデート気分で、観光もいいかなって」
「…せやな」
茶碗坂を下り切った先に五条坂が見えてくる。
結びつけられた風鈴の短冊には「絆」という字が、ちらほら書かれてあった。
「…絆、かぁ」
「?」
「ほんまは絆って馬の脚を繋ぐ紐って意味なんやけどな」
「そうなの?」
エマは目を丸くした。
「馬の脚を繋ぐ紐はすぐ切れよる、せやからすぐまた新しい紐で繋ぐらしいのやけどな」
「ふーん」
翔くん変なこと知ってるね、とエマは呟いた。
「じゃあ、人間の絆も古いのが切れたら、新しい絆を作ればいいのかも知れないね」
「…そこは、考えつかなんだな」
いったいおもろいこというやっちゃで、と翔一郎は笑った。
五条の大通の少し先には、鴨川がある。
大和大路の赤信号が変わった。
エマと翔一郎は、青信号に変わった交差点を、川端通を目指して歩き始めた。
(完)