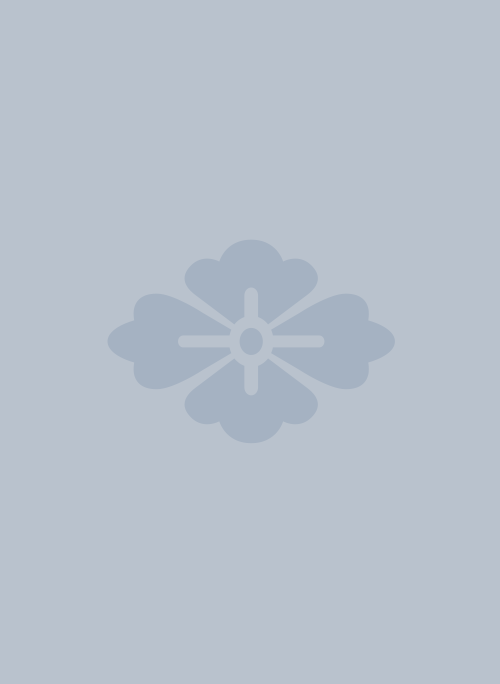翌日。
東京へ薫は帰ることになった。
「一応ミュージシャンやし、スケジュールあるしで、しゃーない」
苦笑を浮かべる薫に愛は、
「あたしはいいよ。卒業したら東京に行く」
どうやら遠距離でも、よりを戻すことになったようであったらしい。
「饗庭、愛を頼むで」
「まあカメラのことだけは任しとけ」
せやけど恋愛はあずかり知らんからな──と翔一郎は切り返し、笑わせてみせた。
「じゃあな」
薫は京都駅の改札をくぐって、人波の中へ消えていった。
「…愛、東京に行かなくていいの?」
エマが訊いた。
「あたしには京都で、やらなきゃならないことがあるから」
そういうと、首から提げたライカのカメラを手に、新たな決意をしたかのような様子で強い目線で前を見据えた。
月が改まった。
南座の顔見世が始まると、京都もちらほらクリスマスのツリーが飾られるようになる。
「クリスマスだけは、何か違和感ぬぐえんよなあ」
翔一郎には、そう映るらしい。
が。
意外に煉瓦や石積みの教会が建っている京都の町は、エマから見る限り違和感はなかった。
ところで。
いわゆる「祇園をどり」が始まった頃、西陣に滅多に来ない陣内一誠がフラッと現れたので、エマも翔一郎も大いに慌てたことがある。
「ちょっと話があって」
とはいうものの、ほとんど予約なしのような状態で来るのは、京都では非常識とされている。
またきちんと約束をした来訪も、
──髪の毛一本遅れて行く。
というのがマナーというか、京都ならではのエチケットである。
(こういうあたりが)
やっぱり異骨相(いごっそう)──一誠は高知生まれである──なのかも知れないな…と翔一郎は思ったことがあった。
さて。
そういう風にやって来た一誠が持ってきた話というのが、
「実は…年甲斐もなくちょっと気になる女がいて」
というので、エマも翔一郎もますます驚き、エマなど危うく運んできた茶菓子を落としそうになるぐらいであった。
「で、相手は…?」
「こないだグラビアの撮影に来ていた、實平あさ美という子なんやが…」
そういうと一誠は、図出しで撮り下ろした實平あさ美のポラロイドを取り出した。
驚いたどころではない。
この頃の東京で話題になっているアイドルのユニットで、メインのボーカルをつとめる美少女ではないか。
世情に疎い翔一郎も、そのぐらいは知っている。
(何を血迷うたんや)
翔一郎が呆気にとられていると、
「いい歳して、まさかこうなるとは思わんかったのやが、何か上手く話せんしやなぁ…」
そうであろう。
どちらかというと真面目な翔一郎とは違っている。
撮影からしてチャラい。
(そういや)
初めて翔一郎に出逢った日も、撮影中の一誠はえらく高いテンションで、エマが軽く引いたぐらいである。
おまけに。
「まったく覚えてへんのやが、どうも酔った勢いで彼女と寝たらしくてやな…」
朝起きると隣に全裸の彼女がいて、さすがにまずいと思ったのか、着替えもそこそこに別れて、それっきりだというのである。
「それ…ただのヤリ逃げですやろ」
翔一郎は呆れた。
しかし。
「何度か会うんやけど、挨拶ぐらいでも、まともに言葉が出てこんくて」
どうも夢にまで出てくるらしい。
「陣内さん、それ…間違いなく恋ですって」
翔一郎の隣で聞いていたエマが珍しく、キッパリと答えた。
「で、彼女は…?」
「特に何も」
「でも、彼女に悪いことをしたって思うなら、謝ってから気持ちを伝えた方が、あたしは正しいと思いますよ」
エマは柔らかく、しかし厳しいところを衝いた。
「…せやな」
でもまぁこのままで終わりやろな、と一誠は番茶を飲み、茶菓子をポケットにしまうと、
「突然悪かったから、今度穴埋めする」
と、足早に帰った。
数日、経った。
かきいれ時となるクリスマス前に年末年始の休暇を取った慶が、関西に戻ってきた。
久々の再会である。
「えらいひさしぶりやなー」
エマと翔一郎が京都駅まで迎えに出ると、紺野萌々子も一緒に来ていた。
「萌々子ちゃん相変わらずフリフリのヒラヒラやな」
フリフリヒラヒラ、とかに道楽の宣伝の節回しで慶が歌うと、
「誰が道頓堀の看板や」
かぶせ気味に素早く翔一郎の突っ込みが返ってくる。
一同、ドッと笑った。
「お前相変わらず突っ込み早いなー」
「まぁまぁやな」
そういえば翔一郎は突っ込みが高速だというのを、東京へ出た折に聞いたことがあったのを、エマは思い出した。
が。
慶の後に、地味なジーンズ姿の眼鏡をかけた女の子がいる。
「…?」
翔一郎が指で示すと、
「あ、こいつ? いとこのあさ美や」
翔一郎は絶句した。
眼鏡で一瞬分からなかったが、間違いなく實平あさ美である。
(…せや!)
芸能人のオーラを、見事なまでに消している。
しかも。
すっかり忘れていたが、前に広島にいた慶のいとこが芸能界に入った話を、翔一郎は思い出した。
「こいつはカメラマンの饗庭翔一郎。なかなか東京に出てこんけど、写真の腕は京都で指折りやで」
翔一郎は黙ってお辞儀をし、
「よろしゅう」
とフランクな感じに挨拶をした。
實平あさ美は挨拶してペコッと頭を下げると、
「饗庭さんはグラビア撮らないんですか?」
いきなり際どいコーナーにボールを投げられたバッターのように、翔一郎は内心仰け反った。
「得意なのは人間より風景とかかな」
エマが代返した。
「まぁ立ち話も何やから」
どっか食いにでも行こか──と翔一郎は地下鉄に向かって歩き始めた。
慶が實平あさ美を連れてきた理由は意外にもあっけないもので、
「流行りに疎いお前は知っとるかどうか知らんが、一応こいつ東京でアイドルやっとるやろ?」
修学旅行行ってないから、連れてったってほしいねん──と慶はいうのである。
「いきなりいわれたかてやな…そんなん困るがな」
「お前の行き付けでえぇねん、頼むわ」
慶は拝んだ。
「…しゃーないなぁ」
翔一郎は渋い顔を作った。
「うーん…女の子が好きそうな雰囲気の場所かぁ」
そういった成り行きで翔一郎が選んだのは、嵐山である。
夏と違って人は少ない。
人力車を停めると、大覚寺のほうへ行くように指し示した。
清涼寺を森嘉の角で郵便局の方へ折れ、覚勝院へ抜ける道を入って、大沢池とは反対側の北ノ段と呼ばれる田んぼのある界隈を、岡幸の角から道なりに竹林の道へ進んで行く。
見えたのは直指庵である。
さわさわ、と葉擦れの音だけが鳴っており、関西生まれの慶ですら知らなかった静かな庵でもある。
「ようこんなん知っとったな」
慶が驚いた。
「ここにな、ノートがあんねん」
本堂に行くと「思い出草」と書かれたノートがあった。
「みんなここにいろいろ書いて、気持ちを整えてまた都会に戻んのや」
「要はおのれを見つめ直せっちゅうことか」
「ま、そういうこっちゃな」
翔一郎はにべもなく言った。
「おれへの面当てか」
「癲狂(てんごう)言いィなや」
翔一郎は切り返した。
が。
「あくまで個人的な意見なんだけどさ」
と口を開いたのは、エマである。
「人間って、立ち位置が分からなくなったら路頭に迷うと思う」
だからポジションをハッキリささせるために、見つめ直すんじゃないかなぁ──まるでエマは、自分に言い聞かすような言い方をして見せた。
「そういうのって、大事だよね…」
呟いたのは、實平あさ美である。
そうして實平あさ美は何やらノートに書いていたようであったが、
──そんなものには関心がない。
と言わんばかりの顔をして、翔一郎は興味なさ気に散った竹の葉で笹舟を作っていた。
夜。
帰宅してしばらくすると、雷を伴った激しい時雨が降り始めた。
「昼間でなくてよかったなあ」
こんなん嵐山で降られたらかなんで──翔一郎はぼやいた。
エマは窓の外の、雨の様子を眺めている。
その頃。
七条の正面橋の東詰から少し入った一誠の自宅の前には、傘も差さずにぐしょ濡れになってたたずんでいる實平あさ美がいた。
「…どないしたんや、あさ美ちゃん」
一誠の驚きは自然であろう。
「あのね、陣内さん」
「なんやのん?」
「…アイドルやってる子なんか、趣味じゃないよね?」
「…どういうこと?」
「今日はね、お別れを伝えに来たの」
一誠は訳が分からない。
「あたしね、…陣内さんのこと、…ずっと好きだったんだけど、アイドルだから誰かのことを好きになっちゃいけないんだって」
だからお別れを言いに来たんだ──必死に笑いながら、しかし目には涙を浮かべていた。
「東京に戻ったら、あたし芸能界から引退しようかなって」
だからお別れを言いに来た、といい終わる頃には、實平あさ美の顔が泣き崩れてみるみる歪んでいた。
一誠は黙っていた。
が、急に抱き寄せてから、
「おれな、あさ美ちゃんのこと…、前から好いちゅうきに」
ずっとおってくれんろうか──出たのは、骨肉に染み込んだ土佐弁であった。
あさ美は少しびっくりした様子であったが、
「…」
黙ってコクン、と頷いた。
東京へ薫は帰ることになった。
「一応ミュージシャンやし、スケジュールあるしで、しゃーない」
苦笑を浮かべる薫に愛は、
「あたしはいいよ。卒業したら東京に行く」
どうやら遠距離でも、よりを戻すことになったようであったらしい。
「饗庭、愛を頼むで」
「まあカメラのことだけは任しとけ」
せやけど恋愛はあずかり知らんからな──と翔一郎は切り返し、笑わせてみせた。
「じゃあな」
薫は京都駅の改札をくぐって、人波の中へ消えていった。
「…愛、東京に行かなくていいの?」
エマが訊いた。
「あたしには京都で、やらなきゃならないことがあるから」
そういうと、首から提げたライカのカメラを手に、新たな決意をしたかのような様子で強い目線で前を見据えた。
月が改まった。
南座の顔見世が始まると、京都もちらほらクリスマスのツリーが飾られるようになる。
「クリスマスだけは、何か違和感ぬぐえんよなあ」
翔一郎には、そう映るらしい。
が。
意外に煉瓦や石積みの教会が建っている京都の町は、エマから見る限り違和感はなかった。
ところで。
いわゆる「祇園をどり」が始まった頃、西陣に滅多に来ない陣内一誠がフラッと現れたので、エマも翔一郎も大いに慌てたことがある。
「ちょっと話があって」
とはいうものの、ほとんど予約なしのような状態で来るのは、京都では非常識とされている。
またきちんと約束をした来訪も、
──髪の毛一本遅れて行く。
というのがマナーというか、京都ならではのエチケットである。
(こういうあたりが)
やっぱり異骨相(いごっそう)──一誠は高知生まれである──なのかも知れないな…と翔一郎は思ったことがあった。
さて。
そういう風にやって来た一誠が持ってきた話というのが、
「実は…年甲斐もなくちょっと気になる女がいて」
というので、エマも翔一郎もますます驚き、エマなど危うく運んできた茶菓子を落としそうになるぐらいであった。
「で、相手は…?」
「こないだグラビアの撮影に来ていた、實平あさ美という子なんやが…」
そういうと一誠は、図出しで撮り下ろした實平あさ美のポラロイドを取り出した。
驚いたどころではない。
この頃の東京で話題になっているアイドルのユニットで、メインのボーカルをつとめる美少女ではないか。
世情に疎い翔一郎も、そのぐらいは知っている。
(何を血迷うたんや)
翔一郎が呆気にとられていると、
「いい歳して、まさかこうなるとは思わんかったのやが、何か上手く話せんしやなぁ…」
そうであろう。
どちらかというと真面目な翔一郎とは違っている。
撮影からしてチャラい。
(そういや)
初めて翔一郎に出逢った日も、撮影中の一誠はえらく高いテンションで、エマが軽く引いたぐらいである。
おまけに。
「まったく覚えてへんのやが、どうも酔った勢いで彼女と寝たらしくてやな…」
朝起きると隣に全裸の彼女がいて、さすがにまずいと思ったのか、着替えもそこそこに別れて、それっきりだというのである。
「それ…ただのヤリ逃げですやろ」
翔一郎は呆れた。
しかし。
「何度か会うんやけど、挨拶ぐらいでも、まともに言葉が出てこんくて」
どうも夢にまで出てくるらしい。
「陣内さん、それ…間違いなく恋ですって」
翔一郎の隣で聞いていたエマが珍しく、キッパリと答えた。
「で、彼女は…?」
「特に何も」
「でも、彼女に悪いことをしたって思うなら、謝ってから気持ちを伝えた方が、あたしは正しいと思いますよ」
エマは柔らかく、しかし厳しいところを衝いた。
「…せやな」
でもまぁこのままで終わりやろな、と一誠は番茶を飲み、茶菓子をポケットにしまうと、
「突然悪かったから、今度穴埋めする」
と、足早に帰った。
数日、経った。
かきいれ時となるクリスマス前に年末年始の休暇を取った慶が、関西に戻ってきた。
久々の再会である。
「えらいひさしぶりやなー」
エマと翔一郎が京都駅まで迎えに出ると、紺野萌々子も一緒に来ていた。
「萌々子ちゃん相変わらずフリフリのヒラヒラやな」
フリフリヒラヒラ、とかに道楽の宣伝の節回しで慶が歌うと、
「誰が道頓堀の看板や」
かぶせ気味に素早く翔一郎の突っ込みが返ってくる。
一同、ドッと笑った。
「お前相変わらず突っ込み早いなー」
「まぁまぁやな」
そういえば翔一郎は突っ込みが高速だというのを、東京へ出た折に聞いたことがあったのを、エマは思い出した。
が。
慶の後に、地味なジーンズ姿の眼鏡をかけた女の子がいる。
「…?」
翔一郎が指で示すと、
「あ、こいつ? いとこのあさ美や」
翔一郎は絶句した。
眼鏡で一瞬分からなかったが、間違いなく實平あさ美である。
(…せや!)
芸能人のオーラを、見事なまでに消している。
しかも。
すっかり忘れていたが、前に広島にいた慶のいとこが芸能界に入った話を、翔一郎は思い出した。
「こいつはカメラマンの饗庭翔一郎。なかなか東京に出てこんけど、写真の腕は京都で指折りやで」
翔一郎は黙ってお辞儀をし、
「よろしゅう」
とフランクな感じに挨拶をした。
實平あさ美は挨拶してペコッと頭を下げると、
「饗庭さんはグラビア撮らないんですか?」
いきなり際どいコーナーにボールを投げられたバッターのように、翔一郎は内心仰け反った。
「得意なのは人間より風景とかかな」
エマが代返した。
「まぁ立ち話も何やから」
どっか食いにでも行こか──と翔一郎は地下鉄に向かって歩き始めた。
慶が實平あさ美を連れてきた理由は意外にもあっけないもので、
「流行りに疎いお前は知っとるかどうか知らんが、一応こいつ東京でアイドルやっとるやろ?」
修学旅行行ってないから、連れてったってほしいねん──と慶はいうのである。
「いきなりいわれたかてやな…そんなん困るがな」
「お前の行き付けでえぇねん、頼むわ」
慶は拝んだ。
「…しゃーないなぁ」
翔一郎は渋い顔を作った。
「うーん…女の子が好きそうな雰囲気の場所かぁ」
そういった成り行きで翔一郎が選んだのは、嵐山である。
夏と違って人は少ない。
人力車を停めると、大覚寺のほうへ行くように指し示した。
清涼寺を森嘉の角で郵便局の方へ折れ、覚勝院へ抜ける道を入って、大沢池とは反対側の北ノ段と呼ばれる田んぼのある界隈を、岡幸の角から道なりに竹林の道へ進んで行く。
見えたのは直指庵である。
さわさわ、と葉擦れの音だけが鳴っており、関西生まれの慶ですら知らなかった静かな庵でもある。
「ようこんなん知っとったな」
慶が驚いた。
「ここにな、ノートがあんねん」
本堂に行くと「思い出草」と書かれたノートがあった。
「みんなここにいろいろ書いて、気持ちを整えてまた都会に戻んのや」
「要はおのれを見つめ直せっちゅうことか」
「ま、そういうこっちゃな」
翔一郎はにべもなく言った。
「おれへの面当てか」
「癲狂(てんごう)言いィなや」
翔一郎は切り返した。
が。
「あくまで個人的な意見なんだけどさ」
と口を開いたのは、エマである。
「人間って、立ち位置が分からなくなったら路頭に迷うと思う」
だからポジションをハッキリささせるために、見つめ直すんじゃないかなぁ──まるでエマは、自分に言い聞かすような言い方をして見せた。
「そういうのって、大事だよね…」
呟いたのは、實平あさ美である。
そうして實平あさ美は何やらノートに書いていたようであったが、
──そんなものには関心がない。
と言わんばかりの顔をして、翔一郎は興味なさ気に散った竹の葉で笹舟を作っていた。
夜。
帰宅してしばらくすると、雷を伴った激しい時雨が降り始めた。
「昼間でなくてよかったなあ」
こんなん嵐山で降られたらかなんで──翔一郎はぼやいた。
エマは窓の外の、雨の様子を眺めている。
その頃。
七条の正面橋の東詰から少し入った一誠の自宅の前には、傘も差さずにぐしょ濡れになってたたずんでいる實平あさ美がいた。
「…どないしたんや、あさ美ちゃん」
一誠の驚きは自然であろう。
「あのね、陣内さん」
「なんやのん?」
「…アイドルやってる子なんか、趣味じゃないよね?」
「…どういうこと?」
「今日はね、お別れを伝えに来たの」
一誠は訳が分からない。
「あたしね、…陣内さんのこと、…ずっと好きだったんだけど、アイドルだから誰かのことを好きになっちゃいけないんだって」
だからお別れを言いに来たんだ──必死に笑いながら、しかし目には涙を浮かべていた。
「東京に戻ったら、あたし芸能界から引退しようかなって」
だからお別れを言いに来た、といい終わる頃には、實平あさ美の顔が泣き崩れてみるみる歪んでいた。
一誠は黙っていた。
が、急に抱き寄せてから、
「おれな、あさ美ちゃんのこと…、前から好いちゅうきに」
ずっとおってくれんろうか──出たのは、骨肉に染み込んだ土佐弁であった。
あさ美は少しびっくりした様子であったが、
「…」
黙ってコクン、と頷いた。