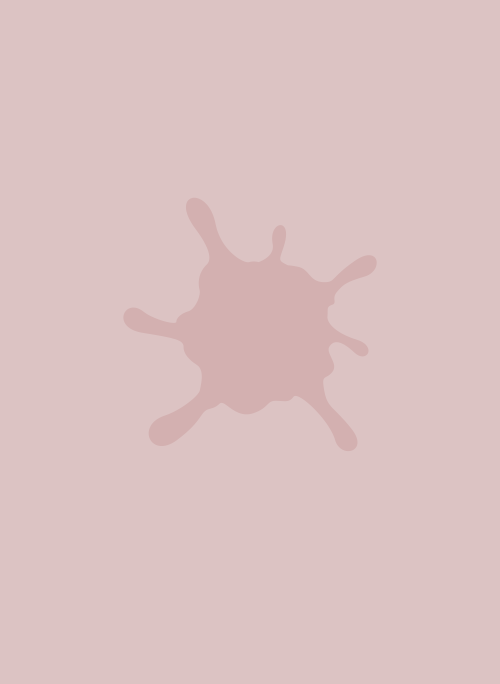「それ、ちゃんと説得したの?」
桂子が不審に聞くと、坂井はにこりと笑い答えた。
「一応注意したんですけどぉ、なんか休み時間になるとマー君ごっこっていうのをやりだすんですよ。
あのこっくりさんと同じですよ。
携帯電話を机において、それを囲むようにしてマー君、マー君おいでくださいなんてやってるんですよ、マジうけますよねぇ」
それを聞いて桂子は呆れた。全くこの学校はどうなってしまったのだろうか。不安が募る中、追い討ちをかけるように困り果てた顔をした教頭が現れた。
剥げたかの頭に地味なスーツ、一般的な教頭先生だろう。彼は頭を撫でながら、ぶつぶつ何かを言っている。
この教頭も少し変わっている。不機嫌になるとこうしてずっと独り言を言っている。
桂子は横を通った教頭を呼び止め、話を聞いてみることにした。
「どうしたんですか? 教頭先生」
おそらく何度も口にしている言葉だろう。そう思いつつも、桂子は教頭の辛そうな顔に同情した。教頭が大半剥げているのは、きっとストレスからだろう。
今の彼の顔には苦渋という言葉が似合いそうだった。
「あ、ああ、三原先生……。大変ですよ。朝から電話が鳴りっぱなしで。昨日の事件のことを知りたがる報道陣がもうっ……」
怒鳴り散らしたいのか声に力が入る。が、立場上あと一歩の所で踏み留まる。
桂子が不審に聞くと、坂井はにこりと笑い答えた。
「一応注意したんですけどぉ、なんか休み時間になるとマー君ごっこっていうのをやりだすんですよ。
あのこっくりさんと同じですよ。
携帯電話を机において、それを囲むようにしてマー君、マー君おいでくださいなんてやってるんですよ、マジうけますよねぇ」
それを聞いて桂子は呆れた。全くこの学校はどうなってしまったのだろうか。不安が募る中、追い討ちをかけるように困り果てた顔をした教頭が現れた。
剥げたかの頭に地味なスーツ、一般的な教頭先生だろう。彼は頭を撫でながら、ぶつぶつ何かを言っている。
この教頭も少し変わっている。不機嫌になるとこうしてずっと独り言を言っている。
桂子は横を通った教頭を呼び止め、話を聞いてみることにした。
「どうしたんですか? 教頭先生」
おそらく何度も口にしている言葉だろう。そう思いつつも、桂子は教頭の辛そうな顔に同情した。教頭が大半剥げているのは、きっとストレスからだろう。
今の彼の顔には苦渋という言葉が似合いそうだった。
「あ、ああ、三原先生……。大変ですよ。朝から電話が鳴りっぱなしで。昨日の事件のことを知りたがる報道陣がもうっ……」
怒鳴り散らしたいのか声に力が入る。が、立場上あと一歩の所で踏み留まる。