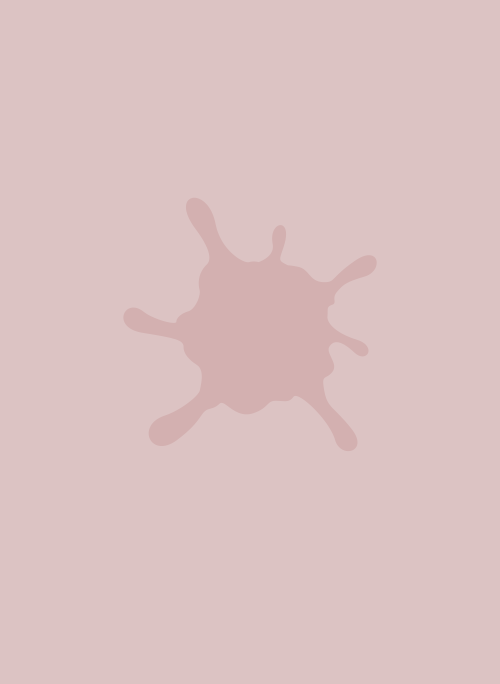勝田はこの家に一人で暮らしている。家族を作ろうとは考えていない。一人身を愛しているからだ。
そのため、当然家には誰もいない。勝田は痛む体をゆっくりと玄関からすぐ左手に見えるリビングに運ぶ。
まるで自分が誰かに運ばれているような感覚だった。
薄暗い家には勝田の足音しか聞こえない。床に敷かれたカーペットがみしみしと音を立てる。
この家は死んだ両親から受け継いだ物で、もうかなり古くガタがきている。
「いっつ」
リビングに入るドアを開ける際、ドアが殴られた肩に接触した。鈍い痛みが肩を覆い尽くしが、歯を食いしばって堪えた。
中に入ると、薄暗いリビングがぼんやりと見えた。誰もいないそこは、まるで刑務所の懲罰部屋のような閉鎖感と、孤独を満面に漂わせていた。
暗闇に目が慣れていた勝田には更に、その空間に置かれているソファやテレビが見えたが、どれも寂れていた。
そんな空間に明かりもつけず入り、テレビの前に陣取る黒いソファに重い体を預けた。まるで倒れ込むように座ったため、ソファからギシギシと音が鳴る。
そのため、当然家には誰もいない。勝田は痛む体をゆっくりと玄関からすぐ左手に見えるリビングに運ぶ。
まるで自分が誰かに運ばれているような感覚だった。
薄暗い家には勝田の足音しか聞こえない。床に敷かれたカーペットがみしみしと音を立てる。
この家は死んだ両親から受け継いだ物で、もうかなり古くガタがきている。
「いっつ」
リビングに入るドアを開ける際、ドアが殴られた肩に接触した。鈍い痛みが肩を覆い尽くしが、歯を食いしばって堪えた。
中に入ると、薄暗いリビングがぼんやりと見えた。誰もいないそこは、まるで刑務所の懲罰部屋のような閉鎖感と、孤独を満面に漂わせていた。
暗闇に目が慣れていた勝田には更に、その空間に置かれているソファやテレビが見えたが、どれも寂れていた。
そんな空間に明かりもつけず入り、テレビの前に陣取る黒いソファに重い体を預けた。まるで倒れ込むように座ったため、ソファからギシギシと音が鳴る。