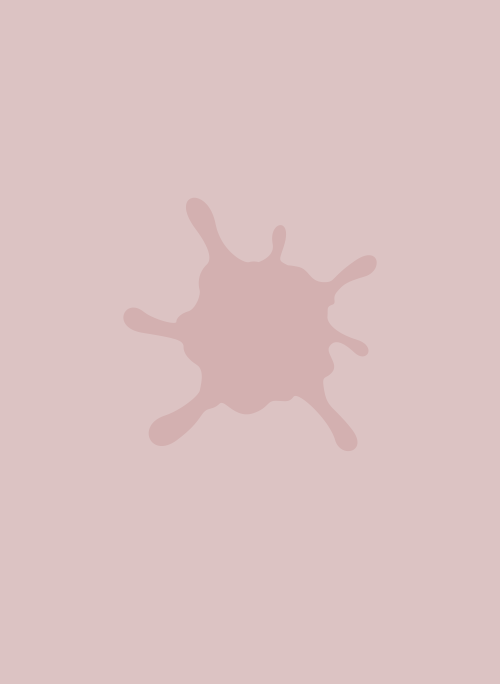「先生、俺、女いるよ? 気付いてんでしょ?」
唐突に彼がそんなことを言うもんだから、心臓が跳ねた。
わかってるよ、そんなことぐらい。
嘘だとすぐわかるような陳腐な理由をつけてここへ来ない時は、誰か他の女の子を抱いているんでしょ。
わかってるってば。
わかっているのに、彼にそう言われて切なくなるのは何故だろう。
「知ってる。でも……それが何?」
平静を装って返せば、途端、彼は傷付いた顔をする。
何故?
ああ――
そろそろこれ、終わりにしないと、か。
「先生、別れよう」
ベッド端に腰掛けている彼は、目の前の座卓の上の灰皿に、タバコを捻じ込んだ。
私が彼のために買った、アクアマリンのガラス製灰皿。
もう、いらなくなるな。
唐突に彼がそんなことを言うもんだから、心臓が跳ねた。
わかってるよ、そんなことぐらい。
嘘だとすぐわかるような陳腐な理由をつけてここへ来ない時は、誰か他の女の子を抱いているんでしょ。
わかってるってば。
わかっているのに、彼にそう言われて切なくなるのは何故だろう。
「知ってる。でも……それが何?」
平静を装って返せば、途端、彼は傷付いた顔をする。
何故?
ああ――
そろそろこれ、終わりにしないと、か。
「先生、別れよう」
ベッド端に腰掛けている彼は、目の前の座卓の上の灰皿に、タバコを捻じ込んだ。
私が彼のために買った、アクアマリンのガラス製灰皿。
もう、いらなくなるな。