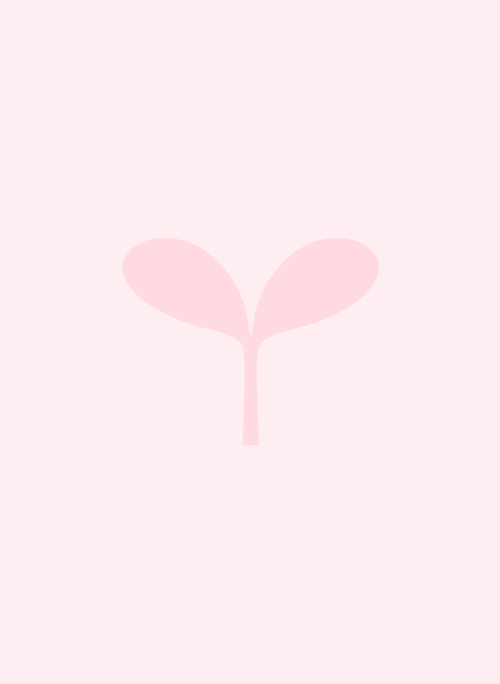キラキラと赤や緑のネオンが輝く街を、俺は細く柔らかい手を握りしめながら歩く。
首から方にかけてのしなやかな筋は、ネオンの光りによって色っぽい艶を出す。
「寛久、待って!待ってよ!そんなに急がなくても、私は逃げないわよ!?」
突然、雨でもないのに寂しくなった。
親父の声を聞いて、一気に俺の中の何かが溢れ出した。
やっぱり・・・ダメだ。
集まり合い輝く光り達を、綺麗だなんて思えない。
安っぽくて。
花がない。
その光りに集まる俺達は、それだけの価値しかないのだろう。
「寛久!・・・もう、聞いてよ!」
呼び出した女は、電話をかけると直ぐに出た。
会いたい・・・。
だなんて、思ってもいない言葉を投げかけてやったら、喜んで奴はやって来た・・・。
最低でも、俺にはこれしか残っていない。
首から方にかけてのしなやかな筋は、ネオンの光りによって色っぽい艶を出す。
「寛久、待って!待ってよ!そんなに急がなくても、私は逃げないわよ!?」
突然、雨でもないのに寂しくなった。
親父の声を聞いて、一気に俺の中の何かが溢れ出した。
やっぱり・・・ダメだ。
集まり合い輝く光り達を、綺麗だなんて思えない。
安っぽくて。
花がない。
その光りに集まる俺達は、それだけの価値しかないのだろう。
「寛久!・・・もう、聞いてよ!」
呼び出した女は、電話をかけると直ぐに出た。
会いたい・・・。
だなんて、思ってもいない言葉を投げかけてやったら、喜んで奴はやって来た・・・。
最低でも、俺にはこれしか残っていない。