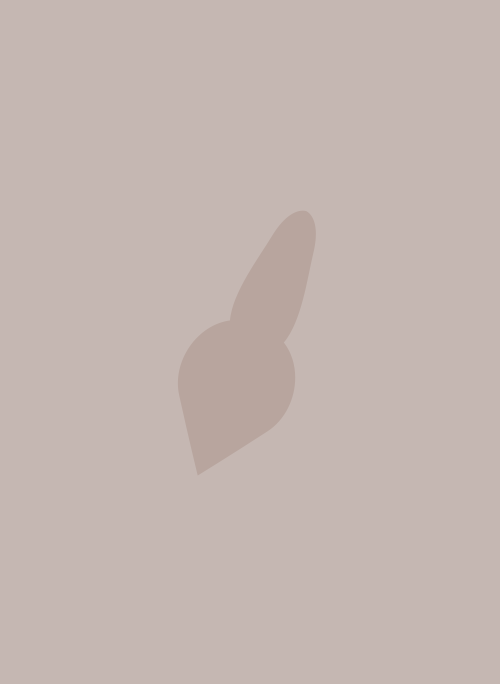「ちょっと、仁さん」
藤沢が唇をとがらせる。それを無視して、仁さんはミツキに聞いた。
「川本、もしおまえが台詞を思い出せんかったら、あのときどうなっとったと思う?」
「え?」
「想像して、言うてみ」
「あ、はい」少し考えてから、答える。「まず、芝居の展開が止まります」
「それで?」
「たぶん、誰かが小声で台詞を教えてくれただろうと思います。そして、一応芝居は続けられます」
「それで?」
「園児達は、さっきまで芝居にひきこまれていたのに、わたしの失敗のせいで、しらけてしまうでしょう」
「それで?」
「幼稚園の先生方も、うちの部への期待を裏切られて、いやな気分になるでしょう」
「それがわかってるんなら、ええわ」仁さんは藤沢を向いた。「説教はもう終わり。ええな?」
「でも」
「なあ、藤沢。部員を叱るんはええんやけどな、タイミングをわきまえてくれや。いまはみんなで打ち上げに行こうってときなんやで」
そこで藤沢は、部員達の不安気な視線に気付いたようだ。顔を赤くして、わかったとつぶやき、ミツキからはなれた。
仁さんはため息をついて列の先頭にもどった。その背中を見つめながら、洋平は、藤沢を止められなかった自分を恥じて歯をくいしばった。