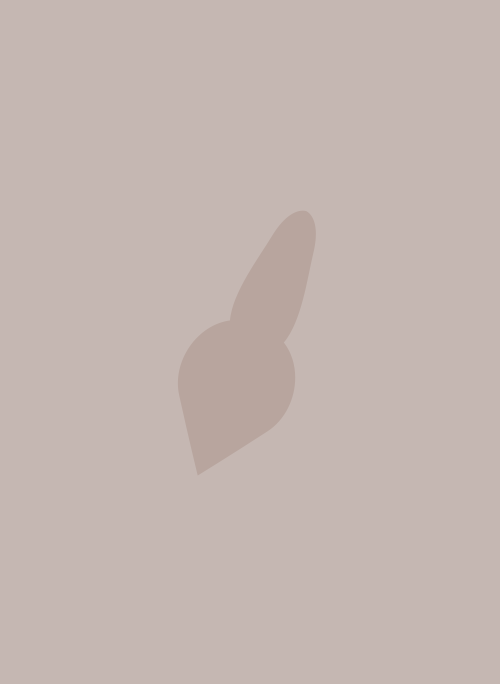練習が終わり、洋平が帰ろうとすると、校門の前で藤沢に呼び止められた。
「話したいことがあるんやけど、途中まで、いっしょに帰らん?」
「はあ、いいですけど」
ふたりはならんで歩きだした。
「部活にはもう慣れた?」
「ええ、まあそれなりに。でも役者のひと達とちがって、練習しとらんから、部活やってるっていう実感はあんまりないっすね」
「それはわたしも同じ。でもこれからはちがうよ。クリスマスの芝居のために、裏方も忙しくなるんやから、覚悟しといてな」
「はい」
「ところで」藤沢な真剣な表情になった。「麻見君、今回の芝居の舞台設計をやってみる気ない?」
「え?」目を丸くした。「そんな大切な役目をおれが?」
「大丈夫よ。間違いはわたしが直したげるけん」
「いや、ちょっと、自信ないです」
「大丈夫やって。それに、演劇部を三年間やっていくつもりなら、こういうことは早めに経験しといたほうがええと思うで」
藤沢は、何度も大丈夫とくりかえしながら説得をつづけた。それを聞くうちに、洋平の心はゆれてきた。
自信はないが、もしうまくできたら、自分が想像した光景が舞台の上で実体化されることになる。そして、役者達がその中を動きまわり、物語をつむぎだしてゆくのだ。
それはとても魅力的だった。
意を決して、洋平は言った。
「じゃあ、やってみます」