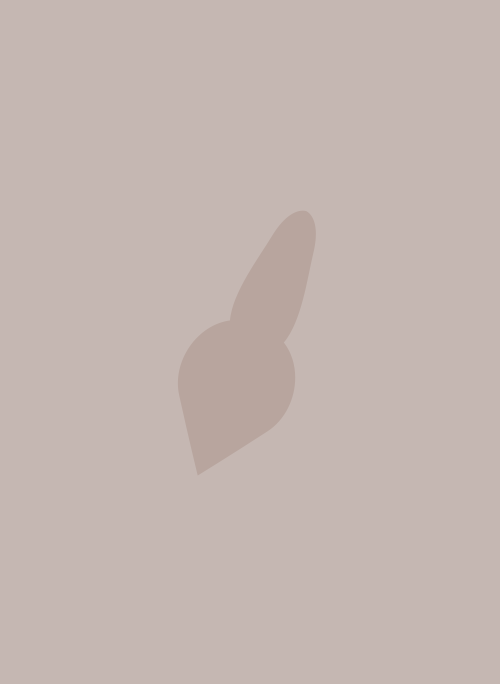日がだいぶ沈み、あたりが薄暗くなってきた。
いくつかの店が、シャッターを閉めはじめている。
見物人の数がだんだんと少なくなってきた。
部員達のほとんどは、まわりのひと達をなんとか楽しませることができたので、すでに帰宅していた。
残りの部員達はあせりながらいろんな芸をくりかえしたが、どれもあまりおもしろくなく、まわりのおばさん達はしらけはじめていた。
藤沢があくびをもらしながら言った。
「麻見君は役者じゃないんやけん、もう帰ってもええんよ」
「はい、でも、もう少しだけ見ときます。藤沢先輩こそ、帰らんのですか?」
「わたしは副部長やけん、最後まで見届けとかんとね」
そのとき仁さんの気合いの入った声が聞こえてきた。
「よっしゃ、そろそろおれも何かやろか」
部員達がどよめいた。藤沢が、待ってましたと言わんばかりに目を輝かせる。
仁さんは前に出ると、アスファルト道路の上に正座をした。
そして、周囲にむかって、ゆっくりと一礼すると、いきなり笑顔で叫んだ。
「どうもこんばんわっす。わたくし、高橋仁と申します」
その声は、商店街の端から端までひびきわたった。
そんなとんでもない声量で、仁さんは古典落語をやりはじめた。
仁さんの落語はすごくおもしろかった。
さっきまでのしらけた空気がすぐに吹っ飛んで、まわりのおばさん達、部員達の笑い声が何度もはじけた。洋平も、座りこみ腹をおさえながら涙が出るくらいに笑った。
華というのだろうか。どうしても目が行ってしまうような魅力が、仁さんには備わっていた。
落語が終わると、割れんばかりの拍手が鳴りひびいた。いつのまにか、まわりの人垣が大きくなっていた。近くの住人が、外に出て集まっていたのだ。
仁さんは人垣にむかって、ていねいにおじぎをしてから、部員達に言った。
「これくらいひとが集まれば、まだ続けられるやろ。おまえら、がんばれよ」
部員達はそろって嫌そうな声をあげたが、その表情は少しも嫌そうではなかった。
「やっぱすごいわ、あのひとは」
藤沢がそうつぶやくのを聞いた途端、洋平の胸中にまた例の不安がよみがえってきた。
ミツキは、こんな仁さんに惚れているのではないか。
もしそうだとしたら、自分なんかではとてもかないそうにない。
そう考えると、さっき仁さんの落語に大笑いしてしまったことが、急にくやしくなってきた。あの落語を楽しんだことで、なんだか仁さんに負けてしまったような気がしてきた。
「藤沢先輩、おれ、そろそろ帰ります」
「あら、そう?」藤沢は、ふりむいて微笑んだ。「じゃあ、お疲れ様。また明日ね」
「はい、お疲れ様でした」
洋平は、商店街の出口へ向かって、乱暴な足取りで歩きだした。仁さんへの拍手は、まだやんでいなかった。いまの洋平にとって、それはひどく耳触りな騒音だった。