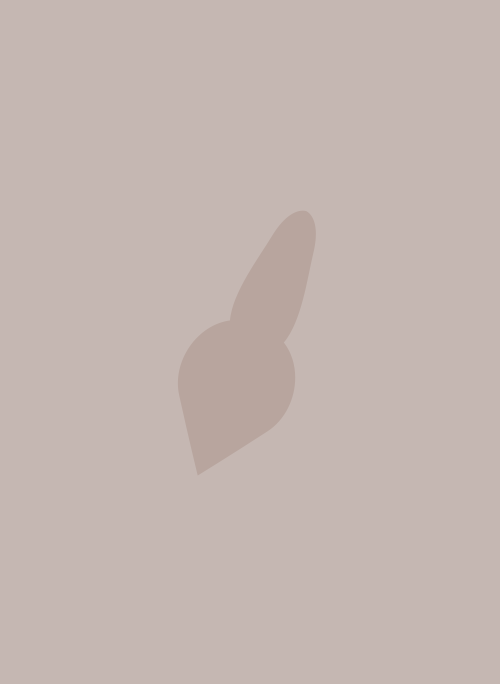藤沢の足音が遠ざかるのを確認してから、ミツキはまた聞いた。
「ねえ、なんでだまってたん?」
「別にだまってたわけやないて。いつか話そうと思っとったわ」
「じゃあ話して。とにかくいますぐ話して」
洋平はあの日の夜のことを語った。
聞き終わると、ミツキは疑いの目をむけてきた。
「ほんまに藤沢先輩のこと、ちゃんとふったん?」
「何やそれ」
「麻見君、やさしいけん、優柔不断な答え方したんやないん?」
「そんなことないて。ちゃんと断ったよ」
「でも、藤沢先輩、あきらめないって言うてるやん。言い方が甘かったんやないの?」
「そりゃあ、そうやったかもしれんけど。あんまりきつく言うんはかわいそうやろ」
「何それ?」声が急に冷たくなった。「かわいそうって何なん?あのひと、わたしらの仲、邪魔しようとしてるんで。そんな遠慮なんかいらんやろ」
「いや、わかるけど。わかるんやけど、あかんねん。びしっと言わないかんのはわかるんやけど、藤沢先輩がどんな気持ちになるかと思うと、やっぱりあかんねん」
洋平は荒々しく頭をかいた。ミツキの視線が痛かった。
「何、いいひとぶってるん?」
「そんなんやないて」
「もうええ。話にならんわ」
ミツキはため息をついて上を向いた。そして、
「偽善者」
とつぶやくと、立ち上がり、わざと大きな足音をたてながら部室から出ていった。
洋平はソファに寝転がった。
「どないせえっちゅうねん」
大声をあげた。
ミツキの言いぶんはわかるが、あそこまで怒ることはないだろうと思った。自分は藤沢をふったのだ。そりゃあ、言い方が弱かったかもしれないが、言うべきことは言ったはずだ。ひとをふるのは疲れるのだ。傷つけたくなくても、相手を傷つけないといけない。それをやりとげただけでも、大したものではないか。
「ちくしょう」
洋平は寝転がったまま、テーブルを蹴った。