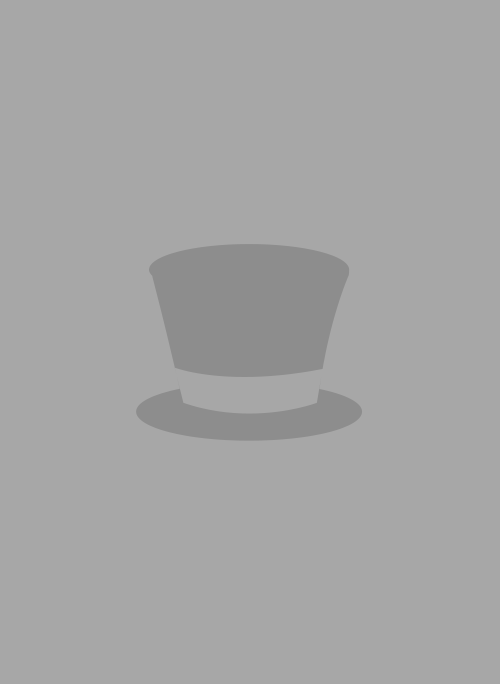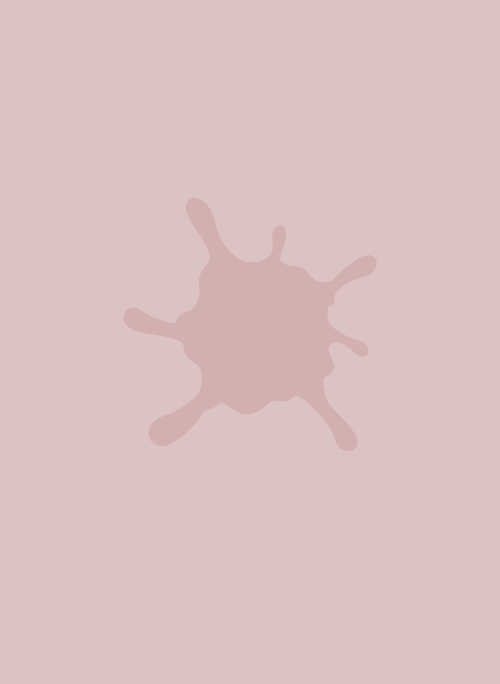窓の外をふと見ると、赤みが帯びた金色の空が、青色の闇に着々と移り変わりそうだった。
――早く帰っても、俺を待つ家族は、いない……。
活力、それは曜子だった。
あいつさえいれば、幸せな気持ちになれたのに――本当に曜子は、いなくなってしまったんだろうか?
今の俺に残された気持ちは唯一つ。怒りという名の気力だけだった。
「やあ、ごめんねぇ~? 秋山君。随分、遅くなちゃって」
静寂の中、ガラガラガラと開けられた扉に、一瞬ドキッとした。
猿田が嫌というほど、笑っている。
黄ばんだ前歯が突き出し、これほどまでに笑顔が似合わない大人を、俺は初めて見た。
――早く帰っても、俺を待つ家族は、いない……。
活力、それは曜子だった。
あいつさえいれば、幸せな気持ちになれたのに――本当に曜子は、いなくなってしまったんだろうか?
今の俺に残された気持ちは唯一つ。怒りという名の気力だけだった。
「やあ、ごめんねぇ~? 秋山君。随分、遅くなちゃって」
静寂の中、ガラガラガラと開けられた扉に、一瞬ドキッとした。
猿田が嫌というほど、笑っている。
黄ばんだ前歯が突き出し、これほどまでに笑顔が似合わない大人を、俺は初めて見た。