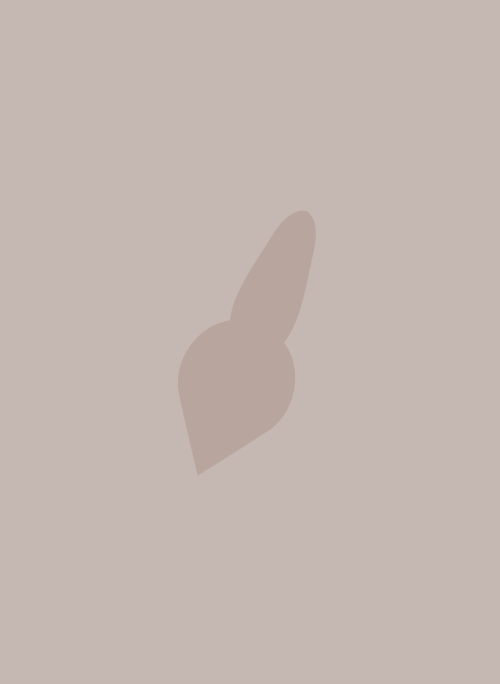お経が一通り終わり、親族が順番にお花を母さんの顔の周りにおいた。
私は、なぜか微笑みがこぼれた。そのまま、私は一礼して、席にいち早く戻った。
周りの人が、私を変な目で見る。父も同様だった。
棺に釘を打ち、棺が運ばれる。お父さんは釘打ちに意見は述べなかったんだ、と思いながら、私は遺影を選択し、墓前へ向かうバスへと乗った。
「…穂乃果」
「……何?」
途端、頬に痛みが走る。…痛い。
「何するの…」
「なんで笑ってるんだ」
「…分かってたら、私も困んないよっ!」
バスの中には、近しい親族。冷たい視線が私たちに浴びせられる。
「…ああ、わかった。泣けばいいんだよね。泣けばさっ!ろくに今まで見舞いもこなかって、いざというときに泣けとかいう、大人に私はなりたくないね」
「お前、それ本気で言ってるのか?」
「うん、本気だよ。知らない人の葬式に行かされたから、別に人が死んでも悲しくないんだよ。誰だろうね、そうさせたのは…」
もう一度、今度は逆をはたかれた。そこで秘書の人が止めに入る。
「社長…車は用意できました。いつでもいけます」
「そうか…穂乃果は、バスで行け」
荒ただしく言い放った父さんは、バスを降りて、車で走り去った。
「…私は…おかしいのかな」
「おかしくないと思いますよ」