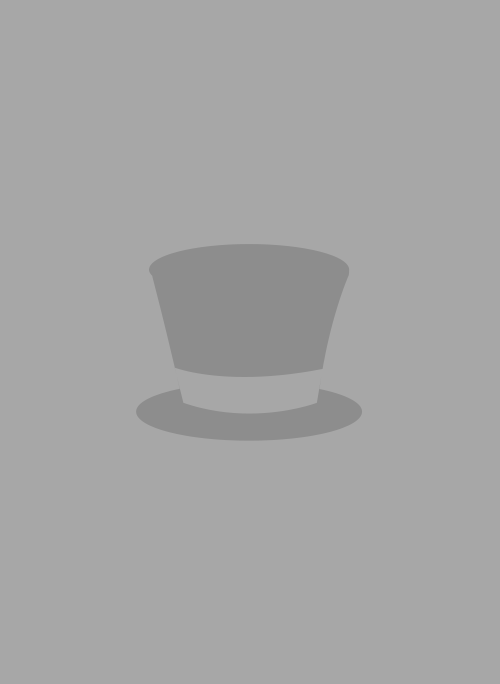長く深い一瞬が始まる予感。
そうなのだ。
今日は時間がない。
それでもこの一時に、アイツは自分の愛の全てを私に伝えようとしていた。
でも、だからこそ私は悪戯をする。
バスローブの下に洋服を着ていたのだ。
アイツの困った顔は見えない。
でもきっと目を輝かせているはずだ。
私はただ、アイツの指先を待っていた。
服が一枚ずつ剥がされていく。
その度に重なる肌が熱くなる。
項から背中にアイツはキスをする。
肌を滑る様な愛撫は私を震え立たせる。
姿が見えない分、私は感覚を研ぎ澄ます。
くすぐったいのは通り越して、快感に酔いしれる。
アイツの愛がやってくるまで、私は何度も身もだえた。
でも、アイツはそれを楽しんでいるようだった。
やはり、アイツは私の仕掛けた悪戯さえも楽しんでいたのだった。
そして、ベッドの上にさっきの辛いと言う字を指で書き始めた。
「良いかい。この字に一を加えてごらん」
私はその横に辛と言う字を書いて上に一本棒を引いた。
それは……
幸と言う字だった。
「これって……」
「辛い時は支え合えば幸せになれる、ってことだよ。だからもっと頼っていいんだよ」
アイツは涙ぐみながらそう言った。
どちらともなく唇を求め合う。
そしてそれはもっと激しいキスに変わっていった。
「みさとのお義母さんに幸せになってもらいたいな」
背中から回された手に力がこもる。
私はそっと振り向いた。
アイツは泣いていた。
「父は今、東南アジア諸国を回りながら技術者を育成しているんだ」
「え、東京じゃなかったのですか?」
そう……
私は東京にいるものだとばかり思っていた。
「心配すると思って、何も話さないで出向したんだよ。勿論俺も一緒に。でも俺は大学に行くために帰ってきたんだ」
「お義父様は凄い技術者だって聞きましたが、やはり……」
「ああ、だから一緒に行った俺はかなり優遇されていたんだ」
「あっ、もしかしたらさっきの寮って」
「うん、其処だった。どう言う訳か、男ばかりにもててさ……。だから本当にみさとが初体験なんだ」
アイツは頭を掻き掻きベッドの隅に座った。
何故アイツがそんなことを言い出したのかは解らない。
でもそれは思いやりの心で溢れていた。
そうなのだ。
今日は時間がない。
それでもこの一時に、アイツは自分の愛の全てを私に伝えようとしていた。
でも、だからこそ私は悪戯をする。
バスローブの下に洋服を着ていたのだ。
アイツの困った顔は見えない。
でもきっと目を輝かせているはずだ。
私はただ、アイツの指先を待っていた。
服が一枚ずつ剥がされていく。
その度に重なる肌が熱くなる。
項から背中にアイツはキスをする。
肌を滑る様な愛撫は私を震え立たせる。
姿が見えない分、私は感覚を研ぎ澄ます。
くすぐったいのは通り越して、快感に酔いしれる。
アイツの愛がやってくるまで、私は何度も身もだえた。
でも、アイツはそれを楽しんでいるようだった。
やはり、アイツは私の仕掛けた悪戯さえも楽しんでいたのだった。
そして、ベッドの上にさっきの辛いと言う字を指で書き始めた。
「良いかい。この字に一を加えてごらん」
私はその横に辛と言う字を書いて上に一本棒を引いた。
それは……
幸と言う字だった。
「これって……」
「辛い時は支え合えば幸せになれる、ってことだよ。だからもっと頼っていいんだよ」
アイツは涙ぐみながらそう言った。
どちらともなく唇を求め合う。
そしてそれはもっと激しいキスに変わっていった。
「みさとのお義母さんに幸せになってもらいたいな」
背中から回された手に力がこもる。
私はそっと振り向いた。
アイツは泣いていた。
「父は今、東南アジア諸国を回りながら技術者を育成しているんだ」
「え、東京じゃなかったのですか?」
そう……
私は東京にいるものだとばかり思っていた。
「心配すると思って、何も話さないで出向したんだよ。勿論俺も一緒に。でも俺は大学に行くために帰ってきたんだ」
「お義父様は凄い技術者だって聞きましたが、やはり……」
「ああ、だから一緒に行った俺はかなり優遇されていたんだ」
「あっ、もしかしたらさっきの寮って」
「うん、其処だった。どう言う訳か、男ばかりにもててさ……。だから本当にみさとが初体験なんだ」
アイツは頭を掻き掻きベッドの隅に座った。
何故アイツがそんなことを言い出したのかは解らない。
でもそれは思いやりの心で溢れていた。