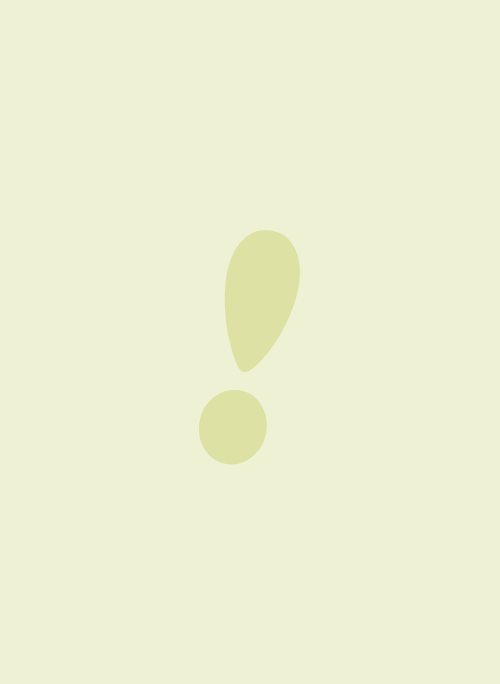「千秋!!」
私は千秋の病室へと駆け込んだ。
病室の中には、千秋のお母さんとベッドに横たわる千秋の姿があった。
「じゃあ千秋、お母さんは外に出てるから美良ちゃんとじっくり話しなさい。いいわね?」
「わかったっつの。」
千秋はぶっきらぼうに答えると寝返りをうった。
私は千秋のお母さんが病室を出たのを確認し、千秋に話しかけた。
「千秋....」
「なに?」
「どうして私にはなにも言ってくれなかったの?」
「なんのことだよ?」
「病気のことよ。」
「美良の顔を曇らせるようなことは言いたくなかった。
だから、病気のことが美良に知られる前に別れたかったんだ。」
「私と...別れたかったの?」
「美良には笑顔が似合う。
俺なんかのために悲しむより、他のヤツのために笑ってたほうがいいと思ったんだ。」
私の顔はもうすでに涙でぐしゃぐしゃだった。
「やだッ!!わ、私は千秋のためにしか笑わないもん...ッグスン」
「泣くなよ〜...困るから...
そんなこと言ってると新しい彼氏できねぇぞ?」
「千秋以外の彼氏なんていらないもん〜ッグスン....」
「........それ、本当か?」
「あ、あたりまえでしょーッ」
そこで私は泣き笑いの状態になる。
「俺も美良以外の彼女なんていらない。
だから...」
「だから?」
「俺が...俺の手術が成功したらもう一回付き合ってください。」
「手術...するの?」
「そ。その日がちょうど美良の誕生日なんだ....。」
「じゃあ、こないだ映画行けなくなったっていうのは...」
「手術するから....美良には申し訳ないけど..」
「勝手に怒ってごめん、千秋」
私はベッドに横たわる千秋に抱きついた。
「え、あ、えっとぉ.....////」
千秋は顔から耳までまるで真夏のスイカのように真っ赤だった。
「あ、そいやあれだ...、先に誕生日プレゼント渡そうと思ってさ..」
千秋はベッドの下から綺麗に包装されたプレゼントを取り出した。
「ちょい早いけど、誕生日おめでとう。」
「ありがとう!!開けていいの?」
「どうぞ。」
袋の中には、ピンクの胡蝶蘭の飾りがついたネックレスと銀色に輝く指輪だった。
「これ...指輪?」
「そ。安物だけど。でも、それ持っててくれれば、美良は俺のもんだって証明できるだろ?」
「どうして?」
「ペアリングなんだ。」
千秋はネックレスとして首にかけていたチェーンの先をTシャツから出した。
そのチェーンには私とお揃いの銀色に輝く指輪があった。
「予約ってことで。受け取って欲しい。」
「わかった。大事にする!!」
私は千秋の病室へと駆け込んだ。
病室の中には、千秋のお母さんとベッドに横たわる千秋の姿があった。
「じゃあ千秋、お母さんは外に出てるから美良ちゃんとじっくり話しなさい。いいわね?」
「わかったっつの。」
千秋はぶっきらぼうに答えると寝返りをうった。
私は千秋のお母さんが病室を出たのを確認し、千秋に話しかけた。
「千秋....」
「なに?」
「どうして私にはなにも言ってくれなかったの?」
「なんのことだよ?」
「病気のことよ。」
「美良の顔を曇らせるようなことは言いたくなかった。
だから、病気のことが美良に知られる前に別れたかったんだ。」
「私と...別れたかったの?」
「美良には笑顔が似合う。
俺なんかのために悲しむより、他のヤツのために笑ってたほうがいいと思ったんだ。」
私の顔はもうすでに涙でぐしゃぐしゃだった。
「やだッ!!わ、私は千秋のためにしか笑わないもん...ッグスン」
「泣くなよ〜...困るから...
そんなこと言ってると新しい彼氏できねぇぞ?」
「千秋以外の彼氏なんていらないもん〜ッグスン....」
「........それ、本当か?」
「あ、あたりまえでしょーッ」
そこで私は泣き笑いの状態になる。
「俺も美良以外の彼女なんていらない。
だから...」
「だから?」
「俺が...俺の手術が成功したらもう一回付き合ってください。」
「手術...するの?」
「そ。その日がちょうど美良の誕生日なんだ....。」
「じゃあ、こないだ映画行けなくなったっていうのは...」
「手術するから....美良には申し訳ないけど..」
「勝手に怒ってごめん、千秋」
私はベッドに横たわる千秋に抱きついた。
「え、あ、えっとぉ.....////」
千秋は顔から耳までまるで真夏のスイカのように真っ赤だった。
「あ、そいやあれだ...、先に誕生日プレゼント渡そうと思ってさ..」
千秋はベッドの下から綺麗に包装されたプレゼントを取り出した。
「ちょい早いけど、誕生日おめでとう。」
「ありがとう!!開けていいの?」
「どうぞ。」
袋の中には、ピンクの胡蝶蘭の飾りがついたネックレスと銀色に輝く指輪だった。
「これ...指輪?」
「そ。安物だけど。でも、それ持っててくれれば、美良は俺のもんだって証明できるだろ?」
「どうして?」
「ペアリングなんだ。」
千秋はネックレスとして首にかけていたチェーンの先をTシャツから出した。
そのチェーンには私とお揃いの銀色に輝く指輪があった。
「予約ってことで。受け取って欲しい。」
「わかった。大事にする!!」