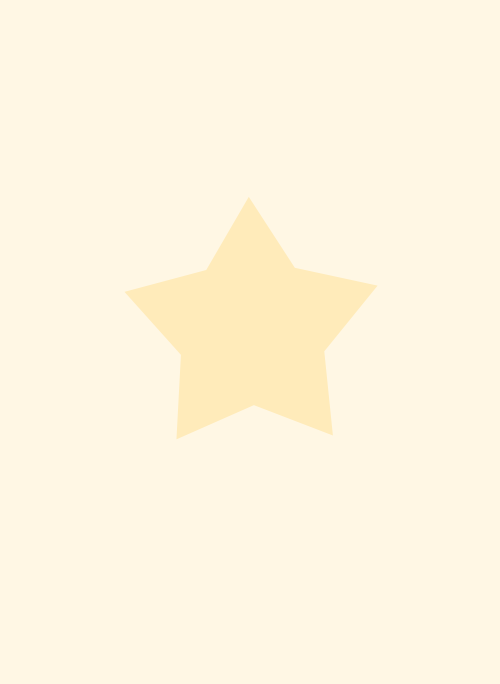大抵の人は俺を見るたび恐怖で震え上がる。
それを見るのが快感だったが、老人相手にムキになっても仕方ない。
俺は諦め、飾ってある武器を眺めると、突然後ろから声をかけられた。
「あれ?アレクサンダーじゃないのか?」
「その声は・・。」振り返るとカウンターから見知った男が姿を現した。
「おお!ロゼルフか!なんでここにいるんだ。」
「なんでって俺、ここの爺さんの孫だし。」
「あぁ、そうだったのか。」
ロゼルフは、この赤の王(俺)を護衛する傭兵隊長。
だが、それ以前にロゼルフと俺は古くからの友人だ。
「また、人を殺したのか。」錆びた剣を持ちながら揶揄するようにロゼルフは言ってきた。
「あぁ、みんなフェルツ家を支援する奴ばかりで胸くそ悪い。これだから馬鹿は困る。この国はいつか必ず俺が支配するというのに民は謀反を諮ろうとするからな・・・。」
「とんだ王だよ。」
すると新しい剣を持ったカタール爺さんが戻り、
俺は新しい剣を受け取った。
カランカラン
それを見るのが快感だったが、老人相手にムキになっても仕方ない。
俺は諦め、飾ってある武器を眺めると、突然後ろから声をかけられた。
「あれ?アレクサンダーじゃないのか?」
「その声は・・。」振り返るとカウンターから見知った男が姿を現した。
「おお!ロゼルフか!なんでここにいるんだ。」
「なんでって俺、ここの爺さんの孫だし。」
「あぁ、そうだったのか。」
ロゼルフは、この赤の王(俺)を護衛する傭兵隊長。
だが、それ以前にロゼルフと俺は古くからの友人だ。
「また、人を殺したのか。」錆びた剣を持ちながら揶揄するようにロゼルフは言ってきた。
「あぁ、みんなフェルツ家を支援する奴ばかりで胸くそ悪い。これだから馬鹿は困る。この国はいつか必ず俺が支配するというのに民は謀反を諮ろうとするからな・・・。」
「とんだ王だよ。」
すると新しい剣を持ったカタール爺さんが戻り、
俺は新しい剣を受け取った。
カランカラン