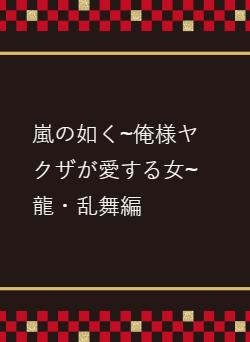あの時キチンと自分の病気を告げれば良かった。
そうすれば、社長だって無茶なコトは言わなかったと思う。
でも、正直言って…そのまま話を畳み掛けられなかった。
もっと…頼さんに近づきたかった。
彼は私を拒んでいたけど。
私は嘘でも受け入れて欲しかった。
瞼の奥が熱くなって…
目の前の頼さんの顔が霞んで見える。
「深…幸…」
優しく甘いテノールの声が私の涙腺を揺さぶる。
塞ぎ止めていた涙腺が崩壊寸前。
頼さんは私の瞳に溜まった涙にそっとハンカチで拭ってくれた。
「お前…このまま…帰れ」
「嫌です。頼さんと一緒に居たい…」
そうすれば、社長だって無茶なコトは言わなかったと思う。
でも、正直言って…そのまま話を畳み掛けられなかった。
もっと…頼さんに近づきたかった。
彼は私を拒んでいたけど。
私は嘘でも受け入れて欲しかった。
瞼の奥が熱くなって…
目の前の頼さんの顔が霞んで見える。
「深…幸…」
優しく甘いテノールの声が私の涙腺を揺さぶる。
塞ぎ止めていた涙腺が崩壊寸前。
頼さんは私の瞳に溜まった涙にそっとハンカチで拭ってくれた。
「お前…このまま…帰れ」
「嫌です。頼さんと一緒に居たい…」