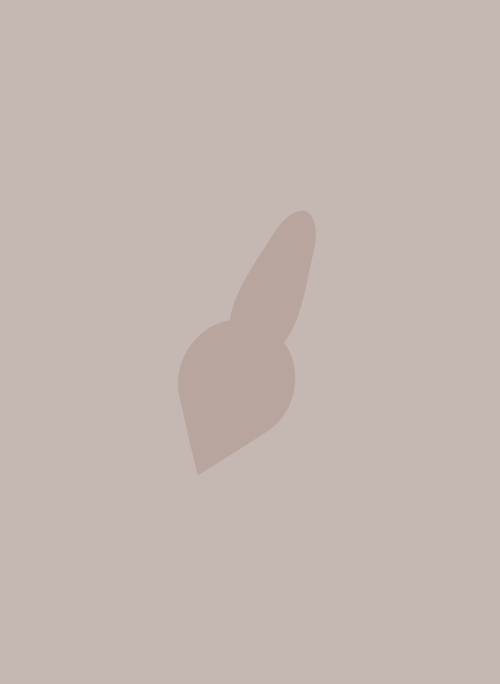注文したエスプレッソを口に含み、俺は教授に視線を戻した。
「だからね、娘は虚言癖があるのよ。」
「それは、どんなんですか?」
「高校の友達とか、いろんな場所で自分のことを偽って話してるらしいの。」
「具体的には?」
「例えば、出身地とか。他には、片親だということ、出身学校、これまでの生活のこととかよ。それにね、高級マンションに住んでるらしいの。」
じっくり教授を見ると、ちょっと年をとって見えた。
俺が大学にいた頃は、もっと子どもみたいにきゃっきゃしてたのに、急に大人になっていた。
「私もよく分からない。とにかく手に負えないから助けてほしい。」
俺は、医者になってまだ二年目だ。よく分からないまま教授の気迫に負け、その仕事を引き受けた。
「とにかく、明日探偵に協力してもらって娘を連れてくるわ。」
そう言って、教授は講義があるから、と小走りで店を後にした。
シワがついたブラウスをみながら、忙しそうだなぁ、と感じた。