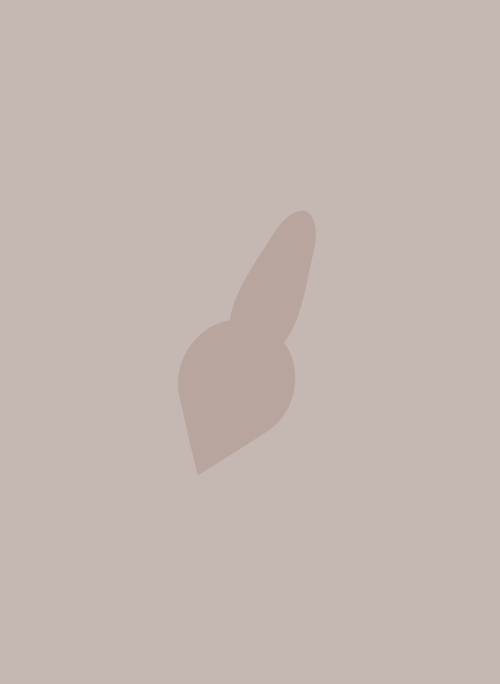昼下がりのコーヒーショップは、ひときは香ばしい薫りが充満している。
今日は日曜日で、俺も仕事が休みだ。
カップル連れが多い店内は、明るい幸せオーラで包まれていた。
そんな中、俺は二年ぶりの再開をしていた。
「教授、お久しぶりです。」
恋人ではないし、俺が25で、教授が38歳という年の差が大きい。
だが、教授はいわゆる童顔で、華奢の可愛いらしい人で、それは他人からは同年代のカップルに見えるくらいだ。
「娘を診てほしいの。」
唐突だったし、かなり早口だった。教授は席につくなり本題に入った。
「はい。そういえば、教授には娘さんがいましたよね。」
目の前にいるのは、医大でお世話になった教授だ。
「ハタチのとき産んだんでしたっけ?」
「うん。もう娘は18になる。」
若いときにできちゃった婚をして、大学も辞めずに働きながら、女手一つで育てたという。
それも、両親や相手の男の援助や手助けは一切なかったそうだ。
「勿論診断しますけど、どういう症状ですか?」
「症状というか、なんというか。」
教授はしばらく考え込んでから、虚言癖、という単語を口から零した。
「高校生になってからは、私とほとんど連絡をとらないから、正確には分からないの。」
教授は言いながら、首を傾げた。
「でもね、年齢を誤魔化して、三年前ぐらいから怪しい店で働いてるみたいなの。」
「怪しい店?なんの店ですか?」
「分からない。探偵に調べさせて、私も昨日知ったのよ。」
「それで、なんで精神科に?」
教授はいわゆる天然で、ちょっとドジなところがある。
俺はしょうがないな、と思いながら苦笑いしたが、教授の表情は固かった。
ピクリとも顔の筋肉を緩めようとしない。
なんとなく、本当にぼんやりとだが、二年前の教授とのギャップに胸が痛んだ。