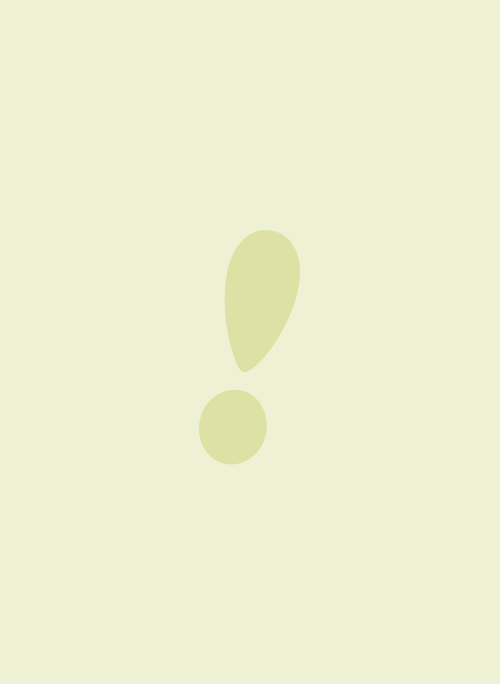「っ……妃乎さん」
まぶたをゆっくりと閉じる。
誰が髪を触っている。
兄さん?
やめて、声が出ているかわからないけど髪を触っている兄さんは優しく微笑んでいた。
「兄さん、私……」
「俺は必ず探し出す」
「なにを?」
儚い顔を祀莉に向いてもう一度髪を触る。
チュンチュンと雀の鳴き声が聞こえ、眩しく祀莉の顔に太陽が当たり、手で顔を隠す。
「ん?起きたか」
「……私……」
まだ頭がはっきりと動かない。
隣にいる人が誰かわからない。
ゆっくりと思考が蘇ってきた。
「……」
私が運んできたのは猫だったような……。その猫の名前は……。
「暉……?
さん……もしかして……猫?」
「ああ」
隠す必要がないと思っているのか認めた。
「猫?人?
どっちなの?」
「俺は」
「そうだ!!
妃乎さん。どこに行ったの?」
「……妃乎は……」
立ち上がろうとすると一瞬クラッと世界が揺れた。
壁を支え、なんとか立ち上がることができた。
外は晴れているのに雨がまだ激しく降っていた。
雷も近くにいるのか鳴り光っている。
「助けに……」
「やめとけ。
あいつのことは、諦めろ」
まぶたをゆっくりと閉じる。
誰が髪を触っている。
兄さん?
やめて、声が出ているかわからないけど髪を触っている兄さんは優しく微笑んでいた。
「兄さん、私……」
「俺は必ず探し出す」
「なにを?」
儚い顔を祀莉に向いてもう一度髪を触る。
チュンチュンと雀の鳴き声が聞こえ、眩しく祀莉の顔に太陽が当たり、手で顔を隠す。
「ん?起きたか」
「……私……」
まだ頭がはっきりと動かない。
隣にいる人が誰かわからない。
ゆっくりと思考が蘇ってきた。
「……」
私が運んできたのは猫だったような……。その猫の名前は……。
「暉……?
さん……もしかして……猫?」
「ああ」
隠す必要がないと思っているのか認めた。
「猫?人?
どっちなの?」
「俺は」
「そうだ!!
妃乎さん。どこに行ったの?」
「……妃乎は……」
立ち上がろうとすると一瞬クラッと世界が揺れた。
壁を支え、なんとか立ち上がることができた。
外は晴れているのに雨がまだ激しく降っていた。
雷も近くにいるのか鳴り光っている。
「助けに……」
「やめとけ。
あいつのことは、諦めろ」