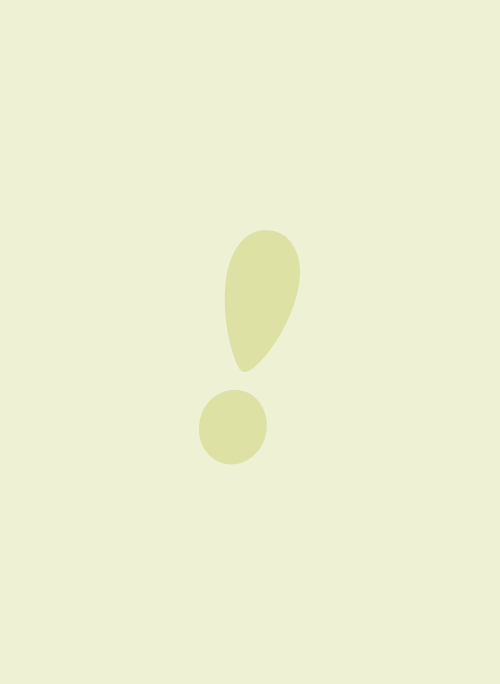「彼はきっと、貴方を頼ってたんだよ。けどそれって、貴方に対する甘えみたいなもんでしょ?」
自分の言葉が自分の胸に突き刺さる。
わたしは、甘えていた。紗枝に。
「意味がわかんないでしょ? 貴方を頼ってて、どうして貴方を裏切るのかって。」
意味がわかんない。
わたしは初めて、自分の心を冷静に見てその滑稽さをおかしいと思った。
笑えるくらい、ワケが解からない。無茶苦茶だ。
「仕返しのつもりだったんだと、思うの。そんな勝手なことをって、思うかも知れないけど、彼は貴方に裏切られたと思ってるんだよ。彼にしか解からない事情があって……、もちろん、貴方には何の関係も責任もないんだけど、それでも彼はそのことを貴方のせいにしてたの。完全な逆恨みだよね。」
わたしがそうだったように。
案の定、平井君は怪訝そうに、不機嫌そうに眉を顰めてわたしを見た。
怒るに決まってる。そんな理屈は理屈ですらない。
「だけど……、彼にとっては、貴方が助けてくれるのは当然ってくらいに、貴方を頼っていたから、さ。」
何かを感じ取ったのか、平井君は心配げな表情でわたしを見ていた。
そして、黙って聞いてくれた。
貴方のそんな態度が、わたしを図に乗らせて、親友君を調子付かせたんだよ。
内心でため息をこぼして、わたしは彼の目を見ていた。
平井君の優しさにつけこんで、調子のいい言葉を続けた。
親友君の代弁というよりも、自分自身の懺悔のような気分だった。
「カノジョを奪って、それで満足したかって言えば、たぶん全然ダメだったんだよ。だって、そもそもカノジョは何の関係もないもの。カノジョが原因なんかじゃないもの。」
思い出されていく過去の出来事は、どうしてだか、今まで忘れていた重要なキーワードだった。
鏡のように、わたしと紗枝は互いに意地を張るようになっていって。
そうと解かっていても、わたしは何もしなかった。
誤解とすれ違いが二人を遠ざける予感に、不安を煽られていた。
それでも、悪いのは紗枝だと、どうしてだか頑なに信じようとしていた。
わたしから離れていく紗枝を憎むことで、辛さから逃げようとしていた。
飛び立っていこうとする鳥を、羨んで見ていたんだ。
自分の言葉が自分の胸に突き刺さる。
わたしは、甘えていた。紗枝に。
「意味がわかんないでしょ? 貴方を頼ってて、どうして貴方を裏切るのかって。」
意味がわかんない。
わたしは初めて、自分の心を冷静に見てその滑稽さをおかしいと思った。
笑えるくらい、ワケが解からない。無茶苦茶だ。
「仕返しのつもりだったんだと、思うの。そんな勝手なことをって、思うかも知れないけど、彼は貴方に裏切られたと思ってるんだよ。彼にしか解からない事情があって……、もちろん、貴方には何の関係も責任もないんだけど、それでも彼はそのことを貴方のせいにしてたの。完全な逆恨みだよね。」
わたしがそうだったように。
案の定、平井君は怪訝そうに、不機嫌そうに眉を顰めてわたしを見た。
怒るに決まってる。そんな理屈は理屈ですらない。
「だけど……、彼にとっては、貴方が助けてくれるのは当然ってくらいに、貴方を頼っていたから、さ。」
何かを感じ取ったのか、平井君は心配げな表情でわたしを見ていた。
そして、黙って聞いてくれた。
貴方のそんな態度が、わたしを図に乗らせて、親友君を調子付かせたんだよ。
内心でため息をこぼして、わたしは彼の目を見ていた。
平井君の優しさにつけこんで、調子のいい言葉を続けた。
親友君の代弁というよりも、自分自身の懺悔のような気分だった。
「カノジョを奪って、それで満足したかって言えば、たぶん全然ダメだったんだよ。だって、そもそもカノジョは何の関係もないもの。カノジョが原因なんかじゃないもの。」
思い出されていく過去の出来事は、どうしてだか、今まで忘れていた重要なキーワードだった。
鏡のように、わたしと紗枝は互いに意地を張るようになっていって。
そうと解かっていても、わたしは何もしなかった。
誤解とすれ違いが二人を遠ざける予感に、不安を煽られていた。
それでも、悪いのは紗枝だと、どうしてだか頑なに信じようとしていた。
わたしから離れていく紗枝を憎むことで、辛さから逃げようとしていた。
飛び立っていこうとする鳥を、羨んで見ていたんだ。