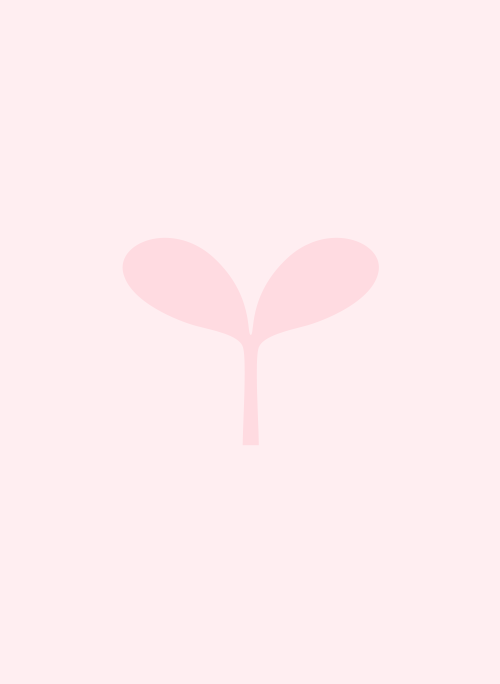それを合図にしたかのように、街に色彩が戻り始めた。
ゆっくり、ゆっくりと。
みるみるうちに町並みに彩度が戻り、
止まっていたはずの人々はそれぞれの日常を紡ぐために歩き出した。
目を見開いたまま固まっていたはずの山本やナカジも弾かれたように動き出す。
街が正常に戻った。
「那智!お前、ほんとに大丈夫か?」
「日射病?顔色悪ィぞ…どっかで休んでくか?」
山本とナカジが那智の顔を覗き込む。
(やっぱり時間が止まったことに気づいてないんだな……って、当たり前か)
おもちゃのような仕組みの世界だ。
那智は心の中で苦笑した。
たった数分の間に起こった出来事のせいで、慣れ親しんだこの世界から自分がただ一人だけ淘汰されたような錯覚を覚える。
唐突に寂しくなった。怖くなった。
山本もナカジも、何も知らない。
ただ、俺だけが異変に気づいている。
なぜだ?なぜ……
クイーンは理由を教えてはくれなかった。ただ、「運命は他人に語られるものではない」とだけ言い残して。
那智は意を決して口を開いた。
「ごめん、山本、ナカジ。俺、行かなくちゃ」
「行くって…どこだよ?病院だったら連れてくぜ?」
「いや、体はもう大丈夫。……ちょっと用事があるんだ」
「用事…?…あっ、こら、那智!」
心配する山本とナカジをよそ目に、那智は踵を返して走り出した。
山本の声がだんだんと遠くなる。
「…ッ……は、ぁ……」
息があがってきた頃、おもむろに振り向いてみた。
二人の姿はすでに人ごみにかき消されて見えない。
さっきまで当たり前のように一緒にいた友人の姿を、那智はしっかりと瞼の裏に焼き付けておいた。
なんとなく、もう……会えないと思った。