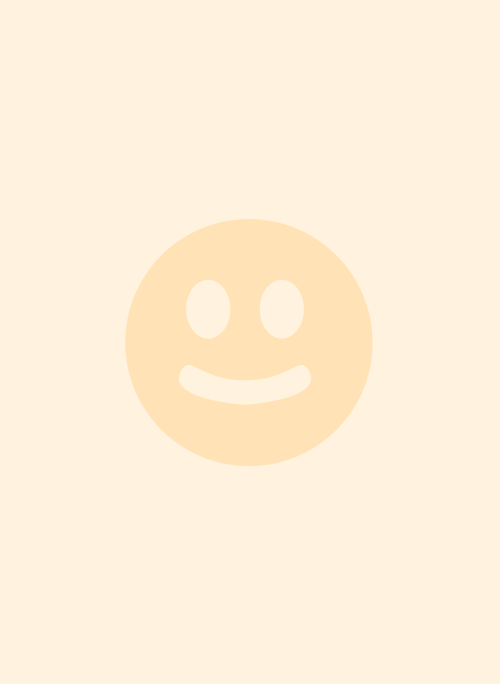俺は慌てて彼に素性を打ち明けようとした。
どうしても、彼に捨てられたくなかったから。
…
コレ、なんかキモいデスネ。
ソーデスネ。
なんとでも言えよ。
どー思われようが、それが真実だ。
俺は『死神』とまで称される無慈悲な殺し屋から与えられるぬくもりを、失いたくなかった。
空っぽの俺を忘れさせてくれるぬくもりを、手離したくなかった。
なのに彼は、俺の祈りにも似た思いを一蹴した。
心から嫌な顔をした挙げ句、盛大に溜め息を吐きやがった。
ナニ?コイツ。
冷酷非情にも程だろ。
号泣すンぞ、まじで。
でも、違った。
彼は俺が感じていたより、もっと、ずっと、あたたかかった。
『存在を許す』なんてフワっとした関係ではなく、彼は俺を認め、受け入れ、信頼を寄せてくれていたのだ。
裕福でも成績優秀でも品行方正でも王子でもない、ただのちっぽけな『俺』自身に。
もうぬくもりに縋る必要はなかった。
ぬくもりは心に満ちていた。
俺は初めて大切なモノを手に入れた。
真っ直ぐに俺を見てくれる、友人を手に入れた。
もう空っぽじゃない。
砂の城なんかじゃない。
『友人』なんて本人に言ったら もっと嫌な顔されそーだケド。