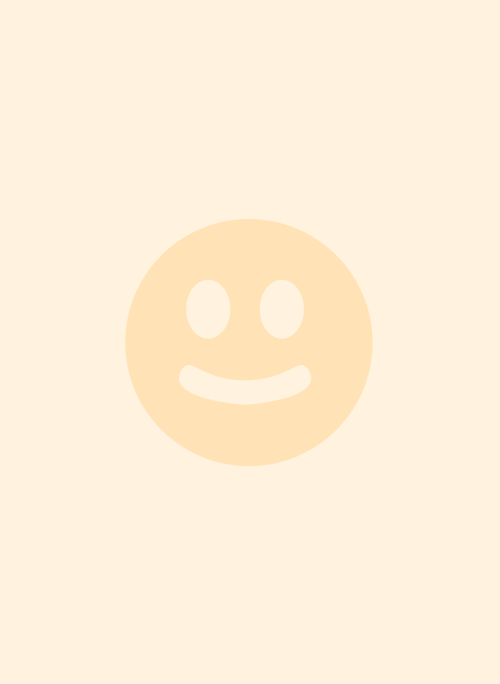ある冬の日の…吹雪の夜。
二人の樵が遭難した。
名を茂七と已之吉という。
彼らは山中をさ迷い歩き…そして崖から転落した。
「…………ぐ」
茂七は痛みから目が覚めた。
「く、くそ…」
体を動かそうとするも、動かない。
いや、動けない。
痛みが全身を貫いた。
寒さ、そんなものは一切感じない。
むしろ体が火だるまにされたような…暑い…とにかく暑かった。
目を開けると、隣には已之吉が倒れていた。
視界がぼやける。
「っ、い、いの…きち………!!!?」
彼のそばには何やら白いモノが浮いていた。
なんだ…ちくしょう視界が聞かねえ。
うっすらと浮かぶ白いもの。それは茂七が目覚めたのに気が付いたのか、ふわりと茂七のそばに身を移した。
…これは一体。
「こんばんは」
若い女の声が聞こえた。
「て、てめえは…ぐっ。
ゲホ。ゲホゲホ…。」
視界が真っ赤に染まった。
「可哀想。…あなたはもう、長くないみたい。」
女はそう呟くと茂七の顔を覗き込んだ。
真っ赤に染まった視界に映った、青い瞳。青い髪…。
一目でそれは人間であることは分かるものの、だが、それは人間ではない。
異種のモノ。
その表現がぴったりだった。
「て、てめえ。…い、一体」
「私はおしん。そんなこと言ってもわからないか。
うふふ…。」
女は楽しげに笑った…。
そして、彼女は隣に倒れている已之吉をちらりと一瞥する。
「可哀想に。この人もこのままだと死ぬね。まぁ、どうでもいいけど」
…茂七は声を震わせた。
「お、おめぇ、ま、まさか、まさか」
「わかってくれた?
私は雪女。
あんたたち人間が化け物って呼んでるモノよ。ふふ…。」
女はくるりと振り返りニタリと笑った。
「た、た、助けてくれ」
茂七は声を振り絞った。
「無理よ。…あなたは。私の力じゃどうしようもできない。」
「…俺じゃねぇ。已之吉だ。げ、ゲホゲホ!」
流血で雪が真っ赤に染まった。
「…どうしてほしいの?」
「…ぐ。グブ!」
茂七は更に口から血の塊を吐き出した。
既に視点が合っておらず、正に死に体、そのものだった。
「…わかった。あなたの望み聞いてあげる」
彼女は手を広げた。
しばらくすると彼女の手は光に包まれ、手を茂七にかざすと茂七も光に包まれた。
ドサドサドサ!
傍らの木から雪が落ちた。
「これで痛みもひいて、喋りやすくなったんじゃない?」
おしんはそう言うと、茂七の上半身を抱き上げた。
茂七は目を開いた。
不思議なことに痛みも引き、そして暖かい。
「お、お前、何をやった…」
…心地よい暖かさ。
その表現がぴったりだった。
「私の力よ。さぁ、望みを聞くわ。」
「本当か?す、すまねえな。…頼む。已之吉を…あいつを助けてやってくれないか?」
「そこの人?」
「そうだ…。奴はまだ若い。まだまだ人生を楽しんでほしい。いや…まだまだこれからなんだ。だから…」
「そうか…。あなたたち、親子なのね。」
「…違う。あいつとは血の繋がりはない。」
茂七はつぶやいた。
「そう…なの?なのになんで…」
「血の繋がりはないが、あいつは俺たちで育て上げた、息子のようなものだ。
あいつは小さい頃両親を亡くし、一人泣いていた所を俺たちが引き取った。
そしてあそこまで育て上げたんだ。血が繋がってなくても…。あいつは、あいつは俺たちの子供みてえなもんなんだ。」
茂七はつぶやくと已之吉を見つめた。
「血の繋がりがないのに助けたいの?…人間って、不思議だわ…。」
「お前も親になればわかるはずだ。」
茂七はおしんに目を移した。
そしておしんを見つめると不意に笑いだした。
「くくく…。ははは。」
「何よ。何がおかしいのよ。」
「いや…、雪女郎が…。こんなにも若くて美しい娘だなんて思わなかったからよ。」
「何よそれ。…冷やかし?」
おしんは眉をひそめた。
「冗談なんかじゃないんだぜ…。おしんさん…。それにまさか俺の願いまで聞いてくれるとは…。
どうやら俺たちは誤解していたみたいだ。雪女ってゆう奴は恐ろしい姿をした老婆だとばかり思っていたよ。」
「いいわよ。別に。それに仲間にはそんな人もいるから…」
おしんは苦笑した。
「本当にすまんな…。
おしんさん、已之吉を助けてやってくれ。あいつの命は絶対助けてやってくれ。俺の…、俺の最初で最後の一生の、一生の頼みだ。」
「わかった…。必ず、彼を治療をして家に送り届けます。約束します…。」
「すまねえな…。ありがとう。本当にありがとう…」
茂七の目からうっすら涙がこぼれおちた。
「安らかに眠ってください…」
おしんは茂七の体を再び地面におろし、手を合わせた。
それからも雪は相変わらず降り続いていたが、光に包まれた茂七の亡き骸に
その冷たい雪が積もることは決してなかったという…。