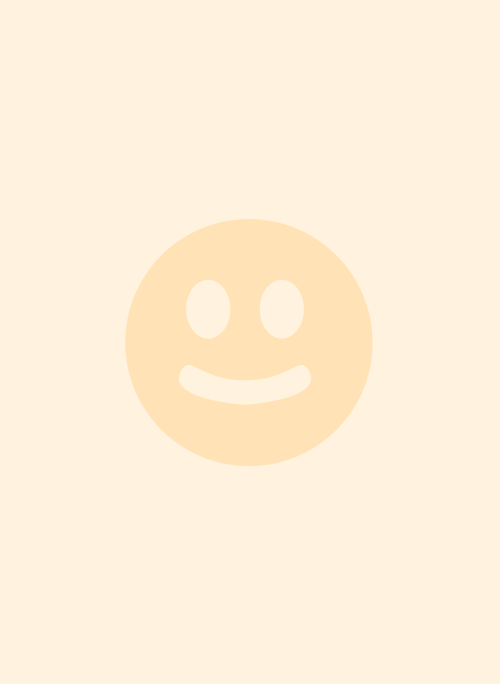…その日は夕方をすぎると雲がかかってきており月明かりもなく、辺り一面漆黒の闇だった。
だが、屋敷のわずかな残り火が赤く、周囲の風景を薄暗く照らしていた。
「おきぬ…」
おしんはうっすらと目を開けた。
「お姉…。」
おきぬはおしんを見つめた。
「良かった。あんた無事だったのね…。
あの金髪の男があんたを担いでるのをみたとき、まさか死んでるかと思ったよ…。炎が来たときも…。
兎に角、良かった…。
おきぬが無事で…」
「何言ってるの?
お姉も…生きてるじゃない…。お姉。また二人でひっそりと暮らそう。山辺に帰ろう…」
おきぬは笑顔を作りつぶやいた。
「ねぇ…。好子と健太郎は。」
「……………。」
「ねぇ…。お願い。教えて…。あの子たちは?」
おきぬは隣で眠っている二人を見つめた。
「やっぱりだめだったんだね…。あれ、やっぱり泗宝仙の香りだったんだね…」
おしんはつぶやく。
「私のせいで…私のせいで、あの二人は。あの子たちは。
已之吉さんも、お母さんも………。
私が…私が人間だったらみんなこんな目に会うことなかったのに…。
うう…。うぅぅ」
おしんの目から涙がぼろぼろこぼれだした。
おきぬは歯を食い縛った。
「いいじゃん。お姉をさ、そそのかした人間が悪いんだよ。
あいつら死んで当然じゃん!お姉は悪くないよ。
お姉は悪くないんだよ!」
おしんはおきぬを睨み付けた。
「あんた…」
「だからお姉、一緒に帰ろう。
今までの事なんか忘れてさ。ね?もう終わった事なんだから仕方ないよ。」
「なんということを…。」
おしんの頬が紅潮した。
(いい。そのまま怒って!士気を高めれば必ず回復する。お姉だけでも元気になれる。)
おしんの傷の程度は…浅かった。
おきぬは彼女の傷の手当てをすませていた。
これで体力さえ、早く回復できれば…。
悲しみより怒りの方が体力回復には効果がある。
おきぬはそう思ったのだ…。