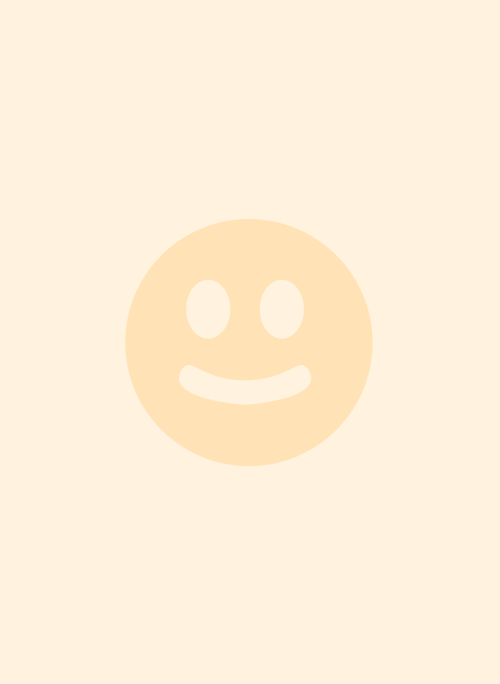あの日以来、おきぬは農耕期、収穫期はおしんの家に手伝いに行っていた。
子供たちはまだ小さく、手伝いの手にはならないので、トミが面倒を見ていた。
…例の話題は二人の間では完全にタブーになり、
特に何もない平穏な毎日を送っていた。
また、ある情報がそれが永遠に続くことが約束された…。
そしておきぬは手伝い賃としてもらったお金で、おきぬの住む山辺の妖魔たちと温泉旅行に行く、それがセオリーになっていた。
…彼らはおきぬから変身術を教わったため、人間の姿に変化できるようになっていた。
全てが順風満帆だった。
…何もない平穏な日々。
おきぬがおしんの前に現れて以来、それが五年近く続いていた。
ある日の農耕期。
「おきぬちゃんも大分田植えの手が早くなったね!」
おきぬが田植えに勤しんでいると、隣の田んぼの松本の妻が感心しながら語りかける。
おきぬは顔を上げ汗を拭うと悪戯っぽく笑った。
「そりゃあコキ使われてますからね。あはは!」
「おきぬ!何よ。それ!」
後方でおしんの怒鳴り声が聞こえた。
「本当の事じゃないのよ~。」
おきぬはすごすごと肩をすくめた。
「本当にあなたたち仲がいいわね!」
奥さんはそういいながら笑う。
彼女の旦那が苗棚を畦から下ろし葉巻に火をつけた。
「もう昼だからよ、そろそろ一服しようじゃないか!」
と大声を張り上げた。
「あいよ!おきぬちゃん、おしんさんお昼にしましょう!」
「あ、はーい!」
「やった!昼だ昼だー!お腹空いたっ!」
おきぬが駆けようとした
その時、足が泥にとられた。
「うわったったっ!」
たたらを踏んだおきぬは…
後の光景は読者の皆さんのお察しの通り…
「おきぬちゃん大丈夫!?」
「うー、泥だらけだあ。」
「全くしょうがないわね、あんたは…
早く家に帰って着替えてきなさい。」
おしんは苦笑しながら頭に巻いていた手拭いをほどき、おきぬの顔を拭いた。
松本夫妻はそんな二人の姉妹のやりとりを微笑みながら見つめていた。
…とある日のなんともない日常の光景である。
おきぬは幸せだった。
姉と仕事できるとは夢にも思わなかった。
また人間の優しさ。
この村にはそれが溢れていた。
おきぬは何度か出稼ぎなどで各地を働いて来たが、正直、残酷無比な人間とは未だ出会っていない…。
しかし、一方では妖怪たちを排除しようとする。
おきぬたちは人間の前では自身が妖魔であることを隠し、日本人と変わらぬ格好に変装していたとはいえ、人間とは恐ろしく残酷な生き物と幼い頃教わり、またそれが頭に叩き込まれていた。
しかし同族だと助け合い、そして支えあいながら生きている…。
変わった生き物だ。人間というのは…。
人と接するうち、最近ではそう感じるようになっていた。