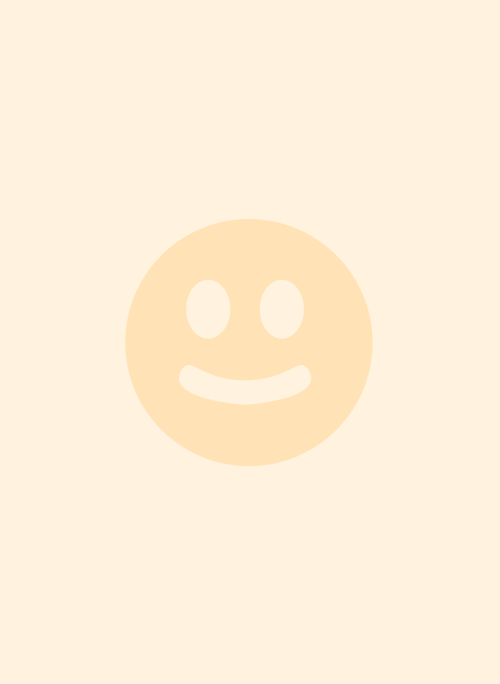そんなある日、おしんは已之吉に連れられて、ある場所にやってきた。
寺に入り、境内を抜けると整然と墓石が並べられていた…。
彼はとある墓石の前で歩を止めた。
「…ここは私の親父の墓です。」
「…お父さんの?」
「はい。前にも話しましたが覚えてますか?」
彼女の脳裏に思い浮かんだ。それは、茂七の亡くなる直前に聞いた言葉…、そしておしんが看病しているときに聞いた、已之吉の話だった。
彼らから感じ取ったもの。…それは絆だ。
人間は不思議な生き物だ。どんなに疎遠でもお互い一緒になり、一定の絆をひとたび越えると、それは自分の命を投げ出しても他人を守ろうとする。
利己・営利、そんなものを投げ出してでも…
例え自分の命が危うくてもそれは通用する…。
「私にとって茂七さんは色んな意味で尊敬できる人だった…。正に父親のような存在だった…。
でも血はつながっていない。
両親のいない私を、…そんな私を彼は愛情たっぷりに育ててくれました。
だが…たった一つだけ、すまないことをしてしまった…。」
「すまないこと?」
「ええ。」
息を流すように彼は呟いた。
たちまち已之吉の顔が曇った。
「…生前、私は茂七さんを一度も親父と呼べなかった。
…むしろ私は茂七さんにずっと敬語で話していました。
心のどこかで壁を作っていたのか…。
わからないのですが、それが未だに心にひっかかっているのです。
私が「茂七さん」と…
そう、名前を呼ぶと、時折茂七さんはひどく寂しい顔をしていることがありました。」
そう言うと已之吉はうつむいた。
おしんは「それは…」
と語りかけたその時…。
…え?
泣いてる…。
已之吉は肩を震わせていた。
「あんなに世話になったのに…。俺にとって本当の親父は、本当の親父は茂七さんだったのに。なのに…なのに…」
歯をくいしばり、拳を握りしめ已之吉の目からは大粒の涙がボロボロこぼれおちた。
おしんは已之吉に寄り添い彼の肩をだいた。
「ダメですよ。已之吉さん…。茂七さんの前で涙なんか見せちゃ…。」
已之吉は真っ直ぐな青年だ…。
素直で実直。
そして穏やかで誰よりも優しい…。
彼を…支えてあげたい。
そんな想いが彼女の脳裏によぎった……。