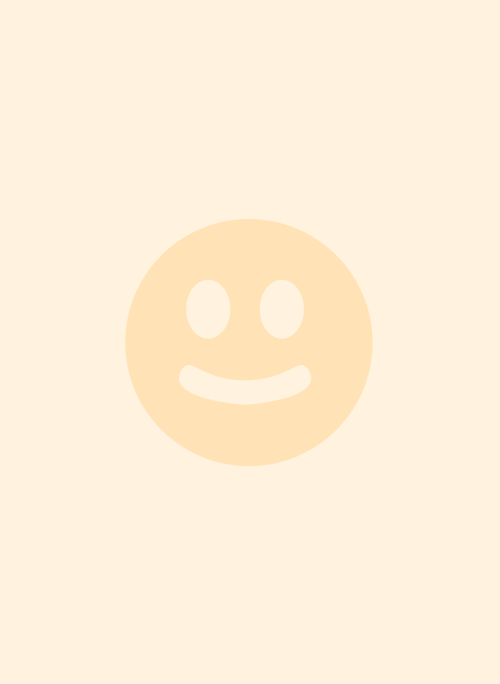時は明治43年…。
ある暑い夏の日の夕暮れ刻…。
八雲はその日の講義を終え、帰宅の途についていた。
…彼は立ち止まった。
自宅玄関の前に見知らぬ者が立っていたのだ。
誰だ…あれは。
その容姿は異様だった。
真っ白い白装束を身に付け、口・鼻まで覆う白色の御高祖頭巾を巻いていた。
八雲は様子を窺おうと物陰に隠れようとした。
…その時だった。
それはこちらを振り向いたと思うと突然足早に八雲に向かって歩いてきた。
「小泉八雲さんですか?」
若い女の声だった。
「なんですか…あなた。私に何か。」
訝しげにその女を見つめた。
「…驚かしてしまい、申し訳ありません。」
女は深々と頭を下げた。
「小泉八雲さん…あなた今、小説を書いてますよね。あたしに…少しだけお手伝いさせていただけませんでしょうか?」
「手伝い?あなた、一体何を言って…」
「あたしは…あたしはただ自分の罪を償いたいだけなんです…。」
女は八雲をじっと見つめた…。
彼女の青い瞳が顔を覆う布地の隙間から見えた…。
その女の瞳からは輝きが消え、それはまるで蝋人形のように生気の感じられない、虚ろなものだった。