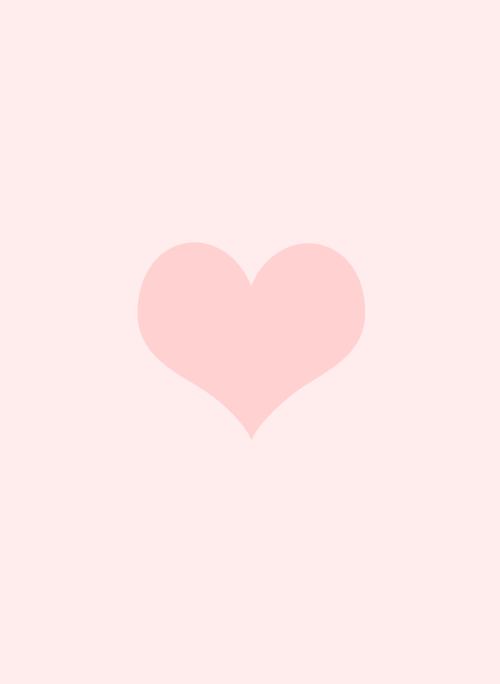「オイ、帰るぞ」
コン、と小気味よい音がして、後頭部に鋭い痛みが走った。
「いっ…った、滝先輩!痛いです!」
「お前が遅いからだろ、アホ」
振り返った先には、パーカスの滝先輩が仏頂面で立っていた。
左手にはケース。右手には剥き出しのスティック。
これで私の頭を叩いたのだろう。
「先輩が脳細胞をスティックで破壊するから、アホになっちゃうんです!」
「いいや、俺はそのアホさを叩いて直してやろうと思ってだな…」
ペン回しの要領でくるくるとスティックを器用に回転させて、ケースに収める。
その動きはいつ見ても感動する。
まるで、スティックが命を吹き込まれたかのようだ。
「とにかく、帰るぞ」
「はーい…先輩、お疲れ様でした!」
「お疲れ様、気をつけてねー」
千尋先輩に挨拶したあと、先に歩き出した滝先輩の背中を追って帰路についた。
コン、と小気味よい音がして、後頭部に鋭い痛みが走った。
「いっ…った、滝先輩!痛いです!」
「お前が遅いからだろ、アホ」
振り返った先には、パーカスの滝先輩が仏頂面で立っていた。
左手にはケース。右手には剥き出しのスティック。
これで私の頭を叩いたのだろう。
「先輩が脳細胞をスティックで破壊するから、アホになっちゃうんです!」
「いいや、俺はそのアホさを叩いて直してやろうと思ってだな…」
ペン回しの要領でくるくるとスティックを器用に回転させて、ケースに収める。
その動きはいつ見ても感動する。
まるで、スティックが命を吹き込まれたかのようだ。
「とにかく、帰るぞ」
「はーい…先輩、お疲れ様でした!」
「お疲れ様、気をつけてねー」
千尋先輩に挨拶したあと、先に歩き出した滝先輩の背中を追って帰路についた。