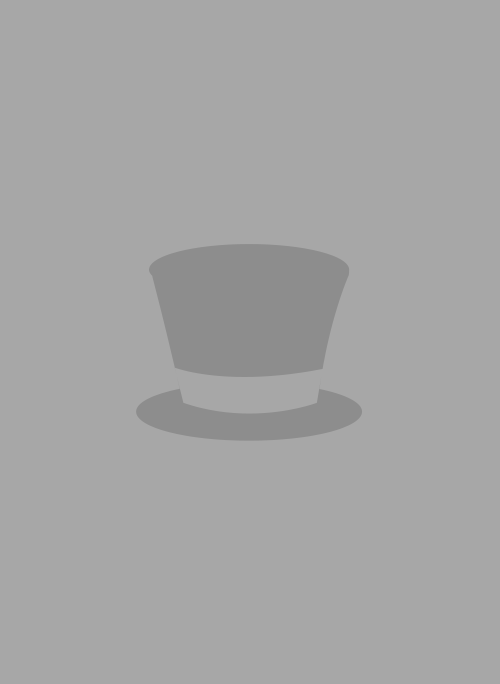僕らは外の階段に腰かけた。
「寒くない?」
「いや、今すごい火照ってて、
気持ちいいよ。」
「ならいいけど。」
「修君。」
「ん?」
「あたしね、
ピアノがめちゃくちゃ
コンプレックスだったの。
うまく弾けなくて、
どんどん落ちこぼれて、
同い年の子たちは、
音大目指してどんどん
うまくなっていった。
中学の時、
合唱の伴奏を頼まれて、
でもうまく弾けなくて、
だから
先生のとこに毎日通ってたら、
部活を毎日抜けるから、
先輩に呼び出されて、
まじめにやれって。
もお、
いやだった。
ピアノなんか弾きたくなかったよ。」
「そんなことあったんだ。」
「寒くない?」
「いや、今すごい火照ってて、
気持ちいいよ。」
「ならいいけど。」
「修君。」
「ん?」
「あたしね、
ピアノがめちゃくちゃ
コンプレックスだったの。
うまく弾けなくて、
どんどん落ちこぼれて、
同い年の子たちは、
音大目指してどんどん
うまくなっていった。
中学の時、
合唱の伴奏を頼まれて、
でもうまく弾けなくて、
だから
先生のとこに毎日通ってたら、
部活を毎日抜けるから、
先輩に呼び出されて、
まじめにやれって。
もお、
いやだった。
ピアノなんか弾きたくなかったよ。」
「そんなことあったんだ。」