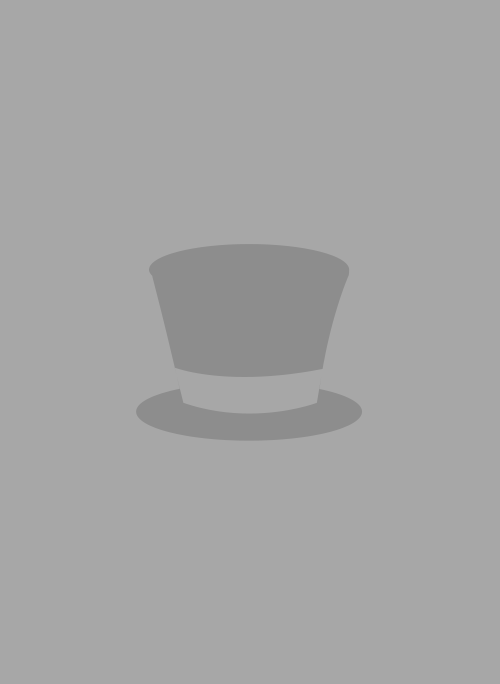僕は彼女に花束を渡そうと、
演奏が終わるとすぐ控室に行った。
でも彼女はいなかった。
ドレスのまま
外に出ていた。
「何してんの?
寒いよ。」
彼女に僕のジャンパーをかける。
「ありがとお。
あー、
最高に気持ちよかった。」
「これ、
花。」
「え?
ほんとに?ありがとう!!
きれい。
修君が選んだの?」
「うん、まあ。」
「いい匂い。」
「すごかった、
ありあちゃん。」
「修君はガッチガチだったね。」
「うん。
もお記憶ないもん。」
「あはは!
最初はそんなもんでしょ。」
演奏が終わるとすぐ控室に行った。
でも彼女はいなかった。
ドレスのまま
外に出ていた。
「何してんの?
寒いよ。」
彼女に僕のジャンパーをかける。
「ありがとお。
あー、
最高に気持ちよかった。」
「これ、
花。」
「え?
ほんとに?ありがとう!!
きれい。
修君が選んだの?」
「うん、まあ。」
「いい匂い。」
「すごかった、
ありあちゃん。」
「修君はガッチガチだったね。」
「うん。
もお記憶ないもん。」
「あはは!
最初はそんなもんでしょ。」