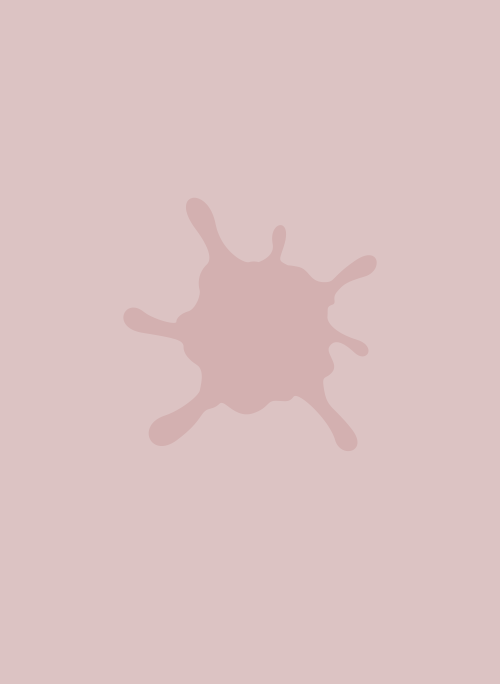「じゃあ、おばあちゃん、何か食べさせてあげて」
「わかった。こっちは任せな」
サキさんは小さくうなずくと、そっと出て行った。
私は背もたれのない三本足のいすに座っていた。あんまり泣いたから、鼻が詰まって息苦しかった。
ここは、調理室。ぴかぴかに磨き上げられたシンクと調理台が見えた。
小さなスイングドアを開けて、奈美ばあちゃんが戻ってきた。
「さ、どうぞ」
そう言って、湯飲みを渡してくれた。
「ありがと」
ひと口飲んだ。ほどよく温かいお茶は、私の極度にこわばった心と体を緩めてくれるようだった。湯気で少し鼻が通るようになった。
奈美ばあちゃんは、からになった木箱をテーブル代わりにして、お盆を載せた。
私の向かい側にいすを引きずってきてちょこんと腰掛ける。私はきっと泣きはらした目をしてる。でも奈美ばあちゃんは何も訊かない。
「ちょうど十時の休憩に入るところだったんだよ」
そう言うと奈美ばあちゃんは、お盆に載っていた菓子鉢からおせんべいをがさりと取った。
口に運んでブォリブォリと豪快な音を立てて噛み砕いた。
もう一方の手で、湯飲みをつかむとふーふー吹いてからちょびっと飲んだ。
奈美ばあちゃんの食べっぷりにつられて、私もおせんべいを一枚手に取った。
香ばしいにおいと、焼き海苔の香りが鼻をくすぐる。
一口かじってみた。甘辛い砂糖醤油の味が口いっぱいに広がった。
「おいしい!」
おせんべいがこんなにおいしいなんて。
奈美ばあちゃんが満足そうな笑みを浮かべた。
「そうだろ、そうだろ。何せ奈美ばあちゃんの特製だからね」
「えっ、このおせんべい、おばあちゃんが作ったの」
「そりゃそうさ。あたしゃこのホテルの一流シェフだからね。せんべいだろうが、シュークリームだろうが、何でも作るよ」
す、すごい。私は尊敬のまなざしで奈美ばあちゃんを見つめた。
「わかった。こっちは任せな」
サキさんは小さくうなずくと、そっと出て行った。
私は背もたれのない三本足のいすに座っていた。あんまり泣いたから、鼻が詰まって息苦しかった。
ここは、調理室。ぴかぴかに磨き上げられたシンクと調理台が見えた。
小さなスイングドアを開けて、奈美ばあちゃんが戻ってきた。
「さ、どうぞ」
そう言って、湯飲みを渡してくれた。
「ありがと」
ひと口飲んだ。ほどよく温かいお茶は、私の極度にこわばった心と体を緩めてくれるようだった。湯気で少し鼻が通るようになった。
奈美ばあちゃんは、からになった木箱をテーブル代わりにして、お盆を載せた。
私の向かい側にいすを引きずってきてちょこんと腰掛ける。私はきっと泣きはらした目をしてる。でも奈美ばあちゃんは何も訊かない。
「ちょうど十時の休憩に入るところだったんだよ」
そう言うと奈美ばあちゃんは、お盆に載っていた菓子鉢からおせんべいをがさりと取った。
口に運んでブォリブォリと豪快な音を立てて噛み砕いた。
もう一方の手で、湯飲みをつかむとふーふー吹いてからちょびっと飲んだ。
奈美ばあちゃんの食べっぷりにつられて、私もおせんべいを一枚手に取った。
香ばしいにおいと、焼き海苔の香りが鼻をくすぐる。
一口かじってみた。甘辛い砂糖醤油の味が口いっぱいに広がった。
「おいしい!」
おせんべいがこんなにおいしいなんて。
奈美ばあちゃんが満足そうな笑みを浮かべた。
「そうだろ、そうだろ。何せ奈美ばあちゃんの特製だからね」
「えっ、このおせんべい、おばあちゃんが作ったの」
「そりゃそうさ。あたしゃこのホテルの一流シェフだからね。せんべいだろうが、シュークリームだろうが、何でも作るよ」
す、すごい。私は尊敬のまなざしで奈美ばあちゃんを見つめた。