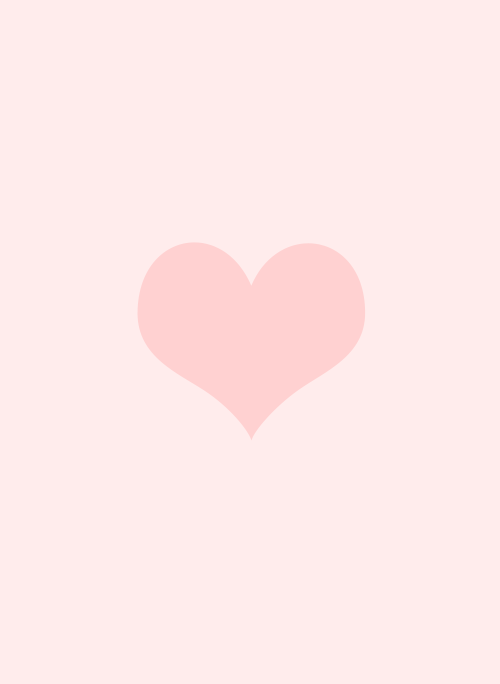「はぐれちゃうよ。行こう」
手首を掴まれ、引っ張られるのに、足を踏ん張り抵抗した。
「どうしたの、何か気になるものでもあった?」
壬生君が問いかけてくるのに、首を振って返した。
「違う、そうじゃなくて」
「あ、もしかして、迷子になったふりして帰るつもりだった?」
わたしは返せる言葉もなくて、情けなく下を向くことしかできない。
「そっか……………」
ぽんぽんと頭をなでられる。
目だけ上を向くと、壬生君は微笑みを浮かべていた。
「大丈夫だよ、俺がついてる。忘れたの? 凜がかわいいから、助けてあげたいんだ」
わざとらしく甘い声で、かわいいを強調する彼。
「あれ、もう恥ずかしくないんだ」
初めのうちは挙動不審だったわたしも、何度も言われると慣れるもので、動揺しなくなりました。
「ざーんねん。………さて、これ以上遅れるとホントまずいから、行くよ」
ホントに助けてくれると言うなら、帰らせてください。
なんて言う勇気もなく、手を引かれ、同行者と合流した。
初めからそこに居たように席に着き、自然に会話に混ざる壬生君。
凄い。
「………だよね、凜」
「へっ…!?」
いきなり話しを振られたけど、一切聞いてない。
壬生君、なんてことしてくれちゃうんですか。
「児嶋さん居たの? もう帰ったかと思った」
あからさまな上坂さんの挑発にうつむく。
ええ、ええ、さっき来たばっかりですよ。
帰ろうとしてましたよ。
帰っていいなら帰っていいって、言って欲しかった。
ここで、遠慮なく帰らせてもらいます、と、口に出せたならどんなにスッキリするでしょうか。
報復が怖いので出来ないけど。
「美男美女の中にアンタみたいなブスが1人混ざるだけで、団体の質が落ちるのがわからないの?」
昼時のフードコートの真ん中で、上坂さんが大声をあげる。
言外に帰れと言われてるのがわかる。
でも、本当に帰っていいのかな。
帰ったら帰ったで難癖つけられたりしないかな。
上坂さんの言うことに注意しながら席を離れようとすると、わたしに合わせて壬生君が席を立つ。