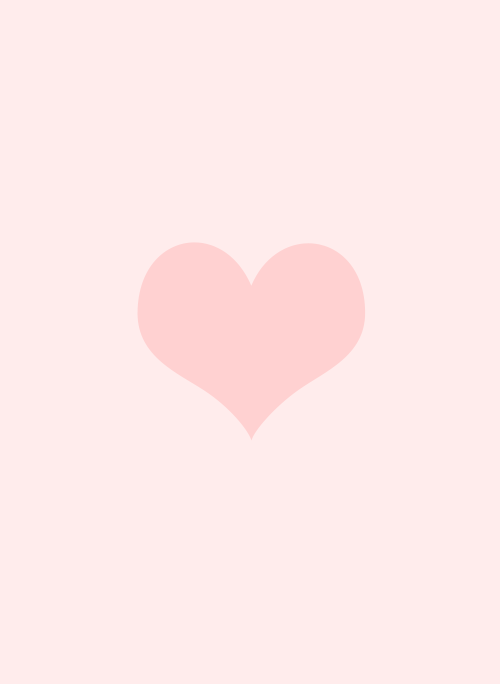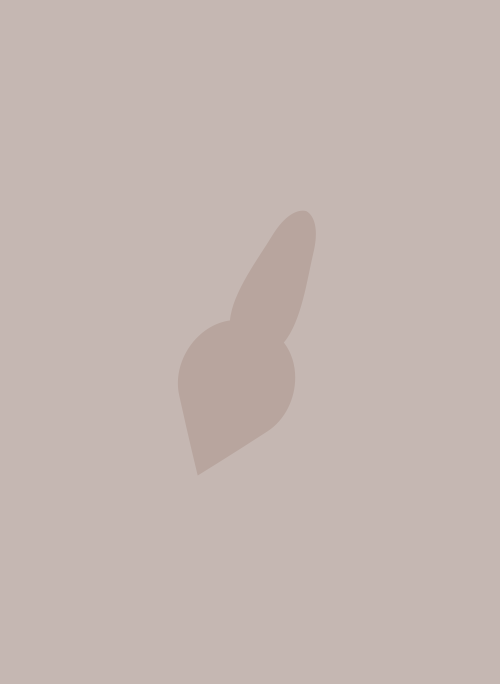階下に下ろされた私たちは、ソファにそろって座らされた。
「あさひちゃん。説明して・・・・・。」
うろうろとしたまま、義母が震える声で尋ねた。
頭はさえていた。
「見たままです。」
バシッと音がするぐらい殴られたのに、痛くない。
郁都が飛び出してきたから。
「郁都!」
とっさに触れようとするのを義母に振り払われ、ソファから落とされた。
「どっちが・・・・!」
義母が聞きたいことは分かっていた。
問題なのはどちらが先に肉体関係に持ち込んだか。
「私が誘ったの。」
「郁都は悪くない。」
「それに・・・・私たちは血がつながっているわけじゃないでしょ。」
義母の怒りはもっともだ。
でも、もともとは他人だったはず。
そんな軽い気持ちだった。
急に笑い出したのは郁都。
「あさひ。知らなかったんだ。」
「郁都!」
義母は顔色を変えていた。
「やめて!」
「あはははは。」
「僕は、あさひが知ってて・・・・それでも受け入れてくれたんだと勘違いしてた。」
暗い冷たい目。
「何を?」
「知らないって何?」
必死に尋ねる私と止めようとする義母。
郁都一人だけが冷静だった。
「僕たちの血はつながってる。」
インセストタブー。
自分がそんなことをしている自覚はなかった。
ただ、郁都から目が離せなくなったことに後ろめたさがあったことは否めない。
顔を覆ったまま義母が訴えてきた。
「今日から一人暮らししてください。
それから・・・・・もう2度とここにこないで。」
何年も本当の親子のように接していた女性が一人の強い母親として私の前に立ちふさがった。
「あさひちゃん。説明して・・・・・。」
うろうろとしたまま、義母が震える声で尋ねた。
頭はさえていた。
「見たままです。」
バシッと音がするぐらい殴られたのに、痛くない。
郁都が飛び出してきたから。
「郁都!」
とっさに触れようとするのを義母に振り払われ、ソファから落とされた。
「どっちが・・・・!」
義母が聞きたいことは分かっていた。
問題なのはどちらが先に肉体関係に持ち込んだか。
「私が誘ったの。」
「郁都は悪くない。」
「それに・・・・私たちは血がつながっているわけじゃないでしょ。」
義母の怒りはもっともだ。
でも、もともとは他人だったはず。
そんな軽い気持ちだった。
急に笑い出したのは郁都。
「あさひ。知らなかったんだ。」
「郁都!」
義母は顔色を変えていた。
「やめて!」
「あはははは。」
「僕は、あさひが知ってて・・・・それでも受け入れてくれたんだと勘違いしてた。」
暗い冷たい目。
「何を?」
「知らないって何?」
必死に尋ねる私と止めようとする義母。
郁都一人だけが冷静だった。
「僕たちの血はつながってる。」
インセストタブー。
自分がそんなことをしている自覚はなかった。
ただ、郁都から目が離せなくなったことに後ろめたさがあったことは否めない。
顔を覆ったまま義母が訴えてきた。
「今日から一人暮らししてください。
それから・・・・・もう2度とここにこないで。」
何年も本当の親子のように接していた女性が一人の強い母親として私の前に立ちふさがった。