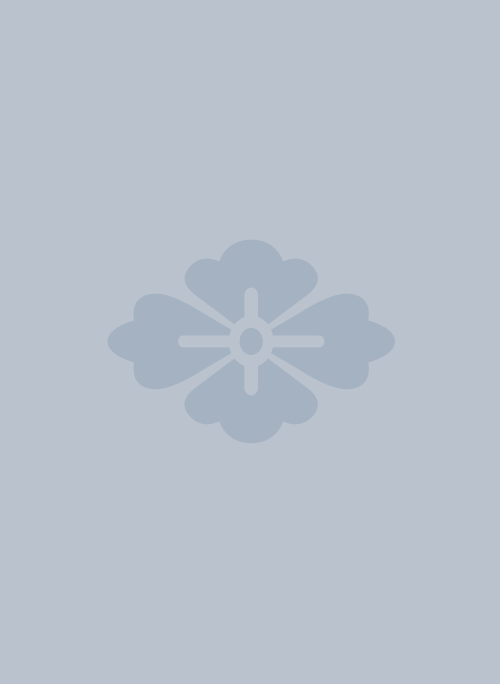あれから暫くしてどちらかが声を描けるまでもなく二人は墓場を後にした。
帰り道を歩く二人は特に話すことなく無言で足を動かす。
そんななか結子は弟の俊輔とこうして一緒に歩くのを久し振りに感じた。思えば一時間以上掛かる大学に通う結子と朝部活をする俊輔とは会ったとしても互いにじっくり話す時間が無かったと思う。
俊輔は来年で十八歳になる。高校を卒業した後の進路を決める時期がこの頃だったと記憶する。しかし本人は一向にその話題を口にしないものだから、私と義母さんからも聞くに聞けない状況であった。
何となくだが隠そうとする俊輔の行動に私は勘づいている。それを今切りだそうと口を開きかけたとき。
ニャーー
猫の鳴き声に反応するように顔を向ければ俊輔があ、と呟いた。
「またこの猫だ」
そう言って猫の方に歩いていく俊輔に私は慌てて後に着いていく。
人が近寄っても逃げない猫に珍しいなと思いながら俊輔とじっと見つめ合う猫を見た。ぶち柄のどことなく近視感を思わせる猫に何だったかと首を傾ける。そんな結子をよそに俊輔が口を開いた。
「この猫さ、鍵に付いてるキーホルダーに似てねえか?」
「ああそれだ」
私は鞄のポケットから鍵を取りだし猫と見比べるように見た。
長年使用していたためか所々色が剥がれかけたそれだが確かに目の前の猫と似ていた。
どこか満足げに鍵を仕舞おうとした私の手に大人しかった猫が急に飛び掛かってきた。
「いたっ!」
咄嗟の出来事に私と俊輔は呆然と見守るしか出来なかった。何故猫が暴れだしたのだろうかと考えた次には声を上げた。
「鍵がない」
「は、マジで?」
急に声を上げた私の発言に俊輔も目を丸くする。そしてすぐさまとある方向へ指を差した。
「姉ちゃん、あいつ!」
指の差した方向には先程の猫が居て、口元に先程私の手元に合ったキーホルダーの付いた鍵がぶら下がっていた。
「取り返さなきゃ」
「追うぞ」
姉弟同時に発したそれを合図に二人は走り出す猫の後を追った。互いにスペアキーは持っているがあの鍵は二人にとってかけがえのない物だった。互いに家を最後に出る者が鍵の施錠にはスペアキーではなく、猫のキーホルダーが付いた鍵で施錠する。あの鍵で施錠することに意味があるのだと二人は考えていた。だからこそ二人は猫を追いかけるのだった。
私と俊輔は全力で追いかけているが猫の瞬発力には勝てる訳がない。そのまま猫を見失ってしまうのはずなのに猫は時折こちらを振り替えっては走り出す。まるで猫と私達は一定の距離を空けたまま進んでいるのではないかと。
そのことに直ぐ様気が付いた私は隣で走る俊輔を見た。どうやら俊輔も同じタイミングで気が付いたみたいで互いに頷き走る速度を落としていった。
駆け出す足は次第に駆け足から緩やかな歩幅へと変えていく。それにつられるように猫も私達と同じように緩やかに前を歩くのだった。
履いていたパンプスの踵がコンクリートをコツコツと鳴らす。気が付けば景色は街並から田んぼに囲まれる。田んぼは水が張られ風が吹けば稲が水面と共に揺れている。
田んぼに囲まれた道はどこまでも真っ直ぐに伸びている。遠くの方には集落がちらほら見えてはいるがかなり遠くまで導かれたみたいだ。
ふと俊輔は時間を確認しようと歩きながら携帯を取り出す。
「まじかよ」
携帯を見たまま立ち止まってしまった俊輔につられるように私も立ち止まる。どうしたのと聞けば姉ちゃんの携帯見せてと言われバックの中から携帯を取りだし画面を開く。
「うそ、県外」
画面に移されたそれは県外と表示されていた。
「田舎だからってここが県外になるなんてあり得ないでしょ」
「すぐ近くに家だってある」
携帯片手に来た道を見回した後もう一度携帯を確認するが県外のままだった。不意に目の前を向けばあの猫が鎮座していた。
こちらを向く猫は二人を観察するようにじっと見つめていた。その異様な姿に思わず悪寒が走る。
反射的に姉の腕を掴み来た道を逆送するように走り出した。
「え、ちょっと俊!」
俊輔の唐突な行動に思考が追い付けない結子は引っ張られる様にして走った。結子は後ろ髪引かれる思いで後ろを振り返った時だった。
「ちょっ、姉ちゃん何で止まるんだよ」
立ち止まりびくともしない結子を咎めるために俊輔も後ろを振り替える。そこで目を見開いた。
「なんで、うちが見えるんだ」
見間違えるはずもない我が家が二人の目の前にある。ゆらゆらと揺れる家に二人は息を飲む。家の前には白い車が停まっていた。何故あの車があるのだろう。あの車はとっくの昔に廃棄された物なのに。
見間違えるはずもない、あの車は両親が亡くなった時に乗っていた車だったからだ。目の前のそれは両親が居た頃の日常風景だとばかりに涙が溢れでた。
二人は目の前の光景に目を離さなかった。否、離せなかった。
まるであの日が嘘だと言えるような我が家を目の前に二人は涙を流した。
変わらぬ我が家に結子は懐かしい、恋しい、あの頃に戻りたいと思ってしまった。
刹那、突如鳴き出した猫に二人はハッとしたように互いを見た。俊輔の瞼は涙で赤く腫れている、おそらく私も赤いだろう。互いの顔を見て冷静さを取り戻していく。俊輔はどこか気まずそうに頭を振る。
「帰ろう」
俊輔の小さく呟いた声に答えるように自然と足が後ろを向く。捕まれていた腕は離され行き場のなくなった腕には携帯が握りしめられている。どこか誤魔化すように画面を開いた私は次の瞬間息を飲んだ。
「時計が、壊れている」
携帯の画面には時計と日付を表示しているそれは昨日、一週間前、一ヶ月前の日付へと流れるように逆送していく。結子の携帯を見た俊輔も即座に自身の携帯で確かめたようだが焦っている表情から、自身の携帯だけじゃないことが分かった。呆然と眺めるしかない二人をよそに西暦までも過去に戻っていくのだった。一年から三年、五年前と表示が切り替わる。
気味の悪い携帯を手放そうとした瞬間目の前がぐらついた。
「いや!なにこれ」
「ちょっ、なんで」
足元を見れば先程までコンクリートだったそれは水に変わり二人を飲み込んでいく。膝から胸元まで浸水する身体はもがこうと動かすが一向に動かない。水が私達を引き込む勢いで身体が沈んでいく。唯一手だけ動いた結子は横にいる俊輔の腕を掴んだ。
「姉ちゃ……ん」
私が俊輔を掴むのと波が頭から被さるのは同時だった。呑まれるように私達は意識を失ったのだった。
ニャーー
猫の鳴き声が響く。猫は二人を呑み込んだ場所に立っていた。コンクリートの地面をじっと見た後その横で投げ出された結子の携帯が目に止まる。
その携帯には今日の日付が表示されていた。
2003年6月30日。十年前の西暦へと変えて。
帰り道を歩く二人は特に話すことなく無言で足を動かす。
そんななか結子は弟の俊輔とこうして一緒に歩くのを久し振りに感じた。思えば一時間以上掛かる大学に通う結子と朝部活をする俊輔とは会ったとしても互いにじっくり話す時間が無かったと思う。
俊輔は来年で十八歳になる。高校を卒業した後の進路を決める時期がこの頃だったと記憶する。しかし本人は一向にその話題を口にしないものだから、私と義母さんからも聞くに聞けない状況であった。
何となくだが隠そうとする俊輔の行動に私は勘づいている。それを今切りだそうと口を開きかけたとき。
ニャーー
猫の鳴き声に反応するように顔を向ければ俊輔があ、と呟いた。
「またこの猫だ」
そう言って猫の方に歩いていく俊輔に私は慌てて後に着いていく。
人が近寄っても逃げない猫に珍しいなと思いながら俊輔とじっと見つめ合う猫を見た。ぶち柄のどことなく近視感を思わせる猫に何だったかと首を傾ける。そんな結子をよそに俊輔が口を開いた。
「この猫さ、鍵に付いてるキーホルダーに似てねえか?」
「ああそれだ」
私は鞄のポケットから鍵を取りだし猫と見比べるように見た。
長年使用していたためか所々色が剥がれかけたそれだが確かに目の前の猫と似ていた。
どこか満足げに鍵を仕舞おうとした私の手に大人しかった猫が急に飛び掛かってきた。
「いたっ!」
咄嗟の出来事に私と俊輔は呆然と見守るしか出来なかった。何故猫が暴れだしたのだろうかと考えた次には声を上げた。
「鍵がない」
「は、マジで?」
急に声を上げた私の発言に俊輔も目を丸くする。そしてすぐさまとある方向へ指を差した。
「姉ちゃん、あいつ!」
指の差した方向には先程の猫が居て、口元に先程私の手元に合ったキーホルダーの付いた鍵がぶら下がっていた。
「取り返さなきゃ」
「追うぞ」
姉弟同時に発したそれを合図に二人は走り出す猫の後を追った。互いにスペアキーは持っているがあの鍵は二人にとってかけがえのない物だった。互いに家を最後に出る者が鍵の施錠にはスペアキーではなく、猫のキーホルダーが付いた鍵で施錠する。あの鍵で施錠することに意味があるのだと二人は考えていた。だからこそ二人は猫を追いかけるのだった。
私と俊輔は全力で追いかけているが猫の瞬発力には勝てる訳がない。そのまま猫を見失ってしまうのはずなのに猫は時折こちらを振り替えっては走り出す。まるで猫と私達は一定の距離を空けたまま進んでいるのではないかと。
そのことに直ぐ様気が付いた私は隣で走る俊輔を見た。どうやら俊輔も同じタイミングで気が付いたみたいで互いに頷き走る速度を落としていった。
駆け出す足は次第に駆け足から緩やかな歩幅へと変えていく。それにつられるように猫も私達と同じように緩やかに前を歩くのだった。
履いていたパンプスの踵がコンクリートをコツコツと鳴らす。気が付けば景色は街並から田んぼに囲まれる。田んぼは水が張られ風が吹けば稲が水面と共に揺れている。
田んぼに囲まれた道はどこまでも真っ直ぐに伸びている。遠くの方には集落がちらほら見えてはいるがかなり遠くまで導かれたみたいだ。
ふと俊輔は時間を確認しようと歩きながら携帯を取り出す。
「まじかよ」
携帯を見たまま立ち止まってしまった俊輔につられるように私も立ち止まる。どうしたのと聞けば姉ちゃんの携帯見せてと言われバックの中から携帯を取りだし画面を開く。
「うそ、県外」
画面に移されたそれは県外と表示されていた。
「田舎だからってここが県外になるなんてあり得ないでしょ」
「すぐ近くに家だってある」
携帯片手に来た道を見回した後もう一度携帯を確認するが県外のままだった。不意に目の前を向けばあの猫が鎮座していた。
こちらを向く猫は二人を観察するようにじっと見つめていた。その異様な姿に思わず悪寒が走る。
反射的に姉の腕を掴み来た道を逆送するように走り出した。
「え、ちょっと俊!」
俊輔の唐突な行動に思考が追い付けない結子は引っ張られる様にして走った。結子は後ろ髪引かれる思いで後ろを振り返った時だった。
「ちょっ、姉ちゃん何で止まるんだよ」
立ち止まりびくともしない結子を咎めるために俊輔も後ろを振り替える。そこで目を見開いた。
「なんで、うちが見えるんだ」
見間違えるはずもない我が家が二人の目の前にある。ゆらゆらと揺れる家に二人は息を飲む。家の前には白い車が停まっていた。何故あの車があるのだろう。あの車はとっくの昔に廃棄された物なのに。
見間違えるはずもない、あの車は両親が亡くなった時に乗っていた車だったからだ。目の前のそれは両親が居た頃の日常風景だとばかりに涙が溢れでた。
二人は目の前の光景に目を離さなかった。否、離せなかった。
まるであの日が嘘だと言えるような我が家を目の前に二人は涙を流した。
変わらぬ我が家に結子は懐かしい、恋しい、あの頃に戻りたいと思ってしまった。
刹那、突如鳴き出した猫に二人はハッとしたように互いを見た。俊輔の瞼は涙で赤く腫れている、おそらく私も赤いだろう。互いの顔を見て冷静さを取り戻していく。俊輔はどこか気まずそうに頭を振る。
「帰ろう」
俊輔の小さく呟いた声に答えるように自然と足が後ろを向く。捕まれていた腕は離され行き場のなくなった腕には携帯が握りしめられている。どこか誤魔化すように画面を開いた私は次の瞬間息を飲んだ。
「時計が、壊れている」
携帯の画面には時計と日付を表示しているそれは昨日、一週間前、一ヶ月前の日付へと流れるように逆送していく。結子の携帯を見た俊輔も即座に自身の携帯で確かめたようだが焦っている表情から、自身の携帯だけじゃないことが分かった。呆然と眺めるしかない二人をよそに西暦までも過去に戻っていくのだった。一年から三年、五年前と表示が切り替わる。
気味の悪い携帯を手放そうとした瞬間目の前がぐらついた。
「いや!なにこれ」
「ちょっ、なんで」
足元を見れば先程までコンクリートだったそれは水に変わり二人を飲み込んでいく。膝から胸元まで浸水する身体はもがこうと動かすが一向に動かない。水が私達を引き込む勢いで身体が沈んでいく。唯一手だけ動いた結子は横にいる俊輔の腕を掴んだ。
「姉ちゃ……ん」
私が俊輔を掴むのと波が頭から被さるのは同時だった。呑まれるように私達は意識を失ったのだった。
ニャーー
猫の鳴き声が響く。猫は二人を呑み込んだ場所に立っていた。コンクリートの地面をじっと見た後その横で投げ出された結子の携帯が目に止まる。
その携帯には今日の日付が表示されていた。
2003年6月30日。十年前の西暦へと変えて。