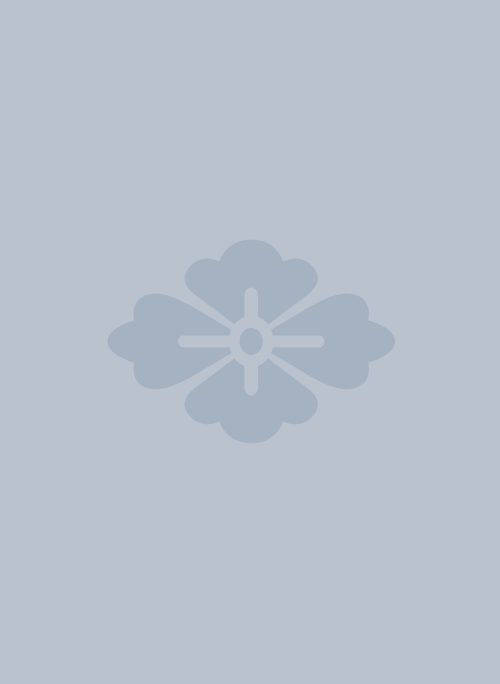結子は初めは何を言っているのだとばかりの顔をしていたが、次第にその言葉の旨を理解すれば表情が一変する。
「あたしは……どっちも選べない」
澤の手から逃れた片方の手はスカートをぎゅっと握りしめて答える姿に内心やはりか、と思った。小さい子にそんな残酷な選択なんてできるはずがない。
「皆、大好きなんだもん。俊だって同じこと言うよ、澤先生。それに………」
結子はスカートのポケットに手を入れ澤の前へと”それ”を見せた。
「お母さんに鍵を預かったの。ちゃんと家に帰らないと、駄目だよ」
結子が見せたそれは丸いぶち猫の可愛いとは言えない真新しいキーホルダーがついた鍵だった。
目の前に掲げられているそれに胸が締め付けられた。
「俺も、家に帰りたい……」
俊輔の声に二人が反応するように見れば、顔はまだベットにうつ伏せのままだった。だが先程とは明らかに違う雰囲気だった。
「……お父さんと、お母さんがいる、家に……帰る!!」
「俊君二人はもうあの家には「いる!いるよ!!」
澤の言葉を遮るように強く否定する俊の姿に結子は澤の方へと顔を向ける。
「澤先生、お父さんもお母さんも、あの家にちゃんといるよ。誰が言ったってあたしと俊は家に帰って二人を待つんだから」
二人の強い視線に澤はたじろぐ。
一歩も引かない二人の答えに澤は二人の子供だな、と諦めた。そして何かを決心するように立ち上がった。
「分かったわ。二人のおじいちゃんおばあちゃん達には先生が伝えるから、四人の時間を大切にしてね」
澤の言葉に泣きそうな結子の頭を優しく撫でれば、扉へと歩いていった。