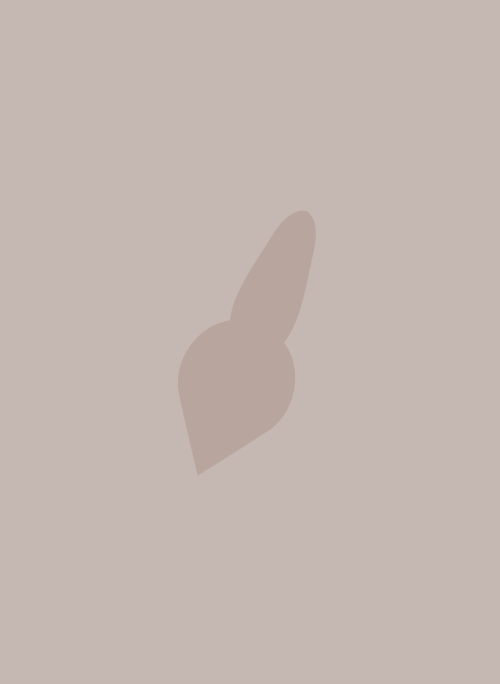「え?」
「あ、今じゃなくて。
中学の時、中2のとき。」
やっと硬かった表情に動きが見えるようになった。
「で、そのとき、すごく、すごく、周りの人に支えてもらいました。」
すごく愛しそうに笑う加藤に
ほんの少し胸は痛むけど、
でも、こっちまで幸せになるんだ。
本当に。
「…それで、特に……」
なんとなく話が見えてきてしまった。
鈍感なくせに
こんなところで察してしまう、わかってしまう自分が憎い。
特に支えてたのが、タカシだ。
それで、多分、会長のことは嫌いではないけど、やっぱりタカシが大切だって、きっとそういう話だ。
「…特に、私のことを元気付けてくれた人がいて。」
ほら、やっぱり。
「文化祭のときに来てた、あの…」
「タカシ?」
「え?なんで…」
驚く加藤に苦笑した。
それは、驚く加藤がまた可愛いって、こんな場面でさえ思ってる自分に対しての苦笑。
「ごめん、加藤に嘘ついてたことがある。」
ほら、俺今から振られんだぜ。
そんなときに可愛いなんて思ってる場合じゃねぇだろ。
「みたんだ。遊園地で、加藤と、その…タカシ?」
「え、」