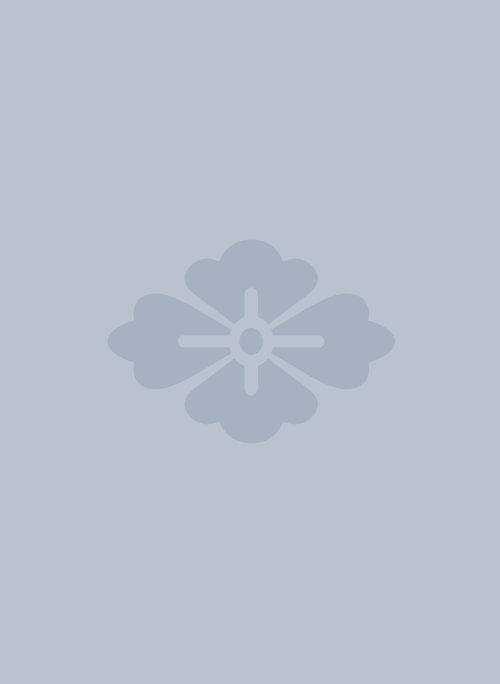視線を盃に向ければ、これが本当にあの永倉新八かと疑いたくなるような顔をした自分と目が合った。
『…随分らしくねぇこと考えてんじゃねぇかよ』
視線を落とした俺にコクリと喉を鳴らしながら酒を流してそう言う目の前の男。
その問いに再び顔を上げれば、俺を見つめる彼の瞳はかつてと同じ色をしていて。
さしで呑むのは随分と久しぶりのことだが、今も尚その色に飲み込まれてしまいそうな気分になる。
狂気と信念の奥に、それ以上の優しさを含んだ瞳に。
いつもそうだった。
見透かしたようなその目に嘘はつけなくて。
その優しさについ、似合いもしない弱音が口から溢れちまうんだ。